PROFILE
今回は、morph transcreation代表・小塚泰彦が、京都市立芸術大学准教授・中村翠さんの授業でゲスト講師としてお話した内容をお届けします。前半は「トランスクリエーション」の概要について学生に説明したプレゼンテーション、後半は中村さんと小塚のクロストークです。二人は大阪府立茨木高校の同級生。
Interview by Midori Nakamura
Text by Yuto Miyamoto
意味を設計する翻訳
小塚:「トランスクリエーション」という言葉は、20世紀半ばぐらいから英語圏で存在しています。1970年代頃からは、マーケティング・コミュニケーションの領域で主に使われてきました。しかし、権威あるオックスフォード英語辞典にも未だ掲載されていない単語なんですよね。日本においては翻訳業界以外では全くと言っていいほど知られていなくて、トランスレーション・スタディーズ(翻訳学)という比較的新しい学問領域の中でも最後尾に位置する、本当に最近になってようやく研究され始めている分野です。そのトランスクリエーションを、ぼくたちの会社では「創造的翻訳=創訳」と呼んでいます。
創訳の具体例を2つお話したいと思います。ひとつは、明太子をニューヨークで爆発的に売った日本人のエピソード。ニューヨークのマンハッタンで日本食レストランを開いたある人が、明太子のことを最初「フィッシュ・ロー(Fish Roe)」と呼びました。魚の卵、というそのままの意味ですよね。だけど、「フィッシュ・ロー(Fish Roe)」と聞いたニューヨーカーがそれを食べたくなるかというと、食欲や興味が全然そそられない。そこで店主が発想を変えて「博多スパイシーキャビア(Hakata Spicy Caviar)」と呼んだところ、一気に売れるようになったということがありました。
もうひとつは、「I love you」のいろいろな訳し方。夏目漱石が「I love you」を「月が綺麗ですね」と訳した、というのはとても有名なエピソードですけど、実はもうひとつ似たような事例があって、ジャズの名曲「Fly Me To The Moon」では、「私を月に連れて行って」を言い換えると「I love you」である、と歌われているんですね。偶然だけど、どちらも月に関連しているのが面白いなぁと思います。
明太子を「博多スパイシーキャビア」と言い換えたり、I love youを「月が綺麗ですね」と言い換えたりするためには、既存の概念の枠組みを越えていくことが大事なポイントになってきます。トランスクリエーションのtransは「越える」とか「向こうへ行く」という接頭辞です。言葉を文字通りに訳すのではなく、意味の設計を変えて、既存の概念の向こうへたどり着くようなイメージ。そう考えると、2つの事例はとても優れたトランスクリエーションですね。ぼくは最近「意味のデザイン」とも言っています。
未来の日本語をつくる
これはあくまで自分なりの解釈なのですが、「design」という言葉は「de – sign」と分けられます。「de」というのは「分離する」や「外側へ行く」、あるいは「下へ向かう」という意味をもつ接頭辞です。そこから考えるとデザインとは、物事に張り付いてる一般的な記号(sign)から、その記号内容を分離し、物事の本質や可能性を改めて検討し、解釈し直して、その上で現実世界へ落とし込むプロセスだと考えています。もともとコピーライターとしてキャリアを始めたぼくは、グラフィックデザインやプロダクトデザインではなく「意味のデザイン」を自分の専門にしようと決めて、morphという会社を立ち上げたわけです。
ぼくらの会社がいま考えているのは、新しい日本語をつくっていくこと。明治時代につくられた日本語──たとえば、「社会」「自由」「権利」「革命」といった言葉──は、日本人の近代的な思考を形成する上では大きく貢献しました。でも、もう明治維新から150年以上が経っているわけで、ずっとその言葉を使い続けていていいんだろうか?という、ちょっと壮大な問題意識があったりします。
江戸時代後期の英和辞典を持っているんですが、それを見ると「love letter」が「艶書」と訳されている。「cake」は「円形ノ餅類ノ総称」。「cabinet」はというと、「内閣」ではなく「密談」と訳されてるんですね。このように言葉が人に喚起するイメージは時代ごとに異なるものでもあります。そう思うと、「未来の日本」を構想するために「未来の日本語」を考案してもいいんじゃないか。そんなことを考えて、これから会社として取り組んでいきたいなと考えています。
正・誤の間にあるグラデーション
お話してきたように、morphというぼくらの会社は、いわゆる翻訳会社とは少し違うんですね。多言語で、戦略的に、意味をデザインする会社。そう考えています。キーワードは「新しい共感」です。明太子が「博多スパイシーキャビア(Hakata Spicy Caviar)」と呼ばれたとき、きっとニューヨーカーたちの間で「新しい共感」が生まれたんだと思うんです。
いまの時代、機械翻訳の技術はどんどん進んでいます。機械翻訳が発展すればするほど、“正しい”翻訳が増えるはずです。けれど、“正しさ”が増したからといって、必ずしも共感の強度が増すわけではない。「トランスクリエーションとは何か?」という問いに対する、いまのぼくの答えは、物事の意味をデザインして、新しい命を吹き込むこと。それは必ずしも“正しい”翻訳じゃないかもしれませんが、「正しくない何か」が新しい共感を生み出すのだと思っています。その「何か」の部分は正・誤の間にあるグラデーションで、共感の度合いによって測られる新しい尺度やアルゴリズムが必要だと感じています。
先日知ったのですが、日本のある地域で池にザリガニが大量に繁殖して困っていると。池の生態系が荒らされるのでザリガニを獲って捨てなければいけないのですが、実はザリガニは食べたらおいしいらしくて。日本にはザリガニを食べる文化がないので、おいしくなさそう、汚そう、というイメージがあって食べてもらえないわけです。そこで地元のある人がザリガニを「レイク・ロブスター(Lake lobster)」と呼んだところ、地元の人たちがザリガニを使った料理を受け入れてくれて、地域のひとつの名産品になったそうです。
言葉が変わると、認識が変わる。すると、行動が変わって、未来が変わっていく。これまでいろいろな企業とお付き合いをしてきたなかで、ぼくらはそうした変化を何度も見てきている。いわば意味の専門家として、その変化に働きかけるということが、トランスクリエーションの果たすべき役割なんだとぼくは思っています。
3つの次元を横断する言葉
中村:ありがとうございました。morphで手がけられているお仕事の事例があればぜひ教えてください。
小塚:これはクライアントワークではないのですが、最近自社で「駅訳/TranStation」という独自のサービスをつくりました。東京の主な駅の「駅名の意味と由来」が英語でわかる路線図です。

たとえば、「お茶の水」をクリックすると、右側に「Tea Water」と表示が出てきます。「神保町」は「Divine Protection Town」、四谷は「Four Valleys」というように、日本語の音だけではわからなかった駅名の意味が英語でわかるようになっています。そしてさらに、四谷ならなぜ「四谷」という駅名になったのか、という歴史を調べて載せているんです。

駅名って、その土地の歴史や文化や地形がもとになって付けられているじゃないですか。その意味を知ることによって、海外の観光客がまた日本に来るときに、「あそこへ行ってみよう」という新しいモチベーションになるんじゃないかと思って立ち上げたサービスです。
中村:「駅訳」という文字が面白いですよね。駅と訳って両方、右側が「尺」じゃないですか。その見た目も非常にインパクトがあるというか、一瞬「同じ文字が並んでいるのかな?」と空目してしまう。それから英語の「TranStation」も「translation」に音が似ているし、「train」を想起させるような音でもある。そうした意味で、「駅訳」も「TranStation」も興味深い単語だなと思いました。
言語情報には、「意味」「形」「音」の3つの異なる次元がありますよね。形而上的な意味を伝える機能と、読み上げたときに聞こえてくる音と、視覚に訴えかける2次元の形。「駅訳」はその3つの次元を横断する面白い事例だなと思いました。例えば、「See you later, arigator」を「さよオナラ」と訳した人がいますが、これは英語のダジャレを、その文字通りの意味にとらわれないで音で戯れた例だと思うんです。そうやってほかの言語に移し替えるときに3つの次元を横断しようとすることは、小塚さんのお仕事でもあるんでしょうか?
小塚:morphの仕事ではないのですが、少し前に知った英語と日本語を両方重ね合わせた言葉で、「アリガサンクスゴザイマッチ(Arigathanks Gozaimuch)」というものがあります。
中村:アリガサンクスゴザイマッチ(笑)
小塚:もともとはアニメ好きの外国人が考え出した、日本語と英語を組み合わせて両方で意味が通じるような「ジャパングリッシュ」と呼ばれる言葉遊びなんだそうです。他にも「Tadai’m home(ただいま+I’m home)」「Eatdakimasu(いただきます+eat)」「Hontrue desu ka(本当ですか+Is it true?)」とか(笑)。ご質問の答えとしてはちょっとずれますが、これもある種「音」の次元での横断と呼べるかもしれません。
中村:いまの質問をしたのは、アダプテーションの研究をしているなかで、文字という言語的・意味的な情報から、視覚や聴覚がメインである映画や舞台に移し替えるときに、どのようにその意味が変換されるのか?ということに興味があるからなんですよね。なので翻訳においても、意味だけじゃなく形や音といった要素を考えて移し替えることがあるのか、ということが気になったんです。
小塚:文字だけだと、それを読む人の脳内にそれぞれのイメージやセリフの声色なんかが生まれるわけですよね。一方、映画や舞台のために視覚や聴覚へ翻訳していくと、それらが一つに定められる。だから「原作を読んでいたときのイメージと違う」ってなりやすくて、テキストをもとにした映像作品の難しいところで。
中村:それはアダプテーションのジレンマですね。というのも、アダプテーション作者はマゾヒストでなければならないと、『アダプテーションの理論』という研究書を書いたリンダ・ハッチオンは言っています。つまりアダプテーション作品をつくると、原作に忠実にやっても批判されるし、原作から変えても批判される。原作を読んでる人と読んでいない人では反応が異なるから、必ずどこかから批判が来ると。
小塚:中村さんのインタビュー記事にもそれを示唆するお話がありましたね。アダプテーションというと文学から映画や舞台への変換をイメージすることが多いかもしれませんが、ぼくが普段関わっている広告やデザインの世界でも日常的にやっていることなんじゃないかと思いますね。
広告をつくるときには、ブランド戦略やマーケティング戦略をもとにします。それは基本的には言葉ですよね。デザイナーの仕事は、その言葉で表現された戦略をビジュアルにすること。もともと言語で表現されたメッセージを、どうやって1枚のポスターや1本の映像に翻訳できるかを考える。これはマーケティング・コミュニケーションにおけるアダプテーションと呼べそうですね。
この授業を聞いている学生の皆さんは、デザイナーやアーティストの卵だと思うんですけど、将来仕事をする領域が映画でも広告でもアーティストとしての作品制作でも、言語からビジュアルへの翻訳のプロセスに注目して考察するというのはすごく役に立つトレーニングだと思います。
新鮮だけれど、意味が伝わること
中村:もうひとつお聞きしたいのは、多義語をどう翻訳するのか?ということです。翻訳をするときには、いくつかの語義がある場合でもそのうちのひとつを選ばないといけないと思うんですよ。研究者が訳す場合は、注釈や脚注をつけちゃって、後からずらずらっと説明する場合もあるんですけど、それもスマートではない気がする。トランスクリエーションにおいて、こういった多義語の変換はどういうふうに工夫されているんですか?
小塚:これはいろいろやり方がありそうですが、ひとつのアプローチは一単語で訳さないことですかね。
たとえば英語で「light」というと、「軽い」という意味と「光」という意味があるじゃないですか。ある製品がこれまでは重かったのに、新しくなって軽量化されたとする。そこで使われる「light」に、軽さの「light」と、その製品が人の気分に明るさをもたらす「light」の、二重の意味が込められているとして。
じゃあ、その多義性を日本語でどう訳すかと考えたときに、たとえば「軽く明るく」のように、2つの言葉を重ねつつも「るく・るく」でリズムをとってひとつの言葉のように収めることができる。こうやって語感を合わせることで言葉を連ねるのは、ぼくらの仕事でもよく使うアプローチです。
中村:先ほど言葉の次元の話がありましたが、意味のみならず音も意識するということですね。
小塚:もうひとつのアプローチは、造語にすること。
以前、ある日本語のコピーライティングの仕事で、通常であれば「生きる」という言葉を使いたくなるところを、あえて「命(いのち)する」という言葉にしたんですね。「命する」という言い回しは日常生活でしないわけですけど、この表現にすることによって、「生きる」とは異なる、自分の持つ生命力を最後まで使い切る、という別の印象が出てきたりする。このときはなるべく多義性を含ませるようにと考えたわけです。
造語にする場合はけっこうチューニングが必要で、「こんな言葉聞いたことないからわからない」と思われてしまってはいけない。造語だからこそ新鮮で読んだ人をはっとさせつつ、意味が伝わる言葉をつくらなくちゃいけないですよね。
中村:初めて見た言葉だけど、意味は自然とわかっちゃうようにすると。
小塚:そういうことですね。
翻訳の世界に新たな転換を
中村:わたしが大学で行っている授業で、アルフォンス・アレーの『とてもパリ的なドラマ』や久生十蘭の『姦(かしまし)』など、初読と再読で解釈が違ってくる作品を取り上げたことがあります。そういった時間差での解釈の変化を誘うようなことは、トランスクリエーションで試みたことはありますか?
小塚:普段の仕事ではないですね。ぼくの会社の仕事は主にマーケティング・コミュニケーション領域のものなので、一発で意図が伝わる必要がある。もう一回読んでもらって理解が深まるとか、違う解釈ができるということよりも、初読ですべてを理解してもらうことが重要ではあります。
ただこれから、アダプテーションや字幕翻訳など、マーケティング・コミュニケーション以外の領域に事業を展開していくときに、時間差で解釈が変遷していくようなトランスクリエーションというのはトライしてみたいとは思いますね。
中村:トランスクリエーションの場合、具体的にどういう分野や場面で時間差攻撃がうまく効いてくるのかは考えたら面白そうです。
小塚:これから取り組みたいなと思ってることのひとつに、絵本のトランスクリエーションがあるんですよ。絵本って、現実では見えない世界を描いたりするわけじゃないですか。絵本のなかで描かれている物語自体が、既存の枠組みから外れたようなものが多いと思うんです。それに絵本って年齢を問わず読まれるものだから、同じ絵本でも子どもの頃に読んだときと、大人になってから読んだときで解釈が変わってくる、なんてことはよくありますよね。
中村:たしかに絵本のような芸術性が高い分野のほうが、時間差攻撃は親和性が高いような気がしますね。
最後に、学生から届いている「ある種の誤訳もトランスクリエーションと呼びますか?」という質問をお聞きしたいと思います。
小塚:トランスレーション・スタディーズのなかで、「スコポス理論」というのがあるんですよ。
中村:スコポス?
小塚:スコポスはギリシャ語で「目的」という意味。スコポス理論は1970年代に提唱された理論ですが、一言で言えば「目的によって訳は変わるべき」という理論なんですね。
つまり、その訳が正しいか誤りかじゃなくて、目的に適っているかどうかで判断をする。正しさを基準に判断する人から見れば誤訳に映るものでも、それが目的に適っていればOKとするのは、トランスクリエーションではよく取る立場ですね。ぼくの仕事の領域では、すごく支えになる理論といえます。
中村:いまの話を聞いて思い出したんですけど、学生時代に京都大学で内田樹さんの研究発表を聞いたときに、どんな悪訳でも、何かしら原作の雰囲気を伝えてくれるよね、ということを彼が言っていたんです。誤訳だらけと言われてる訳でも、何かしらの雰囲気は伝えてくれていて、後から別の訳を読んだり、原文を読んだりしても、そのときに感じた雰囲気は間違っていなかったと思う、と。正しいか誤りかという判断軸を超えたところにある何かを伝えるということも、翻訳にはできるのかもしれませんね。
小塚:トランスレーション・スタディ-ズでは歴史的に、元となる起点言語と翻訳される目標言語は等価であるべきか、何をもって等価とするのか、という議論が行われてきました。そうした流れの中で、70年代になって等価性よりも目的が大事なのでは、という提言がされてきた。そして冒頭でもお話した通り、ごく最近になってトランスクリエーションなどの新しい研究の芽が出てきている。
まだまだこれからスコポス理論がさらに発展したり、翻訳の世界に新たな転換が起きることをぼくは期待しています。学術的にもビジネス的にも、トランスクリエーションにはすごい可能性がありますし、morphとしてはマーケティング・コミュニケーション以外の領域にも創造的な翻訳を広げていきたいと思っているんです。
PROFILE
YASUHIKO KOZUKA & MIDORI NAKAMURA
小塚泰彦&中村翠
小塚泰彦 morph transcreation 共同代表
中村翠 京都市立芸術大学准教授
YASUHIKO KOZUKA
morph transcreation 共同CEO/共同創業者。博報堂でコピーライター、アートディレクター、博報堂生活総合研究所研究員などを経て退社し、渡英。ロイヤル・カレッジ・オブ・アート(英国王立芸術大学院)イノベーション・デザイン・エンジニアリング学科MPhilを中退し、英国でKieran Hollandと共にmorph transcreationを創業。数多くのグローバル企業から京都の老舗まで、トランスクリエーションを実践しながら「創造的翻訳論」と「意味のデザイン」を探求。長年の趣味として観世流で能の稽古をしており、中世以前の言葉にも関心が強い。
中村翠
MIDORI NAKAMURA
京都市立芸術大学准教授。専門はフランス文学。京都大学文学部フランス語学フランス文学専修 修士課程修了後、ジュネーヴ大学でDEA(博士準備課程)を、パリ第3大学ソルボンヌ・ヌーヴェルで博士号を取得。上智大学グローバル教育センター特別研究員、名古屋商科大学専任講師を経て、2015年より京都市立芸術大学にて教鞭を執る。「物語を読むのはなぜ面白いのだろう?」という疑問を出発点に、19世紀のフランス自然主義文学を中心にアダプテーション(翻案)に関する研究を行う。
Interview by Midori Nakamura
Text by Yuto Miyamoto


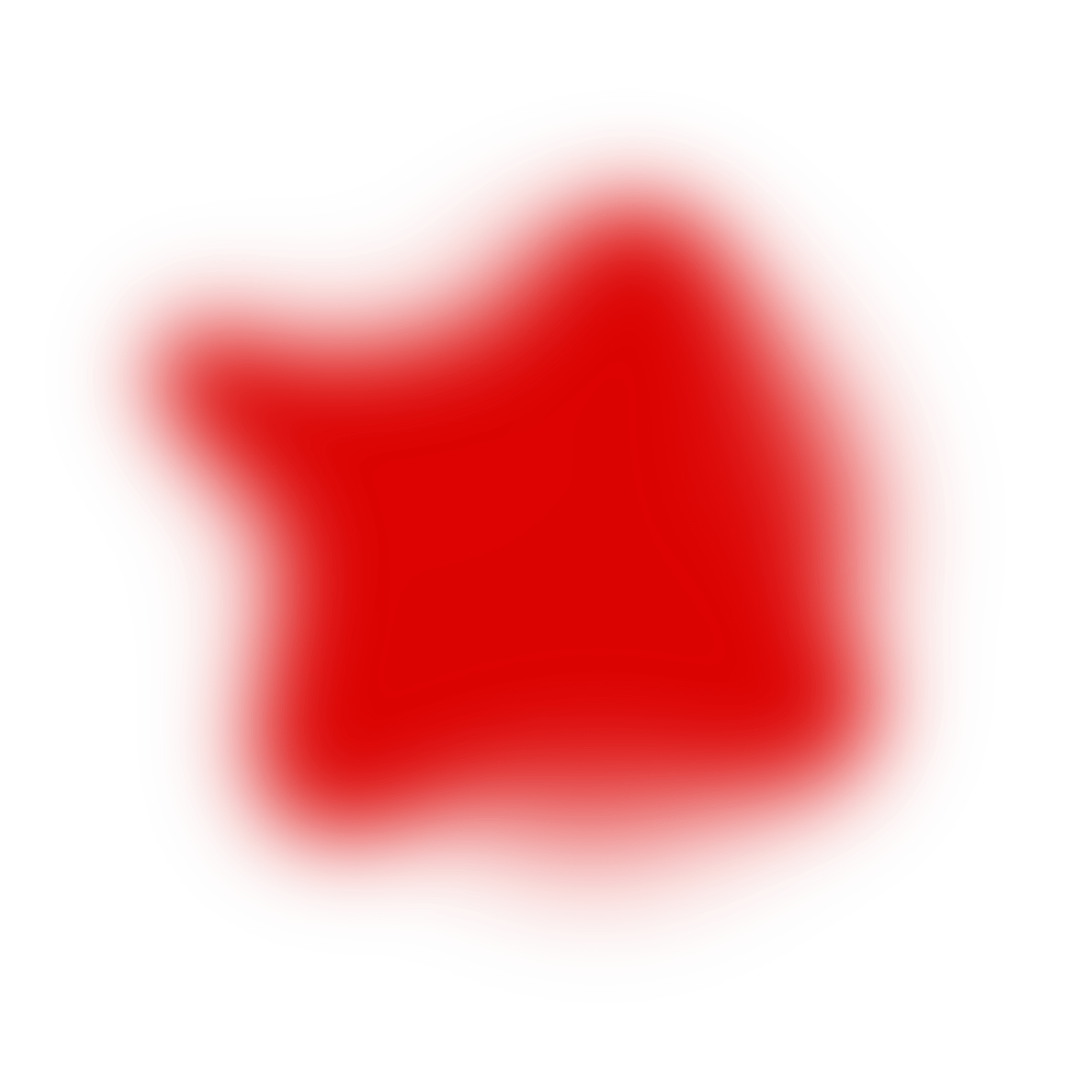
YASUHIKO KOZUKA
morph transcreation 共同CEO/共同創業者。博報堂でコピーライター、アートディレクター、博報堂生活総合研究所研究員などを経て退社し、渡英。ロイヤル・カレッジ・オブ・アート(英国王立芸術大学院)イノベーション・デザイン・エンジニアリング学科MPhilを中退し、英国でKieran Hollandと共にmorph transcreationを創業。数多くのグローバル企業から京都の老舗まで、トランスクリエーションを実践しながら「創造的翻訳論」と「意味のデザイン」を探求。長年の趣味として観世流で能の稽古をしており、中世以前の言葉にも関心が強い。
中村翠
MIDORI NAKAMURA
京都市立芸術大学准教授。専門はフランス文学。京都大学文学部フランス語学フランス文学専修 修士課程修了後、ジュネーヴ大学でDEA(博士準備課程)を、パリ第3大学ソルボンヌ・ヌーヴェルで博士号を取得。上智大学グローバル教育センター特別研究員、名古屋商科大学専任講師を経て、2015年より京都市立芸術大学にて教鞭を執る。「物語を読むのはなぜ面白いのだろう?」という疑問を出発点に、19世紀のフランス自然主義文学を中心にアダプテーション(翻案)に関する研究を行う。