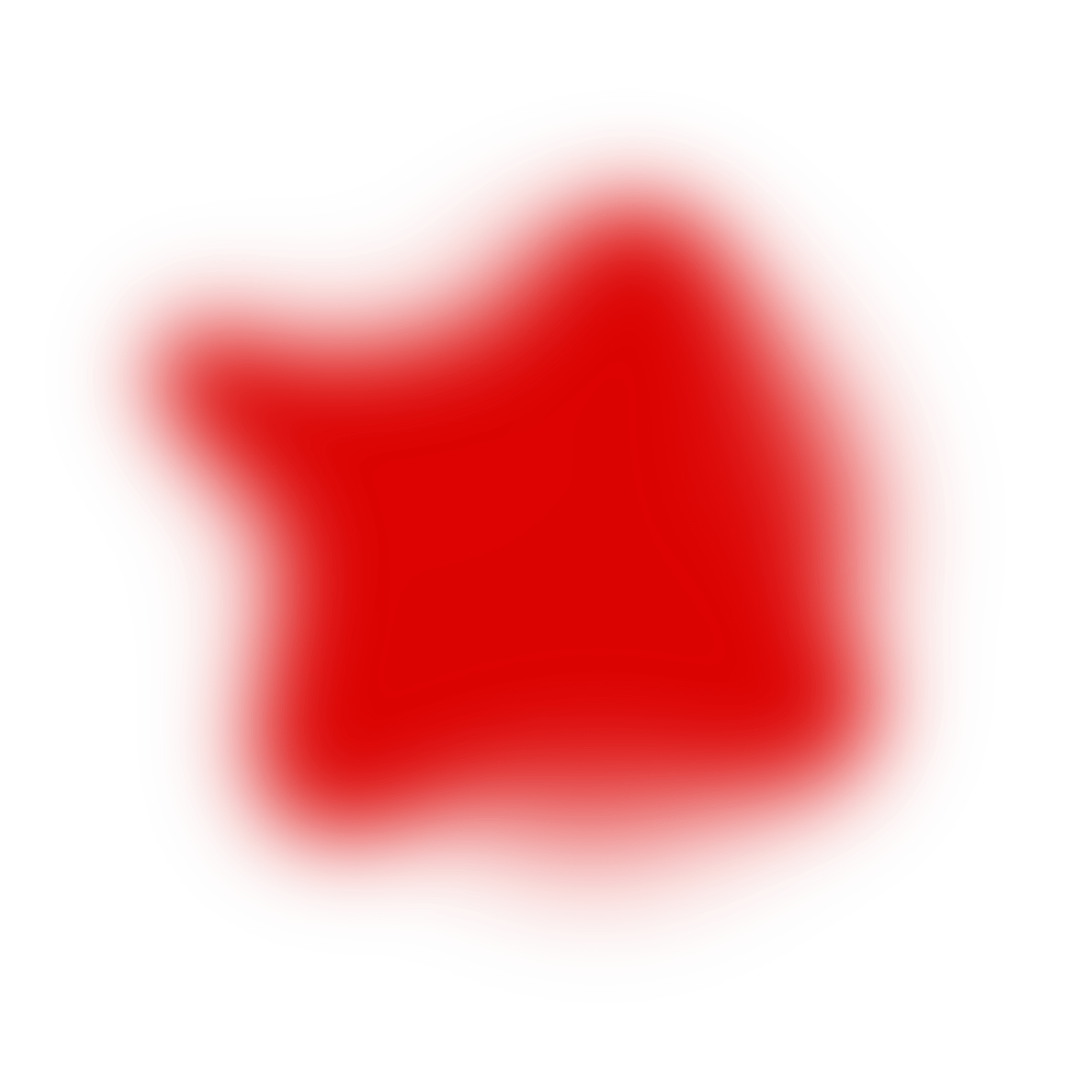PROFILE
Interview by Yasuhiko Kozuka
Text by Yuto Miyamoto
Photographs Courtesy of Hiroyuki Anzai
必須科目としての「異文化理解」
──いちばん最初にお聞きしたいのが、安西さんが『SankeiBiz』で書かれている連載「ローカリゼーションマップ」についてです。10年にわたって450以上の記事を書かれていますが、この連載を始めたきっかけからお伺いしてもいいでしょうか?
あの連載はそもそも、ぼくの想いとしては、2010年から1年間『日経ビジネスオンライン』で書いていたものの続きなんです。『日経ビジネスオンライン』の連載の内容をまとめるかたちで2011年に『「マルちゃん」はなぜメキシコの国民食になったのか?』という本を出したのですが、連載が終わってからもまだまだ語り足りないなという想いから『SankeiBiz』に書き始めて、いまに至っています。
ぼく自身がローカリゼーションに自覚的に突っ込み始めたのが、2003~2004年頃。1990年からイタリアで仕事を始めて、日本とヨーロッパ諸国の間でコーディネートをするなかで、やっぱり文化性の高い商材を扱うのが難しいことに気づきました。例えばイタリアのデザイン家具を日本で売るときは、そのテイストの違いが障壁になる。「日本の空間では、お洒落過ぎる」と受け取られたりとか。それに比べて、日本のハイテク商品をヨーロッパで売るほうがラクなんじゃないかと思ったこともあるのですが、こうした商品においてもアプリケーションやコンテンツの段階で文化の違いが重要になってくることを実感するようになりました。
例えば、日本ではカーナビの地図は鳥瞰図的な描かれ方をされますが、ヨーロッパの人たちは「家から300m進んだ広場を右に曲がって、そのあとに左に曲がって……」と道順で覚えるじゃないですか。そういった違いが十分に理解されないままインターフェースがつくられてしまうと、もはや冗談では済まされなくなってくる。IT化が進み、ローカリゼーションの対象が人間工学的なものにプラスして認知科学的なものが加わっていくなかで、文化理解が命にかかわる問題になってきたということです。
こうした課題についていろいろな日本のメーカーと仕事をしていくなかで、「異なる文化がわかる」ということがいかに大変なことかがつくづくわかったわけです。特に商品企画やクリエティブの担当に障壁が高い。具体的で可視化されるものを相手にする人たちですから、一見、ギャップは少ないと思われがちですが。そこからビジネスパーソンが異文化を理解するためのアプローチを考え始めて、2008年に『ヨーロッパの目 日本の目』という本を書くことになりました。その辺りの問題意識から「ローカリゼーションマップ」につながっていった、という感じですね。
──連載を始めてから10年以上が経ちますが、ビジネス界のローカリゼーションに対する認識はどのように変わってきたと感じますか?
連載を始めた当時、2010年代はじめの頃は「グローバリゼーション」や「グローバル商品」という言葉が盛んに言われたのを覚えています。なおかつ、わりと「グローバル万歳」みたいなところがあって。しかし「グローバル」と言ったときに、「その要素は何なのか?」ということに関しては中途半端にしか考えていないまま、日本のメーカーはグローバリゼーションに巻き込まれていったように思います。
一方で近年は、ローカル文化を拠点としたビジネスが段々と強まってきたじゃないですか。グローバリゼーションは幻想である、といった声さえ聞くようになった。つまり、「グローバル」と「ローカル」に対する理解が曖昧なままに、今度はローカルに突っ込んできたわけです。まだまだ異文化理解の問題は引きずっているな、と感じています。
──ローカリゼーションと一言で言っても、小説やファッションやカーナビの地図などあらゆるジャンルで、それぞれ文化ごとに捉え方は違ってくるわけですよね。だから本来であれば、文化やジャンルに応じて、それぞれのローカリゼーションを進めていかなければいけないと。
そうですよね。ローカリゼーションは分野や商品によって考えるべきことが違います。いま、スマートフォンのハードウェアが世界共通であることにほとんど問題はないと思いますが、実は2005年周辺までカーナビの仕様は地域ごとに分かれていたんです。日本ではその頃までにタッチパネルが普及していたのに対して、ヨーロッパではタッチパネルは自動車には向かないと考えられていて、ボタン式のものが主流だった。だいたいカーナビに限らず、ヨーロッパの人はタッチパネルを苦手とする、あるいは好まないとさえ言われました。だから銀行のATMもボタン操作が主流でした。
それが2007年にiPhoneが出て、世の中が一変しましたよね。ヨーロッパの人たちもみんなタッチパネルのスマートフォンを使うようになって、「何だ、全然問題ないじゃないか」となったわけです。それまで日本の自動車メーカーはヨーロッパ向けにはボタン式のカーナビをつくっていたのに、タッチパネルに統合されていったという流れがありました。
こうした事例からわかるのは、いかにわれわれが文化を静的に捉えていたかということ。ローカルの文化を考えるときには、それを動的なものとして考えることが重要になってくると思います。
問題解決からセンスメイキングへ
──そして、ロベルト・ベルガンティ教授の『突破するデザイン』をきっかけに、安西さんは「意味のイノベーション」を広めていかれます。「意味のイノベーション」というワードに出会う前から、安西さんとして「意味」にフォーカスした問題意識はあったんでしょうか。
ベルガンディに出会うまでは「意味のイノベーション」という言葉こそ知りませんでしたが、ローカリゼーションは対象の市場において「意味のイノベーション」を起こす手法である、という考えは持っていました。
ローカリゼーションっていうのはある意味、その行為自体がダサいものだったりするわけじゃないですか。特にアメリカの多国籍企業が各ローカル市場でモノを売るためにやるようなローカリゼーションは、若干“下請け”的な感じがありますよね。そうした売ることだけを目的にした下請け的なローカリゼーションは、ぼくはそこまで面白いと思わなかった。文化を静的に捉えマニュアルとしてこなす面がある。でも、ローカリゼーションを積極的に使うことで、その市場の文化にイノベーションが起こることに興味があったわけです。
──最近、モリス・バーマンの『デカルトからベイトソンへ』という本を読んでいて、原書は1981年に書かれたものなんですけど、最初のページから「現代では意味が失われている」と書かれているんです。ノルベルト・ボルツの『意味に餓える社会』という1997年の本でも似たようなことが書かれている。つまり、「意味が失われている」というのは、かなり以前から言われていることだと思うんですけど、ベルガンディさんがいま「意味のイノベーション」を取り上げる背景には、どのような社会の変化があるとお考えでしょうか?
ベルガンティが意味のイノベーションが必要と言っているのは、やはりこの20数年くらいかな、みんなの関心が圧倒的に「問題解決」に寄ったことに対する危機感からですよね。どの企業も「われわれは問題解決のために存在する」と言う。そうやってすべてが問題解決のためと振れすぎたから、それに対するものとして彼は「センスメイキング」の重要性を強調したわけです。
ひとつ例を挙げると、富士フイルムのチェキなんてまさにそう。携帯カメラが普及したなかで、アナログ写真のよさをセンスメイクしたという点では、意味のイノベーションと言えると思います。自分のために、ソーシャルメディアに載せるために写真を撮る時代において、「写真を人にプレゼントする」という行為にウェイトを置いているところにチェキの面白さはある。「写真を撮ること」にまつわる意味を変えた商品だと思います。
──そうしたローカリゼーションや意味のイノベーションに成功するブランドと失敗するブランドを分かつものは何だとお考えですか? 文化を越えて成功する企業に共通するものがあれば、教えてください。
一般化するのは難しいですが、傾向としてアメリカやイギリスのような大国の企業よりも、小国の企業のほうがローカリゼーションに優れているところはあるかもしれません。そうじゃない企業もたくさんありますが、大国の企業はグローバルとローカルのレベルをきっちり線引きしがちなのに対して、文化的なセンスに優れたブランドは、小国や辺境の地域から生まれることが多い。そうした国の企業が海外市場に行くときは、文化差に対して繊細な場合が多いといえるかもしれません。例えば、スイスの企業であるネスレは、各国市場に対してうまいローカリゼーションをやっているとよく評価されますよね。
──ネスレでいうと、キットカットは「きっと勝つ」の音に近いことから日本で「受験を応援する」という文脈でも売られています。キットカットが「きっと勝つ」に似ているのは偶然に過ぎないのですが、それを活かして日本における受験文化を捉え、製品の特徴とうまく融和させることで大成功した事例ですね。
小さい企業であれば、商品数も多くないから、輸出をするときに一つひとつの商品ごとにローカリゼーションにフォーカスできるということはありますよね。もちろん、コストもかかるわけですから、対象地域は限定されますが。大きな企業でたくさんの商品がある場合は、すべてにおいてキットカットと同じやり方でローカリゼーションをしていくのは難しいだろうなと思います。
ロベルト・ベルガンディによるTEDトーク「アイデアに溢れた世界における意味あるイノベーション」。
──安西さんの連載を読んでいると、ローカリゼーションや意味のイノベーションといったテーマに並んで、最近は「ラグジュアリー」の新しい定義にも関心が移っているように思います。その経緯についてもお伺いしてもいいでしょうか?
理由は2つあって、ひとつはやはり自分で意味のイノベーションの実践をしていきたいと思ったこと。2017年に『突破するデザイン』の監修をして、意味のイノベーションのエバンジェリストとして活動をするようになったわけですが、講演や執筆を通して伝えるだけじゃなくて、自分で実践していかなくちゃいけないと考えるようになりました。さっき話したように、ローカリゼーションのプロジェクトのなかで、実質的に同じことを考えてはいたのですけどね。意味のイノベーションのアプローチやプロセスを意識してやりたい、と。
もうひとつは、ラグジュアリーという概念は実はけっこう動かせるものなんだと気づいたこと。数年前にセラミックの仕事にかかわり始めたのですが、セラミック容器の価値って日本とヨーロッパでまったく違うんですよね。日本では100万円以上するものがあるのに対して、ヨーロッパではその価値があまり評価されない。ところがヨーロッパでは、セラミックアーティストのつくった作品は何百万、何千万で売れたりするんです。この違いは何なんだろう?と調べてみると、ヨーロッパではファインアートという概念が重視され、かつそこに高い値段がつく傾向があるのに対して、アジアや中東では工芸品と美術品が同じ領域にあることが、状況によっては足を引っぱる場合があることがわかってきた。そういった文脈の置き方次第で、グローバルマーケットで有利になったり不利になったりするわけです。
つまり、「ここからがラグジュアリーでここからはラグジュアリーじゃない」なんていうのは、みんながそれぞれの主観でやっていることであって、どこかに指標があるわけではないんですよね。なおかつ、フランスのLVMHのようなコングロマリットがつくる、手法がかなり透けてみえるラグジュアリーに消費者たちが飽き飽きし始めてきたところもある。そういったことから、新しいラグジュアリーのあり方に突っ込んでみようと思うようになりました。
──確かにラグジュアリーって、既存のフレームの中で行われる、ある種の記号操作に過ぎないのかもしれません。過去の流行の延長線上で、次に流行るものを無理くり生み出すような印象もあります。
それこそ、いまみんながラグジュアリービジネスと思っているようなものって、20世紀後半に出てきたものじゃないですか。それは19世紀に生まれたラグジュアリービジネスとは違うものだった。19世紀のラグジュアリーは、産業革命以降の新興ブルジョアジーたちが自分の地位を上げるためのものだったのに対して、20世紀後半のラグジュアリーは、ヨーロッパ以外の人たちがヨーロッパの文化を取り入れることでステータスにするためのものになったわけですよね。
──そうした歴史的な流れがあるなかで、安西さんはこれからの時代の、21世紀のラグジュアリーはどんな方向に進むとお考えでしょうか?
やはり中国マーケットの圧倒的な大きさは、ラグジュアリーのかたちを変えていくだろうと思っています。
ぼくは2017年頃から、コングロマリット的なラグジュアリーハイブランドがローカリゼーションの考え方を取り入れ始めたことに注目していました。それまではヨーロッパの本社が決めたプラットフォームを世界共通で使い、翻訳もすべてそれに合わせていた。だからフランスやイタリアのハイブランドの日本語版ウェブサイトには、これでいいの?と思うような日本語がけっこう書かれていたじゃないですか。商品を見ても、ローカライズは許されないのが基本ポリシーでした。
それが段々と、ローカルごとに商品やプラットフォームを使い分けるようになってきたのは、中国の影響だと思いますね。いまではヨーロッパの人たちも「中国で流行っているものを取り入れて、次は中国以外のマーケットにそのエレメントをインプットしよう」という発想になってきている。その変化が見え始めたことも、これからのラグジュアリーは変わっていくなと思った理由のひとつです。
ただここで注意点なんですが、ヨーロッパのブランドや中国市場だけに左右されるのも良しとしない人たちが世界には多くいます。ですから、各々のローカルの文化に基づいたラグジュアリー構築の動向が窺えます。その動的なきっかけをつくっているのが中国市場との見方ができるでしょう。
新しい動詞をつくらなければいけない
──この『TRANSCREATION®Lab.』で中心にしているテーマは「言葉」なんですね。ローカリゼーション、あるいは意味のイノベーションを行っていくにあたって、安西さんが言葉の重要性をどのように捉えられているのかをぜひお聞きしてみたいです。
言葉、すごく大事なポイントだと思ってるんです。例えば江戸時代後期から明治の初めにかけてヨーロッパの言葉が日本にローカリゼーションされたときに、抽象的な概念が漢語に翻訳されたじゃないですか。あるものは定着して、あるものは定着しなかったと思うんだけど、150年経っても相変わらず難しい言葉ってたくさんありますよね。そうやって翻訳された言葉をベースにもう一度自分たちで海外に発信しようとするときに、トラブルになるわけです。例えば「人権」みたいな言葉は厄介で、文化によってその言葉がもつ幅と重みはかなり異なってくる。そのことを十分に理解しないまま世界に向けて発信をすると、けっこう危ないのかなという気がしています。
だから、概念というのはユニバーサルであるようで、実は必ず誤解がある、あるいは異なる解釈が有り得ることを前提に考えなくちゃいけない。ローカリゼーションのために自分たちの文化に合うような言葉をつくって、国内で定着するのはいいんだけれど、それをベースに海外に発信したときにドツボにはまる可能性があるということに、いま関心がありますね。和製英語をそのまま英語を話す人に使って、首をかしげられるのも、似ていることかもしれないです。和製英語は、英語の翻訳だとすれば。
──日本語のなかでも明治時代につくり出されたものの場合は、とくにそう感じます。
「ローカリゼーションマップ」にも書いた話ですが、2016年に、原研哉とイタリア人デザイナーのアンドレア・ブランジが100の動詞を選び、それぞれに合うモノを展示する展覧会がミラノで開催されたことがあります。
2人は人類の歴史に沿って動詞を選ぶわけですが、「殺す」「磨く」「切る」といった古い言葉においては、人間の基本的行為としては文化差を感じさせることがないのに対して、現代の言葉、例えばコンピューター分野に絡む「拡張する」といった動詞になってくると、途端に西洋の言葉──そこではイタリア語と英語と日本語が並んであったわけですが──と日本語の格差が広がるわけです。そして、圧倒的に日本語は不利。「Expand」という英語の動詞に対して、日本語では「拡張する」と、「漢語+する」というかたちでしか表現できないからです。こういったことが、いまの世界で日本人が苦労するところなんだなって、つくづく思ったわけです。
要するにラテン語系の言葉では、多くの名詞が動詞を起点に生まれている。そもそもイタリア語の不定詞というのは動詞の原形がそのまま名詞になるものですから。英語だと動詞に「ing」や「to」を伴いますよね。そうすると言葉の理解に幅があるから、やっぱり良い意味で試行錯誤しやすいし、自分で新しい概念をつくりやすいと思うんです。一方で名詞っていうのは、印象としては10cm四方に収まるもので、流動的じゃないんですね。
例えば「文化」という言葉はラテン語の「耕す」という動詞から来ていますが、日本語で「文化」というと、やっぱり“そこにあるもの”で“動くもの”じゃないように思う。でも「耕す」という動詞から「Culture」という言葉ができていることを知ると、これは自分でつくれるものになるじゃないですか。こうした流動的な言語空間のなかで生きていると、自然と動的な思考をすることができる。これがいま、日本語を使うわれわれが損な立ち回りをしている遠因になっているのではないかと最近考えています。
──明治時代につくられた日本語はもう150年以上使われているわけです。「社会」「自由」「権利」といった言葉は日本の近代化に大きく貢献したと思うのですが、日本の未来を構想するときに、また新たに日本語をつくってもいいんじゃないかとぼくらは考えていて。Googleという企業のサービスから「ググる/google」という言葉ができたように、テクノロジーによって新しい営みが生まれたときに自然と新しい言葉も生まれるのかもしれません。一方、いまの段階から未来を構想して新しい動詞をつくる、ということがあってもいいのかなと考えたりもします。
そう、名詞じゃなくて動詞をつくりたいですよね。少なくともそういった試みをすることで、世の中の見え方が変わってくる可能性はあると思います。
ちょっと話が外れるんだけど、イタリア人ファッションデザイナーのブルネロ・クチネリが「人間主義的経営」という言葉を掲げて、人間らしい社会をつくるための取り組みを自身の会社を通して行っています。だけど「ヒューマニティー」や「人間性」という言葉でそれを捉えている限り、彼のやっていることはわかっていなかったんだなと、この間思ったわけです。
つまり、ヒューマニティーとか人間性という言葉を使うと、なんだか堅苦しい。窮屈で暗いんですよね。ところがイタリア語の「umanità」という言葉があると、パッとイメージが広がるわけです。先日、クチネリがプレゼンテーションしているところを聞いて、いま更ながら彼が求めているのはこの「umanità」なんだなと思った。人間性でもヒューマニティーでもなく、「umanità」という言葉の明るさがないと伝わらなかったんだな、と。
──月並みですけど、やっぱりイタリア語ってどこか明るく聞こえるんですね。
たしかに、母音が印象を明るくさせるんでしょうね。そうか、音の使い方でこれだけ意識が変わるんだ、とそのときに思ったわけですが、そういうことに気づくためには、やっぱり異なる文化との遭遇が必要なんだと思います。
──最後に、インタビューする方々に聞いている共通質問です。安西さんにとって翻訳とは何でしょうか?
翻訳とは、議論されるための格好の「おいしいネタ」ですよね。つまり、翻訳っていうのは一方通行ではなく、オープンループであって、議論を生むためのネタを提供するものである。そういうふうに思います。
言葉をつくることによって世界観や見え方が変わるのであれば、翻訳とはそのきっかけを与えてくれるもの。だから誤訳や誤読、誤解が許容されていくことから、新しい世界の見え方も生まれていくのだと思いますよね。
PROFILE
HIROYUKI ANZAI
安西洋之
ビジネス+文化のデザイナー
Interview by Yasuhiko Kozuka
Text by Yuto Miyamoto
Photographs Courtesy of Hiroyuki Anzai