PROFILE
Interview by Yasuhiko Kozuka
Text by Yuto Miyamoto
「翻訳のダイナミクス」を見つめる仕事
──最初にお伺いしたいのが、トランスレーションスタディーズのメッカとも呼ばれるロンドン大学SOAS(東洋アフリカ研究学院)の翻訳研究センターについてです。そこで片岡さんがどういったことを教えられてたのか、というところからお聞かせいただけますか?
SOASは基本的に中東、アフリカ、アジア関連の研究を行う大学なので、その地域の言語における翻訳研究をしたい、あるいは翻訳者になりたい学生たちに向けて、翻訳理論や文化翻訳、それからそれぞれの言語にフォーカスした実践翻訳の授業を担当していました。あとは定期的にリサーチャー向けのセミナーがあったので、そうした場で学生と研究者たちが集まって研究の話を聞いたり、交流したりしていましたね。
──翻訳学という学術領域はわりと新しいものですが、どういう目的で生まれたのでしょうか?
翻訳学は1970年代に生まれた学問ですが、それ以前まで翻訳とは、文学や言語学といった各分野のなかで語られることがほとんどでした。それも「翻訳は原文に対してどう忠実であるべきか」といった同じような議論が繰り返しされることが多かった。翻訳学は、そうしたバラバラの分野に散らばっていた翻訳に関する議論を共通のプラットフォームにまとめるためにつくられたのが始まりなんです。
なので現在は「翻訳」というキーワードのもと領域横断的な研究ができるような場所になっていて、オーディオ・ヴィジュアル・トランスレーションからサブタイトルに関する研究まで、翻訳に関わるさまざまな分野の研究者たちを内包するような研究分野になっています。
──「翻訳は原文に対して忠実であるべきかどうか」という問いは翻訳における永遠のテーマだと思います。片岡さん自身はどのようなスタンスで研究を行っているのでしょうか?
翻訳における等価性の問題って、翻訳研究者であれ翻訳について語る批評家であれ、みんなが必ず突き当たる問題ですよね。「等価であるべきだ」という前提から入る研究者もいれば、「等価であることなんて到底不可能だ」と考える人もいる。
ただわたし自身は、日本研究や比較文学の側面から翻訳を捉えているので、それが等価であるかどうかよりも、翻訳プロセスの「あいだ」に興味があるんです。比較文学者である東京大学の大澤吉博先生が、翻訳とは、生産者と消費者の力関係や、その間に介在する中間流通業者の思惑などから生み出されるものだと、訳文が届けられるまでの間に等価性の議論では割り切ることのできないダイナミクスがあることを指摘をされているのですが、わたしもその「あいだ」に興味をもって研究を行っているんです。
──翻訳の「あいだ」について、もう少し詳しく聞かせてください。どのようなきっかけでそこに興味をもつようになったんですか?
わたしがそもそも「あいだ」に興味をもったのは、フラミンゴで海外のブランドを日本にローカライゼーションするときに、「あいだ」でいろいろなダイナミクスがあることを現場で見たことがきっかけでした。翻訳研究って普通、完成されたテキストを比較して研究するのが主だと思うんです。そこで誤訳とされるものがあったり、削除された箇所があったりすると、すべて翻訳者の責任にされるのがかつては普通だった。
だけど実際に文化が翻訳される現場を見てみると、全然そんなことなかったんですよね。いろんな人が介入して、いろんな思惑があって、話し合いの結果、あるひとつの翻訳ができあがっていく。日本文学にはずっと興味があったのでいつか研究したいと思っていた時期に、翻訳の現場にそうしたダイナミクスがあることを知ったんです。
いま行っている研究に興味をもったきっかけのひとつに『日本語と日本人の心』という大江健三郎・河合隼雄・谷川俊太郎の対談集があるのですが、大江健三郎との対談のなかで『雪国』の冒頭が英訳では削除されている、という話があったんです。気になって調べてみると、実際には『雪国』の冒頭はカットされていなかったのですが、1950〜70年代、つまり第二次世界大戦後に日本文学が初めて大量に英語圏に紹介された時代に、削除・改変がされた事例がかなりあることがわかった。そして日本の読者からは、翻訳の過程で作品が歪められてしまったという非難がされていたんです。
だけど出版社の現場を調べてみると、ただ単に削除したわけではなく、切ったからには切る理由があったこともわかってきました。あえて原文とは違ったかたちにするからには、編集者や翻訳者にその選択をさせた背景があるはずじゃないですか。それを知りたいという気持ちから、わたしは「あいだ」にすごく興味をもつようになったんです。だから自分が実務で得た経験、文化翻訳の現場で経験したジレンマが、本当にいまの研究につながっていると思います。単純な構図では捉え難いものや揺れ動くもの、簡単には理論化できないものを、事例研究を通して積み重ねていくことによって人に見せていきたい、という気持ちで研究をしてるんです。
誤訳が拓く可能性
──「あいだ」に興味をもたれてから、キャリアをガラッと変えてまで「これを探究したい」と思うに至った片岡さんの原動力はどこから来たんでしょうか?
振り返ると、「自分自身を知りたい」という気持ちが強かったように思います。わたしは両親がヨーロッパの音楽をやっていたので、ヨーロッパの文化に近い環境で育ったんですね。だからそのなかで、日本とは何か?という問いは常にもっていたように思います。それから大学時代にイギリスで英文学を勉強したときにも、英文学が自分にフィットしない部分があったので、自分のアイデンティティに近いものを勉強してみたいという気持ちから日本文学を研究することにしたんです。
研究をするなかでも、作品を見るときに、自分はいま日本人として見ているのか、それともイギリス側から見ているのかと悩むことがある。文化と文化の間にいる状態で、「わたしって何なんだろう?」と思うことがすごくあるんです。なのである意味、研究を通して、自分がどのパースペクティブから物事を眺めているのかを確かめたいという気持ちがある。「自分自身のことを知りたい」という想いから、現在の研究の道に進んだところがあるように思っています。
──そうして「あいだ」の研究をしていくなかで見えてくるもの、あるいは翻訳の背景を紐解くことによって片岡さんが知りたい普遍的なことというのはどういうものなんでしょうか。
翻訳研究って、わりとネガティブな方向に傾きがちなんですよね。というのも、多くの研究では原文と訳文を照らし合わせながら、結局は「翻訳プロセスのなかで何が失われたか」に焦点が当てられがちだからです。
ただわたしはそれだけとは限らないと思っていて、むしろ翻訳とは、可能性を拓いていくための行為だと思うんです。そもそも翻訳がなければ読者は外国文学を知り得ないわけですし、それを元にした新しい文化も生まれなかったりする。わたしが好きな詩にゲーテの『ひとつの譬喩』というものがあるんですけど、これはゲーテが自分の作品が別の言語に訳されて詠われたときに抱いた印象を書いたものなんですね。そのなかで彼は、自分の詩が別の言語に移植されたことによってより生き生きしてきた、という話を書いてるんです。
自分のなかでは、ゲーテの言ってるこの翻訳が拓きうる可能性みたいなのを追い求めているところがあって。翻訳って、新たなものを生み出していく原動力になり得るわけじゃないですか。翻訳を通して、言語と言語、文化と文化の根本的な差異に気づいたり、あるいは逆に普遍的な何かに通じたりすることによって、そこから新しい芸術のかたちが生まれていくことがある。しかもそうしたポジティブな刺激は、しばしば思いがけぬかたちで生まれるんですよね。その偶然性や翻訳が生み出す可能性にわたしは興味があって、これまで翻訳によって文化が発展してきたプロセスのなかで何が起きていたのかを知りたいんです。
それと同時に、アカデミアと現場との橋渡しをしたいという気持ちもあります。というのも、わたしがフラミンゴ時代に経験したような現場のリアルを、おそらく多くのアカデミアの人たちは見たことがないと思うんです。現場の葛藤を想像できないと思うので、「あいだ」ではこんなことが起きているんです、ということを伝えていきたいと思っています。
──翻訳が可能性を拓くための行為である、というのはとても共感します。片岡さんが感じた、翻訳によって起きたマジカルな瞬間、翻訳によってオリジナルとは違った魅力がプラスされたような事例があれば教えてください。
わたしの記憶にいちばん残っている例は、『細雪』の英訳からアンガス・ウィルソンというイギリスの作家がインスピレーション受けた話ですね。『細雪』の英題は『The Makioka Sisters』というまったく違うタイトルなんですけど、ウィルソンがそれを読んだときに、最後の2行がすごく印象に残ったと言っているんです。
そもそも『細雪』は雪子という四人姉妹の三女のお見合い話をめぐる谷崎潤一郎の作品ですけど、そのエンディングは、とうとう嫁ぎ先が決まった雪子が東京に行くために列車に乗る、その中で彼女のお腹の調子が悪くなる、というものなんですね。ウィルソンはこのエンディングに驚いた。というのも、英文学ではハッピーエンディングや何かしらの問題の解決で物語が終わるじゃないですか。それが『細雪』では淡々とした描写で終わっていて、しかもそれが少しコミカルでもある。ただそのコミカルな終わり方になった理由というのが、実は訳者のエドワード・G・サイデンステッカーが、直前の主語を取り違えたことがきっかけなんです。
普通、誤訳はマイナスなものとして語られることが多いなかで、翻訳者がちょっと読み違えてしまったところから日本文学の特徴や谷崎の作品がもつポテンシャルがハイライトされて、イギリスの作家がインスピレーションを受けることにつながった、というプロセスがすごく面白い。実際にウィルソンはこれがきっかけで、それまで目を向けていなかった日本文学を読むようになるんです。
こうした谷崎の作品の特徴は、日本のなかに留めておいたら永遠に気づかれなかったかもしれません。それが翻訳されることによって、そしてミス・トランスレーションがされたことによって、自国の言語ではハイライトされなかったものが見えるようになった。いまのところ、これが最も印象に残っている「あいだ」のエピソードですね。
──その文学がもっているポテンシャルが、たまたま誤訳によってあぶり出されることになったと。きっと誤訳以外の方法でも、そのポテンシャルが開花する可能性というのはあるのでしょうね。
十分にあり得ると思います。例えば文学の世界では、テキストだけでなくブックデザインでもだいぶん姿形が変わるんです。それからその著者を海外でどんなふうに説明するのか、レプリゼントするのかによっても受け取られ方は違ってくる。そうした変容の様子はすごく面白いし、その結果、作品が思わぬところにたどり着くのも素敵なことだと思っています。
「あいだ」の実相
──これからの日本文学が海外に紹介されていくときに、どのように伝えられるのがいいのか、ということが気になっています。ぼくがロンドンに住んでいたときに、大きな書店でまず目に入ってくる日本人作家は村上春樹。その次に並んでいる冊数がかなり減って、川端康成、三島由紀夫、谷崎潤一郎、よしもとばなな、安部公房。最近だと川上未映子が海外のメディアで紹介されていますが、現代の作家がもっと紹介されてもいいのにと思うんですよね。川端や谷崎といった作家がどう英語に訳され、海外に伝えられてきたか、という過去の事例からいま学べることがあるとすれば、どんなことでしょうか?
未来を予測するのって難しいですよね。わたしは過去のことを見ることが仕事なので、正直なところ答えはわかりません。とくに現在は、文化間の差異が縮まってきている時代なので、果たして過去に起きたことが同じように起こりうるのかどうかもわからない。ますます予想するのが難しい世の中になってきていると思います。
そのうえでわたしにできることがあるとすれば、過去の事例を見て、「こういうケースもあったよ」と可能性を示して見せることなんですね。例えば、日本文学の影響が海外で広く伝播した事例では、川端康成の『眠れる美女』にガルシア・マルケスをはじめとしたラテンアメリカの作家がインスピレーションを受けた話がある。あとは同じく川端の『名人』という囲碁の棋士たちについての作品も、一見すると囲碁というモチーフは理解されにくいように思えるものの、実は英語圏で人気があったんです。
これらの事例からいえることは、人が誰しも経験し得るユニバーサルな体験を新鮮な角度から書くことによって、結果的に海外の作家にインスピレーションを与えることができたということ。『名人』ではボードゲームというユニバーサルなモチーフを扱いつつも、囲碁ならではの勝者と敗者の描かれ方がされたことで、海外の受け手の印象に残ることになった。またボードゲームは政治を表象するものであるからこそ、冷戦期に受容されることになったのかもしれません。過去のケースから学べることがあるとしたら、こうした作品が受容される過程におけるダイナミズムの例だと思います。
──日本文学の翻訳プロセスからブックカバーに見る翻訳の現場、ファンによって行われるマンガ翻訳まで、片岡さんはいろんなテーマで論文や著作を書かれてますが、それらの研究活動に通底するものをあえて一言にするとどんなものになるんでしょうか?
「あいだ」の実相、ですかね。
──「あいだ」の実相。
文化の受け渡しがされる、その「あいだ」で行われている人の思惑や政治というのが、自分が一貫して書いていることだと思うんです。翻訳の過程で作品が変容するなかで、さまざまな人の手が加わっていることをわたしは示したい。それも決してひとりの想いによるものではなく、いろいろな人やモノが介在するなかでその変容が行われるというのは、文化や言語の翻訳に関わる人たちは絶対に経験することじゃないですか。そうした「あいだ」の本当の姿を知ってほしい、という気持ちで研究を行っていますね。
──冒頭でもお話されたように、片岡さんはビジネスと学術の両方の現場を経験されて、珍しい視点をもたれていると思うんです。そんな片岡さんから見て、「あいだ」の実相を知ることやその研究は、実社会にどんな可能性をもたらしうると考えていますか?
わたしが行う研究は過去に起きたことを中心にしているので、もしお役に立てることがあるとしたら、実際に文化を翻訳・紹介する人たちのパースペクティブを広げることだと思うんです。現場にいると忙し過ぎて、同じ型にはまりがちになったり、トレンドの後追いをしてしまったりすることってあるじゃないですか。でも過去のいろいろなケースを知ることによって、その時局、その状況に合わせたやり方で、自分なりの解を考えられるようになる。過去の人がこんなことを考えていたのかと知るだけでも、思考は柔軟になると思うんです。これからの文化の可能性を拓くのは、実際に翻訳に関わっている方々なので、よりよく、より面白いものをみんながつくっていくプロセスに、知の蓄積が役に立てればと思っています。
──ぼくが「トランスクリエーション」という言葉に惹かれたのは、言語や文化を越境していくプロセスで、トランスクリエーションする人自身の創造性が拓かれていくからなんですよね。今回片岡さんのお話を伺って、学術研究として翻訳の世界を開拓していくことの面白さを教えてもらったように思いますし、そこから新しい可能性が拓かれていくことにワクワクしました。
今日お話したゲーテやアンガス・ウィルソンもそうですけど、過去の文豪たちを見ると、自国の作品を読み続けることによって思考が固くなってしまうことに危機感を覚えて、視野を広げるために他国の文学を読むようになっているんですね。
選択肢が増えることによってより多くの可能性を考えられるようになるというのは、わたし自身も経験していて。研究を通して過去の事例を知り、翻訳の過程で思いがけぬことが起きたことを知ることで、昔ならできなかったような考え方ができるようになったところがある。どんな分野においても、異なる文化のことを知ることによって、よりクリエイティブなことができるようになるんじゃないかと思っています。
──最後に、インタビューをする方々に聞いている共通質問です。片岡さんにとって翻訳とは何でしょうか?
翻訳とは、自分自身を知るためのプロセスであるというふうに思ってます。翻訳の面白いところって、やっぱり他者と出会うことにあるじゃないですか。他者というのは、異なる言語や文化のことであり、人でもある。その異なる文化圏に遭遇することによって、初めて自分を知る機会を得ることができると思うんです。わたしの研究でいえば、日本の小説が英語圏に翻訳されることによって、初めて日本文学の性質を自覚できるようになる。「自分自身が何者なのか?」を他者との遭遇を通して知ることができる──翻訳とは、そんな鏡みたいなものだと思っていますね。
片岡さんが所属する東京大学東アジア藝文書院はこちら
PROFILE
MAI KATAOKA
片岡真伊
東京大学東アジア藝文書院 特任研究員
https://www.eaa.c.u-tokyo.ac.jp
Interview by Yasuhiko Kozuka
Text by Yuto Miyamoto


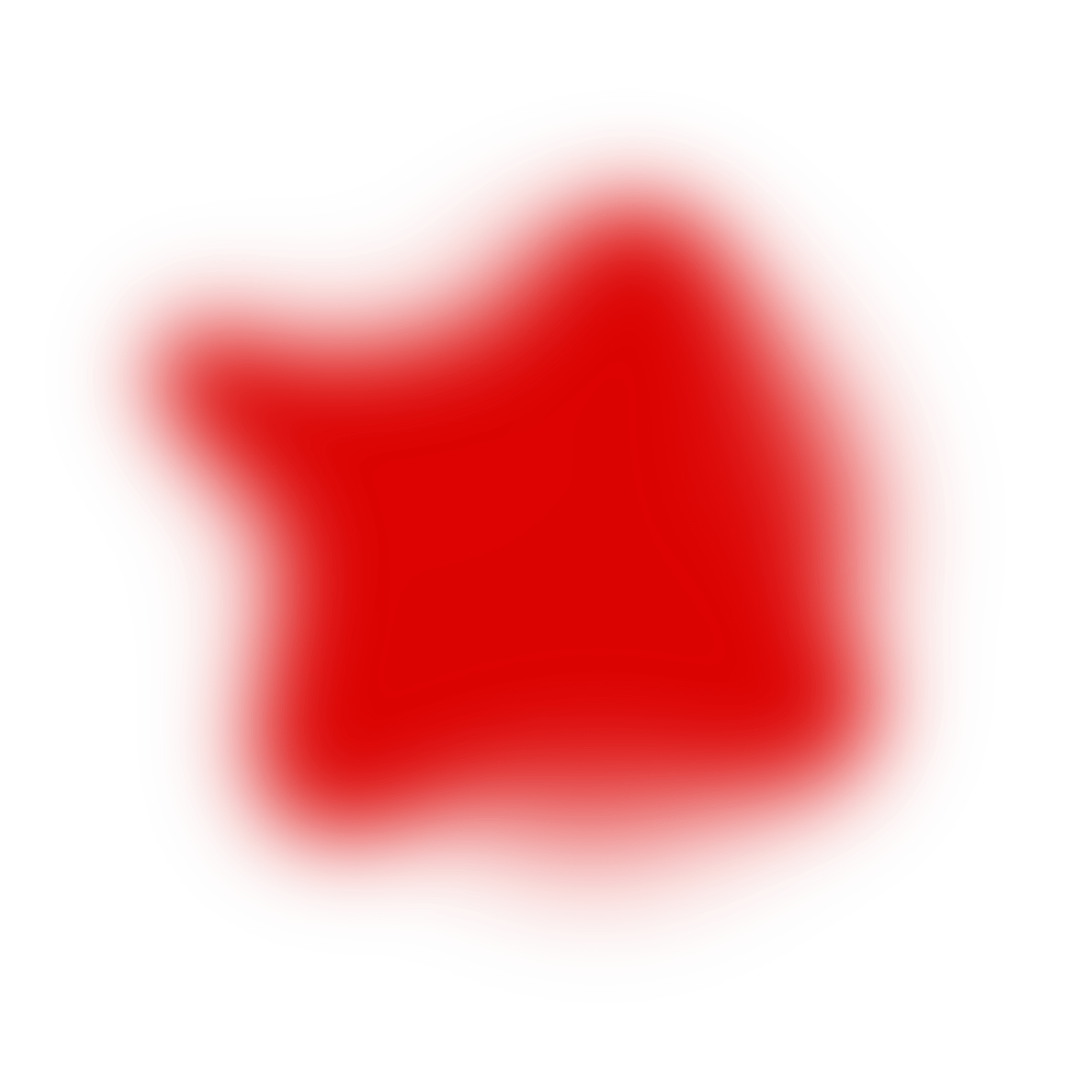
https://www.eaa.c.u-tokyo.ac.jp