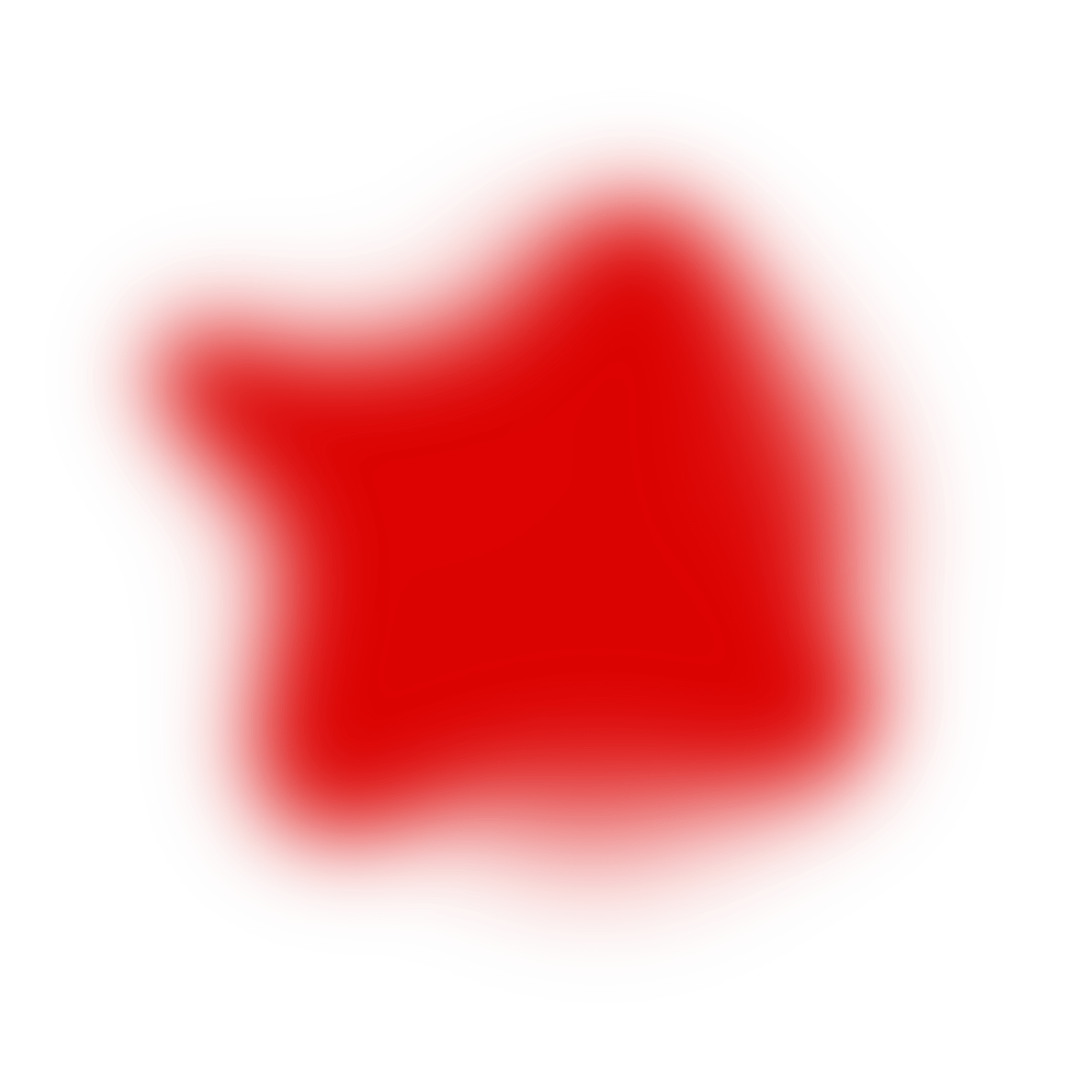PROFILE
Interview by Yasuhiko Kozuka
Text by Yuto Miyamoto
Profile photo by shimizu kana
Photographs Courtesy of Midori Nakamura
みんなが物語に惹きつけられるわけを求めて
──中村さんの研究についてお聞きしたときにすごいと思ったのは、「物語はなぜ面白いのだろう?」という非常に根源的な問いから出発している点です。そもそもその問いをもつこと自体がめちゃくちゃ面白い。どういう経緯でその疑問に行き着いたんですか?
そもそも物語とは何か?というところからお話したいと思います。「物語」というと文学作品のイメージが強くて堅く捉えられがちですけど、ここでは「フィクション」と言い換えたほうがわかりやすいかなと思ってます。つまり「ウソ話」と思っといたらいいと思うんですけども、そのウソ話が何で面白いのか?と。
文学研究ってお金にならないし、「何でお金にならない研究に研究費を使うんだ」みたいに思う人もいらっしゃいますよね。でも、いやいや、物語──つまりウソ話──って、昔から人の心を捉えてきたよねと。ギリシャ悲劇含め、紀元前から、もっと言えば文字で伝えられる以前から口承で、ウソ話って語られてきたし、それに人は惹きつけられてきたわけです。だから、物語はお金を生まないというのもウソで、例えば物語性をもった多くのCMがつくられているように、ストーリーとは常に人間が欲してきたもの、求めてきたものだと思うんです。
そこでわたしは、何で物語を読みたくなるのか、そして、どうして物語を読み始めたら手が止まらなくなっちゃうんだろう?ということを考えたわけです。そのときに、「テーマやキャラクターが面白いから」と言う人もいるかもしれませんが、それって主観的な要素じゃないですか。そうではなくて、みんなが物語に惹きつけられるわけだから、万人に共通する原因を探っていきたいと思ったのが文学研究の道に進んだ最初のきっかけだったんです。
──個別の作品論ではないわけですね。科学的なアプローチというか。とても興味深いです。
その原因として最初に思い付いたのが、サスペンス。サスペンスとは「宙づりにされた(=suspendされた)状態」であり、一時的に進行が中断した状態のこと。美学辞典で引いてみると、「サスペンスは物語世界の進行の見せ方を調節して、読者や観客に不確実さを与え、どうなっていくのか知りたいと思わせるためのものである」と書いてあるんです。
これは一見正しいように思えるのですが、まったく不確実なものだけではサスペンスとして機能しないんじゃないか、とシャルル・グリヴェルという人は言っています。「小説のテキストは、いかにうまく隠そうとしても最終的な結末を推測させる。小説のテキストが生む不確実性は共通認識とは反対に、確実性を完璧に排除することではないのだ」と。つまり、情報を隠そうとしても、実はテキストは、将来起こる物語の展開について自ずと読者に知らせている。完全に真っ暗闇の中に入れられたらこの先どうなるか予測がつかないのと同じように、情報がまったくなければ予測や期待もできないということです。
それと同じことは映画監督のヒッチコックも言っていて、彼は「サプライズ」と「サスペンス」の違いを比較しています。ヒッチコックは観客の前でトリュフォーと対談をしたときに、「もしこの場にならず者が爆弾を仕掛けていたら」という話をします。爆弾を仕掛けたところを観客が見ていなければ、爆弾が爆発した瞬間に誰もがびっくりします。心臓はドキドキする。その間、15秒だとしましょう。これがサプライズです。
反対に、対談が始まる15分前にならず者が爆弾を仕掛けたところを観客が見ていたとしましょう。すると、観客はヒッチコックとトリュフォーが会場にやってきて対談をしている間も気が気じゃないわけです。15分間ドキドキしっ放しで、爆弾が爆発することでその緊張が解かれることになる。「最初のケースは15秒のサプライズを与え、2つ目のケースでは15分のサスペンスを与えた。この結論は、可能なときには毎回観客に情報を与えなければならないということだ」と、ヒッチコックは言うんです。
この話を知ったときに、「そうそう」とわたしも思ったんです。将来の出来事の情報を知らされることによって読者や観客はドキドキする。本当にそれが回収されるかどうかを確かめたいと思って、読者は読み進めるんじゃないかと。フランスの文学理論家、ジェラール・ジュネットがこの現象を生み出すための語りの手法に名前を付けていて、1972年の研究書のなかで「物語の先のほうで、後に語られるであろうことを前もっていう」ことを「予告」と呼んでいます。「物語の構成における予告の役割は明らかで、読者の意識のなかに期待を生み出すことである」と。
わたしはこの「予告」──サスペンスを生むために情報をチラ見せすること──を研究しようと思い、博士論文ではフランスの作家、エミール・ゾラの作品における予告の役割や機能を研究しました。
──そこからアダプテーション研究に移行していったのは、どのような経緯があったんでしょうか?
博論が終わる頃に、ちょっと疑問に思ったんですよ。こういった予告の方法は、確かにサスペンスを生み出して、読者を引きつける効果をもちます。でも、これは初読のときにしか有効ではないのでは?と。だから予告の役割は、わたしが最初にもった「物語はなぜ面白いのか?」という問いの半分にしか答えられていない。そこで、「再読のときに面白いと思わせるような効果には何があるんだろう?」と考え始めることになりました。
その問いについて、先ほどのジェラール・ジュネットがすでに答えてくれていました。それは「布石」と呼ばれるもので、彼はこう定義をしています。「明らかな定義によって、これらの予告と布石とむしろ呼ぶべきものとを混同しないようにしよう。布石とは単なる備えの石であり、期待を生じさせず暗示すらしない。その意味は後になってようやく明らかになるのであり、古典的なテクニックであるプレパラシオン=伏線に属するものである」
つまり、「予告」が情報を前出しすることで読者のサスペンスをかき立てるものなのに対し、「布石」とは初読のときには気付かずに通り過ぎてしまうもの。ただ、クライマックスまで読んだあとで、「あそこにあったのは、実はこういう意味だったんだ」とピンとくることってあるじゃないですか。それに気付いたときには「おお!」と感動しますし、「もしかしてほかにも気付いていなかった布石があるんじゃないか」と再読を促すきっかけにもなる。なので、初読の際にサスペンスを引き起こす「予告」に対し、「布石」は再読を促すのだとしたら、この布石こそが再読に耐え得る力をもつ作品に見られる現象なんじゃないかと思い、博士課程のあとはこの「布石」という現象を「予告」と比較しながら研究をすることになりました。
そのときに、同じ物語を別の芸術ジャンルで語り直されたものと比較すると、例えば原作では布石として描かれていたものが、別ジャンルになると予告的に演出されていることがあるんです。そうやって原作とアダプテーション作品を通して予告と布石を比較していくと、芸術ジャンルによって予告と布石が使い分けられていることが多いのに気付くことになりました。それは、さまざまな芸術ジャンルのなかでも、初見・再見にそれぞれ適した形式があるからで、例えば本は再読に適したメディアなのに対し、舞台芸術は再見しづらい。
こうした媒体の特性を基に予告と布石の研究をしていくといいんじゃないかと思い、芸術ジャンルの転換=アダプテーションの研究に片足を突っ込んでいくことになりました。アダプテーションは、ひとつの物語に対して異なるジャンルで表現されたもの同士を比較できるので、予告と布石を比較するのに最適だったわけです。
──中村さんが、アダプテーション研究を通して探究したい問いとはどのようなものでしょうか?
まずは「既に語られてしまった物語をもう一度新しく語り直そう」とする、その原動力は何なのかということ。観客たちにとっても、知っているストーリーをもう一回見ようとするのはなぜなのか? それから、アダプテーションを惹起する力が原作にあるのか? アダプテーションされやすいものとあまりされないものがあるのはなぜなのか、ということです。
また「予告と布石」というテーマとアダプテーションを絡めて考えると、アダプテーションには、その物語を初めて体験する鑑賞者とすでに原作を知っている鑑賞者の両方を同時にターゲットにしないといけない、というジレンマがあります。この両者に対して、同時に効果のある手法は存在するのか?ということも問題意識としてもっています。
トランスレーションとアダプテーション
──アダプテーションでもうひとつお聞ききしたいと思ったのが、その成功事例について。例えばハリー・ポッターのアダプテーションは、一般的にいえば大成功だと思います。原作から映画になって、映画がさらなるファンを獲得して、また原作を読ませている。そうした循環が起きているし、経済的にも大成功している。これはぼくの邪推かもしれませんが、作者のJ・K・ローリングは映画化することを前提に小説を書いたんじゃないかという気もするんです。そうやって映画化、舞台化されることを前提に文学が書かれるというのはよくあることなんですか?
ローリングが映画化を前提に書いたかどうかはわかりませんが、少なくともアダプテーションされやすい作品とそうじゃない作品があるとはいえると思います。そうしたアダプテーションを惹起する力が具体的にどんなものなのかはまだわかっていませんが、やはり映像を喚起するような描写が多い作品は映画化されやすいのかもしれません。
面白いのは、映画がない時代に書かれた小説のなかにも、現代になってものすごく映画化されているものがあること。しかも映画がない時代に生まれたにもかかわらず、「ズーム」や「トラベリング」といった映像手法を喚起するような作品がけっこうあるんです。
例えば19世紀の小説家フローベールの『ボヴァリー夫人』では、建物の中にいる登場人物が主人公の女性を口説いてるシーンと、建物の外でスピーチが行われているシーンの2つの場面を交互に描写するところがあるのですが、これはまさに映画でいうところのモンタージュ的な表現になっている。フローベールは将来映画化されることをわかっていたんじゃないかと思うくらい、映画特有の手法を小説のなかで使っているといわれています。
だから、そうした映像的な手法を取り入れやすい小説はたしかにアダプテーションされやすいと思うんです。ローリングがアダプテーションされることを望んでいたかどうかまではわかりませんが、彼女は自分の頭のなかで映像化されたものを書いていた、ということは大いにあり得るんじゃないかという気がします。
──ローリングにしてもフローベールにしても、まず自分の頭のなかに映像があり、それを言語として表現していたのかもしれないと。今度はその小説を読んだ読者のなかで映像が再生される。つまり、アダプテーションとは単に「言語→映像」という一度の転換だけではなく、「映像→言語→映像→……」と幾重にも重なった関係であるといえるのかもしれないですね。
そうですね。アダプテーションというのは「他者の解(釈)を共有する行為である」と、ジャン・クレデールとロラン・ジュリエによる共著は述べています。読書をする際に、それぞれの読者が頭のなかで映像を思い描きながら読むわけですが、その映像って千差万別のはずですよね。ひとつとして同じ映像はない。
けれども、アダプテーションというのはある意味、そのひとつの答え合わせといえると思います。それぞれが独自のイメージを描いているなかで、「自分がイメージした映像はこういうものです」と見せることができる。そうやって人の頭のなかを覗き見れるような機会でもあるんですよね。
──中村さんが考える「翻訳=トランスレーション」と「翻案=アダプテーション」の共通点や相違点はどういうところにあるのかを教えてください。
共通点は、翻訳も翻案も解釈のひとつであるということですよね。先ほどお話ししたように、アダプテーションとは千差万別に行われる解釈のひとつ。同様に、翻訳をする際にも翻訳者の解釈が必要になってくるわけで、その点ではいかに透明な翻訳を目指してもやっぱり個人を消せないものです。「たくさんある解釈のうち、あなたのはどう?」と、本来ならば見せられない他人の頭のなかを見させてくれる──そういった行為であるという点で、翻訳も翻案もクリエイティブなものであると思います。
それと同時に違う点として、翻訳はなるべく原文に忠実でなければいけないのに対して、翻案は自由度が高いものだと考えられていることがあると思います。もちろん原作の核が大事にされていないアダプテーションは原作のファンから怒られてしまいますが、言語情報を視覚や聴覚にシフトするなかで、原作の設定や内容を大胆に変えることが許されている。そうした次元をシフトさせながら、かつ作品が伝えようとする核をそのまま保つことができるのが、アダプテーションの魅力だと思っています。
──そのように高い自由度をもつなかで、優れたアダプテーションとはどんなアダプテーションだと中村さんはお考えですか? この答えも人それぞれの解釈で異なるものだと思いますが、現時点での中村さんのお考えを伺わせてください。
やっぱり、感動するようなアダプテーションは「シフト」をする。
例えばですけど、原作の小説に叙述トリックがあったとします。それは、文章、あるいは言語情報でしかできないトリックなわけですが、アダプテーションにおいてそのトリックを言語以外の別の要素にシフトさせることで表現しているものは、すごいと思います。言語情報でしかできなかったトリックをどのように映像化するか、あるいは音声にするかという難しいお題に対して、真正面から取り組んでいるような作品に出会うと、それはいいアダプテーションだと思いますね。
──具体的に特にこれはよかった、という作品はありますか?
トルストイの『アンナ・カレーニナ』では、冒頭で汽車の点検係が列車事故に遭う現場に主人公アンナが居合わせる場面が、不吉な予感を抱かせる予告になっています。それからだいぶ後でアンナは、勢子が出てきて鉄を鳴らしている、という悪夢を見るんです。
原作ではその2つの異なるエピソードによってヒロインの不吉な将来が暗示されているわけですが、映画ではそれらのエピソードがひとつにまとめられています。勢子の悪夢は出てきませんが、その代わりに事故が起きるシーンで、汽車の点検係が車輪を叩く「カンカン」という音が挿入されることになります。
つまり、「勢子が鉄を鳴らしている」という悪夢の代わりに、車輪の「カンカン」という音で不吉さを象徴しているんですよね。映画ではそのあとにも、アンナが若い将校と出会って浮気をする場面や、最後にアンナが自殺をしようとする直前にも、その鉄を叩く音が挿入されている。そうやって物語の予告を「音」という次元に落とし込んでいるのは、いいアダプテーションの事例だったと思っています。
映画『アンナ・カレーニナ』のトレーラー
アダプテーションが原作を超えるとき
──ぼくたちが考えている創訳(トランスクリエーション)と近いものに、「意味のイノベーション」という言葉があります。ミラノ工科大学のロベルト・ベルガンティ教授が提唱している概念ですが、彼は意味のイノベーションにおいてメタファーが極めて重要であると話している。つまり、そのもの自体よりも、それが何を隠喩的に表しているのかということから解釈を広げたり、解釈を移行させることができる。その点で、アダプテーション理論が大事にしていることと、意味のイノベーションの考え方は非常に重なっているのかなと。
イノベーションという意味では、原作が目指したもの以上のものをアダプテーションが提供する、ということがあるんですよ。原作と同じ核を伝えつつ、かつ+αの何か、さらなる感動というか、カタルシスみたいなものを観客に提供する。そういう作品も、やはり優れたアダプテーションだと思います。
例えば2014年にロンドンで、エミール・ゾラの『テレーズ・ラカン』を舞台化したものを観たんですけど、開始早々、ガーっと涙が出たんですよ。別に泣くようなストーリーじゃないので、悲しいという涙ではなく、あの原作をこうアダプテーションしたのか!という事実にカタルシスを覚えた。なかなかこのカタルシスを客観的に説明するのは難しいんですけど、あれは確かに、原作の核を伝える以上の何かがあったアダプテーションでしたね。
舞台『テレーズ・ラカン』のトレーラー。中村さんは『Prétexte : Jean-Jacques Rousseau』にて『テレーズ・ラカン』のレビューも書いている。
──わかります。ぼくもロンドンで『スクール・オブ・ロック』のミュージカルを10回以上観たんですけど、元になっている映画よりもそれがアダプテーションされた舞台のほうが何百倍も感動した。プロットは変わっていないんだけど、舞台では音楽がガラッと変わっていて。そのアダプテーションによって作品の核が熱されて強まった、そのえも言われぬ熱さに自分は感動した気がします。
いまのお話を聞いて、優れたアダプテーションの条件としてもうひとつ思い出したのは、アダプテーション先のジャンルの特徴を活かしてることです。
例えば、芥川龍之介の『藪の中』ってあるじゃないですか。『藪の中』は、ある事件について、それぞれの人がそれぞれの目線で見たことを語る話ですが、あれを野村萬斎が狂言にしたんですよね。そのときに、お面を付けている人と、付けていない人がいて。語る人はお面をせず、それ以外の登場人物がお面をして出てくるわけです。語り手が順繰りに変わっていくなかで、シーンが変わるとお面を付けている人が交代していく、という演出がされていました。
ところで、能や狂言では、ワキと呼ばれるいわば出来事の証言者のような立場の人物は能面をせず、シテと呼ばれる語られる対象の存在は能面をします。『藪の中』という特殊な語りの形式に、能や狂言で伝統的に使われるお面の機能を付与している点で、すごくおもしろいアダプテーションだと思ったんです。
──morphでは「言語から他の言語へ」のトランスクリエーションを主に行っているのですが、アダプテーションの理論を学んだり、優れたアダプテーションの実例を知ることは、トランスクリエーションの理論を発展させることにとてもつながると今回お話をお聞きして確信しました。
「言語から他の言語へ」のトランスクリエーションでも、意味だけでなく、音や形といった言語がもつ多面的な次元をフルに活用できたら面白いかもしれないですよね。それに「言語」と一口にいっても、トランスクリエーションする先の言語がどういうジャンルのテキストなのかで翻訳の仕方も違ってきますよね。例えば公文書だったら透明な翻訳が求められるかもしれないけれど、もっとユーモアをもってシフトすることが求められるテキストもあるかもしれない。テキスト自体のジャンルも多様なのかなと思います。
──最後に、インタビューする方々に聞いている共通質問です。中村さんにとって翻訳とは何でしょうか?
翻訳とは、やっぱり個人的な脳内解釈の見せ合いっこをすること、それを通して、他人の頭のなかを覗けることだと思いますね。翻訳は、必ず翻訳者の解釈というフィルターを通される。そうした普段は見ることのできない他人のフィルターに触れることのできる、貴重な機会だと思います。
PROFILE
MIDORI NAKAMURA
中村翠
京都市立芸術大学准教授
Interview by Yasuhiko Kozuka
Text by Yuto Miyamoto
Profile photo by shimizu kana
Photographs Courtesy of Midori Nakamura