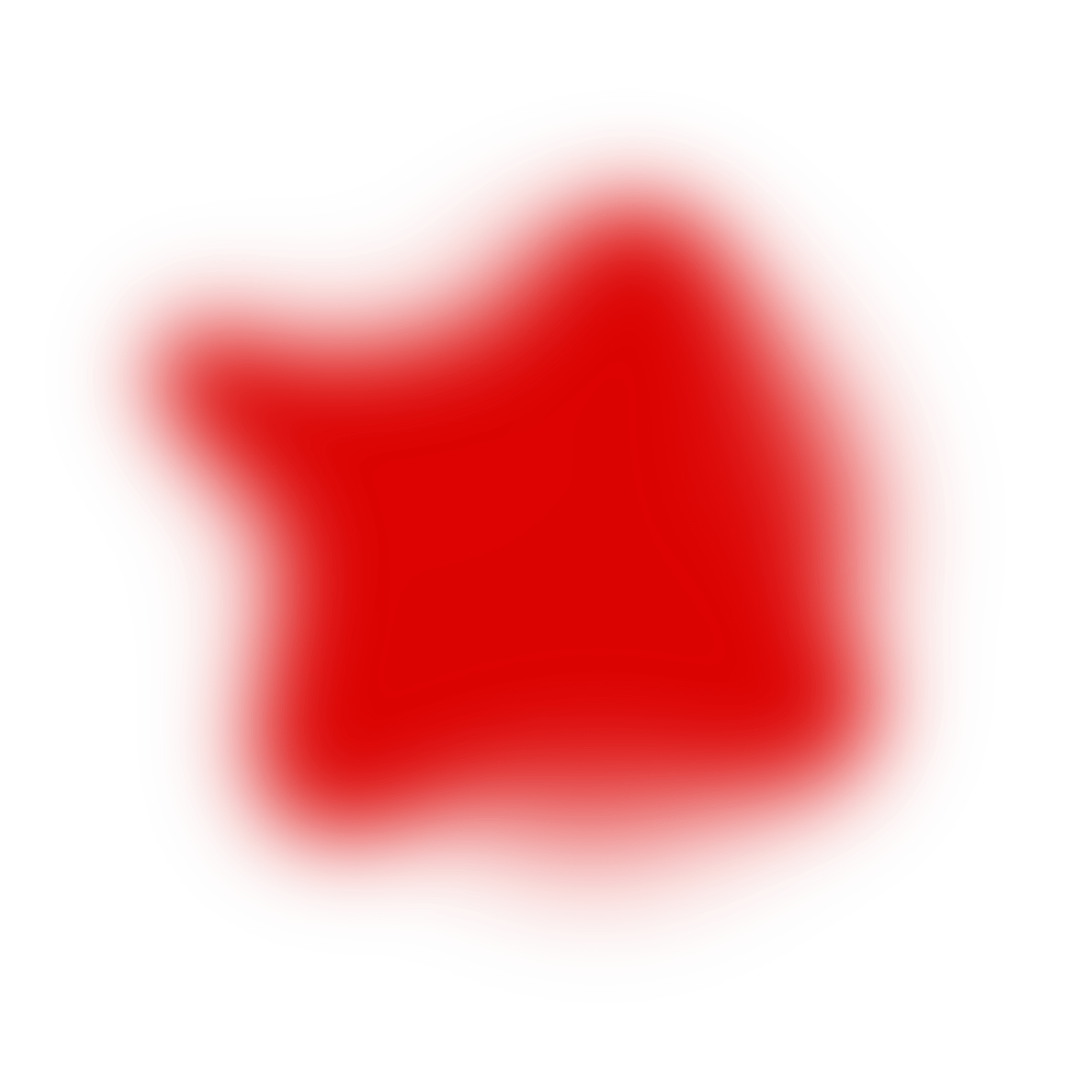洋書の波乗り
この冬は、例によってオミクロンにかかり、症状こそは軽くても外には出られず、ふわふわした浮遊感の中、何をする気も起きず、結局ずっと憑かれたように洋書を音読していた。
言語の学びにおいて、何が一番大事かと言えば、その音世界を丸ごと身体に取り込む音読に尽きる。でもいつだって問題は、それを楽しくやり続けられるかどうかだ。
昔から、自分が語学を「勉強」する時にも、いつまでも参考書の世界ではなく、触れることに喜びを感じられる素材にしようと、好きな作家の洋書を読んだものだった。
世界一周中の船の日々も、駆け出しの通訳の仕事をしながら、夜な夜なブツブツ言っていた素材が、例えば、アメリカの現代作家・ポール・オースターの『ムーン・パレス』だった。
編み出したやり方はこうだ。
1 好きな本(原書)をまず英語で音読しながら、ボイスレコーダーに録音
2 録音した英語を1.5倍速以上で再生し、それを聞きながら同時に日本語訳の本を読む
3 本を読んでない時も、英語音声を流し、聞こえた音をそのまま声に出すシャドーイング
やってみると、暮らしのそこかしこで自分の声がこだまする、ちょっとシュールな世界だ。もちろん、これは文学に限らず、自分の好きな詩でも雑誌でも歌でも、どんな言語でも応用が可能。だが、初級時のフランス語とか中国語の自声を聞くと絶望する。でもその落胆こそが、燃料にもなる。
キモは、自らの音読した英語を聞きながら、今度は日本語本を手にとり、翻訳家の柴田元幸さんの訳出を同時に追いかけていくことだ。英語から日本語を旅するとはこういうことか、というたまらない感動と学びがあった。
他にも、アルクが出している『村上春樹ハイブリッド』という彼が出した訳文のアンソロジーのひとつ、作家ティム・オブライエンの生の肉声での録音も最高だった。家でも車でも数百回は聞いて、音読して、その文章は音感も言霊もまるごと血肉化された。
英語が日本語で聞こえる
昔、通訳の師匠が、「同時通訳は練習をしていけば、日本語が英語で聞こえてきて、英語が日本語で聞こえてくるようになります」、と、およそ禅問答のようなことをのたまっていた。
でも優れた訳文を見ながら、二言語を同時で行き来していると、音感も文法もまったく違う両者の言語に、自然と言葉の波に乗り、(時に呑み込まれるような)没入的で身体的な感覚を覚える。
言葉は、それが苦手な多くの人から、理屈とか頭でっかちと、敬遠されることも多いけれど(そしてそういう言葉使いもあるけれど)、優れた使い手は、それを間違いなくもっと深いところで感じ、表現をしていると思う。
そこに誰がいるのか
通訳をはじめ、魅力的な演説や講義、パフォーマンスを見る時、なぜそれに人は感動したり、目が釘付けになったりするのだろうか。
ひとつは、これまでも語ってきたリズム感とか身体的同期感という言い方ができる。これは技とも構えとも言えるし、人が持っている鼓動そのもののつながりなのだと思う。
しかし最近ふと、大学時代のK先生のイギリス文学論の授業を思い出して、何か違う角度のヒントをもらった。普通ならば大講義室の200から300人レベルの授業というのは、ある種の予定調和であり、計画通り淡々と進んでいくことが多い(ゆえに多くの学生は眠る)。
そこが、先生は違った。すでに、講義の最初から、どこか遠くを見通しながら、「あの日思ったのだ、シェイクスピアは……」「違う、ロミオはそんなことを言ったんじゃない!」と、すでに、彼なのか誰なのか、その渦中からの人物が表出して来ていて、???と、こちらの関心は尽きない。気づけば、講義室には劇場かのような場が生まれている。
これは、言葉の使い手として大きく影響を受けた、前述の、翻訳家の柴田元幸さんの「同時翻訳」を初めて見た時の感動にも通じるものがあった。
とあるイベントで、ヘミングウェイの『殺し屋 Killers』を彼がライブで訳していった時、日本語と英語が交互に読み上げられていく瞬間、同時に、ポンポンと、その人物たちの姿が見えた。それぞれの個性が、文体というよりもはや声音の違いとして、明確に存在していた。この場には物理的にいない作中の人物を彼は召喚していた。
あるいはまた、自分が住む京都の山奥の京北で、敬愛する地元の河原林さんと話していると、20代(27代という説も)ここに住み続けて来た彼が、この地の歴史を語る時に、もはやそれが彼の話なのか、家の話なのか、地域のことか、そこに個人を越えた広がりが見える。まるで背後にぼわ~っと、かの土地のご先祖様が佇んでいるような、そういう不思議な感じがする。
東京で、どれだけ能力や人格が優れた人と会っても、こういう感覚を知ることはなかった。
皆に共通して、そこでは「何を言ってるのか」ということよりも、一体「誰が言ってるのだろう」という、不思議な問いが湧き上がる。いるはずのない他者がそこにあり、自分もつながりの一部となる。そういう意味では、こうした演劇的な行為を呼び寄せながら、人はひとつの管であり通路、チャンネルになっているのだと思う。
古代の真言につながる
今、自分なりにサンスクリット語を深めながら、2500年前(かそれ以上)のインドの古代の音を、現代に同じ形で発音できることが、とても面白い。自分にとっては、ある文化と向き合う時には、常に、その国の言葉の音と、その言葉が体現する身体性をつかむことが、ひとつのやり方であり、喜びだからだ。
それが、真言密教の、非常に学識と知恵に富んだ僧侶の方とお話をしていると、バラモン教では、サンスクリットは絶対的な真言だった、と教えてくれた。仏教では、比較的、ラテン語的な記録・書き言葉としての捉えられ方が強いサンスクリットに対して、バラモンが発するその「音(真言)」はまさに神を降ろしたり、つながるための言葉。ところがその発音が、お布施が足りないと、「んー、ちょっと間違っちゃうかもな」となって、その場合災厄はクライアント側に降りかかる、という恐ろしい話だった。
通訳というのは、一般的な養成システムの中では、非常に精確な、機械的メタファーで語られる。あるいは、実際世の中のほとんどの人はそう思っている。しかし、自分にとっては、この行為は、より演劇であり、場合によっては憑依、という感覚が近いと、24歳のやり始めた頃から思っていた。
隠せない自分の振る舞い
誰かの言葉を代弁する、ということ。それは、大きな責任を伴う。バラモンではないけれど、通訳者は、言葉の意味内容を一切変えずに、このスピーカーを好ましく思えば、いわば好意的な印象が残るような「振る舞い」をすることもできる。そしてその逆もしかり。
自分は誰かを貶めるような通訳をしたことは、全く思い出せないけど、各国の思惑がぶつかり合う国際会議で、日本代表チームの一員として、言葉の価値を増幅(= amplify)するような「振る舞い」を、クライアントと合意の上で行ったことはある(そして多いに成功した)。
スピーチやパファーマンスは、時に語られること以上に、その佇まいが発している情報やエネルギーがとても多く、不思議とそのことが記憶に残る。
あるいは、そもそも自分という人間の、声の発し方、言葉の選び方自体が、実際は、誰がやっても同じ言語的変換、という機械的メタファーとは程遠いほどに、自らの存在や来歴を、いやがおうにも語っていると思う。
そういう、表出される通訳、演じ・乗りうつる通訳こそが、個の自我を超えた歓びを感じられる、この仕事の醍醐味だと感じる。
COLUMN
TEXT & EDIT : Kei Nakayama