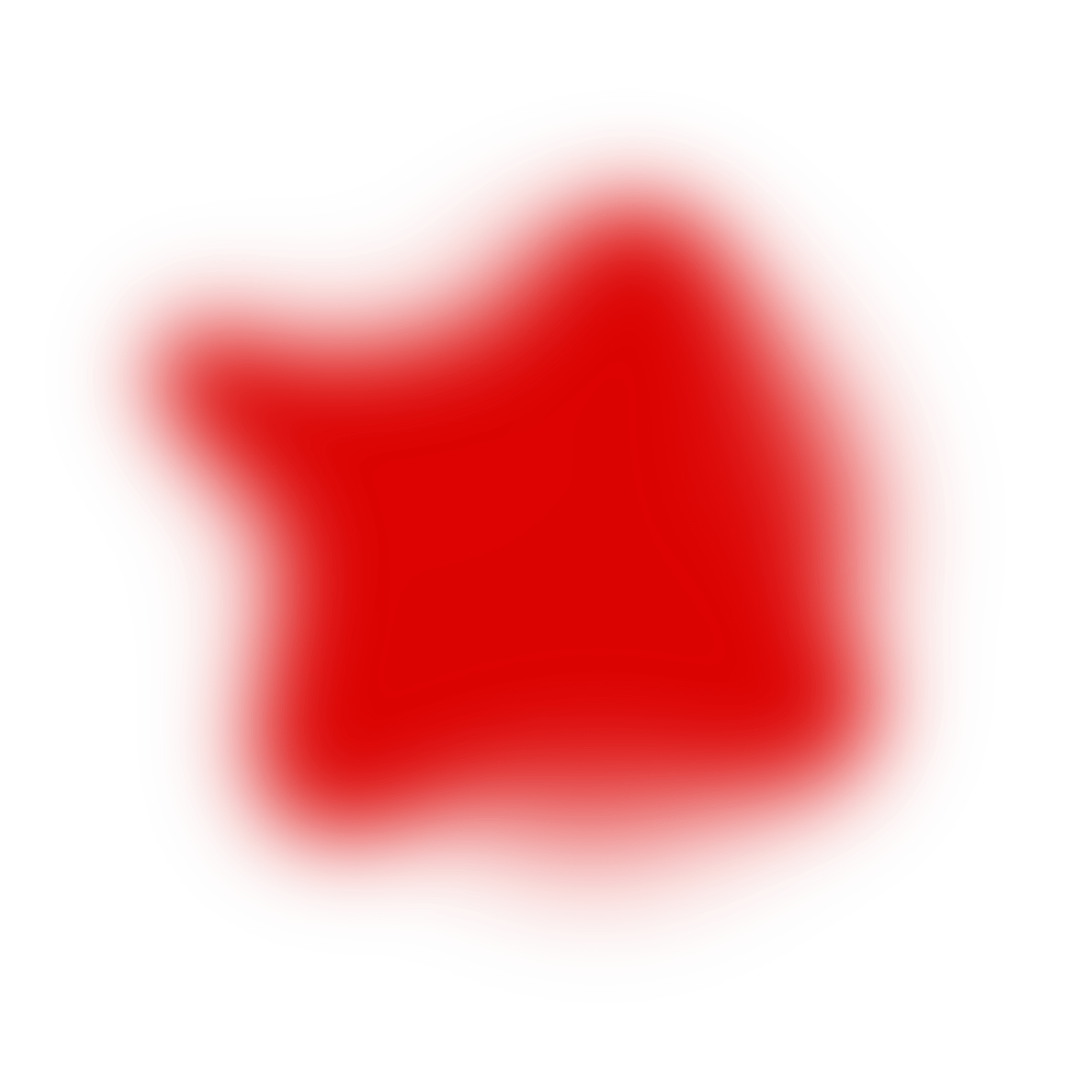第九回 拡大された創造力論へ – 自然を創造力の主体として受け入れる
作り手が「作家」という特権的な立場から一段下に降りて、自分を取り囲む物質や物、他の人たちと同じレベルで混じり合い、対話しながら発揮されるのが「控えめな創造力」であったが、人間が自然に対しても同じ「控えめさ」(humbleness)を忘れず、自然を創造力の主体として受け入れる時、初めて自然と人間との間の共同作業による創造力が可能になる。ムナーリやカスティリオーニの時代には、創造力に自然環境を守るという使命が課されたことがなかったため、彼らの創造力の「控えめさ」の中にそのような可能性があるとは想像されたこともなかった。しかし、実はそこに、人間を自然から分け隔てず、両者の本格的な共生を実現する創造力を探求する、新たな創造力論の可能性が潜んでいたのである。そのことを、現代に活躍する創造家、活動家、思想家たち(いずれも優しき生の耕人たちと言える人たち)の作品や活動や言説とともに確認することができる。
動いている庭
環境問題が深刻化している現代においては、自然に対し「控えめな」姿勢で寄り添い、その創造力をサポートするタイプの人たちが注目されるようになっているが、その中でも代表的な存在として、植物の創造力に主体性を認め、それを助けながらごく「控えめに」介入するという革命的な造園術(“jardin en mouvement” = 動いている庭)1を開発したフランスの庭師であり、ランドスケープアーキテクト、そして作家でもあるジル・クレマン(1943-)がいる。
クレマンは、1977年にフランス中央部2の起伏のある土地を4ha購入し、そこに自力で石を積みながら家を建てた。そしてまず、周囲にある約1haの土地を使い、「この場所で生物多様性を守る実験的庭園を作ろう」3と思った。しかし、当時彼らが教えられていた造園術は、ただ小綺麗に美しいフォルムを作り、それを守ることを目ざすばかりで、余計な動植物は全て排除の対象にされていたため、これと全く相容れなかった彼は「そこに棲む鳥や獣、昆虫たちにトラウマを与えない」4方法を自分で徐々に編み出していった。彼は机上で図面を引かず、まずある場所に身を置いて、「自然に生えている植物たちが示唆する“動き”と“流れ”に従うこと」5から始める。これは、自分が「話す」前に「聞く」ことを大事にする「控えめな創造力」の基本そのものである。彼は実際よく「植物の創造力」と言う言葉を口にするのだが、まず目の前にある植物を創造力の主体として認め、その特徴を精確に見極めながら、それに寄り添う形で自分はごく控えめに介入していく。そのため、彼の手がける庭園はいつも人間と植物の共同製作の成果となる。
こうして辿り着いた「[植物に]出来るだけ合わせて、なるべく逆らわない」という彼の哲学は、まさに「控えめな創造力」のエッセンスそのものである。具体的には、春になり、草花の芽が出てくると、それらの正体を見極め、まだはっきり見えていない多様なフォルムを想像しながら、それらを明確にすべくどこに刈り込みを入れ、どこは残すかという判断を下していく。季節が進みまた別の種類の植物が生えてくるに連れて当然姿を変えていく「動いている庭」には、伝統的な西洋庭園のような固持すべきフォルムはない。常にエントロピーと戦ってきた西欧の庭園(特にイタリア式庭園)の歴史を考えると革命的なことである。例えば、もし小径だった所に飛んできた種から美しい花が咲いても、植物がただちに除去されることはなく、むしろ通路の方を移動することが考慮されると言う。一番の主体はフォルムでも人間でもなく生命の創造力なのである。
こうして、クレマンの設計した「動いている庭」ではいつも、誰が「作者」なのかがぼやけている。庭のプランナーであるクレマンなのか、現場で日々管理する庭師か、それとも一年を通して多様な創造力を発揮する草花たちか。「作者」の顔が草むらにまぎれて見えなくなっている。作者/作品と言う概念がこうやって解消され、特に絶対的な創造者としての人間が自然を支配し形まで作るというパラダイムが消えることになる。これこそ、世界をエコロジカルに見つめるための一番の基本なのである。それはただ人間が自然のように振る舞うことではない。周囲の自然の創造力を受け入れることにこそポイントがあり、そのためには、人間の創造力は「控えめ」である必要があったのである。
二つの歴史観/世界像
ところで、クレマンの「動いている庭」に働く創造力を「創造力の木」(連載第三回参照のこと)の図式上でみるとどこに特徴があるのだろうか。一番大きな特徴は、それが、我々の視線をこの図式の地下の部分に力強く引き下ろすことだろう。
大抵の人は、木を思い描く時、地上に出ている幹と枝葉や花だけをイメージする。地下の根や土壌の内部のことを思い描く人は稀で、植物学者の他、ユングのような心理学者やヨガの実践者6、あるいは自然に対する意識の高い芸術家くらいだろう。まして地下の部分、それも根よりもさらに下の土、土壌の部分に注目する人は珍しい。同様に、自分たちの創造力を「創造力の木」の図式において検証してみると、そこで我々自身が注目している部分も全く同様で、目に見える地上部分(つまり文明:人為によるものの世界)には日常的に意識が行くが、目に見えない地下の部分(根、土壌:無意識および自然/非人間的なものの世界)にはなかなか意識が回らない。目に見えていない。このことを「創造力の木」の図式上で表現すると、根と土壌の部分に濃い影が落ちて真っ黒く塗りつぶされているようなものである。(図1)
そして、この認識の「影」が生み出す可視領域/不可視領域の間の二項対立は、「人間/非人間」のほか「精神/物質」「文明/非文明」「理性/狂気」「覚醒/睡眠(夢)」「一般言語/野生言語」その他多数のヴァリアントとともに、人間を自然などに対して特別扱いする「二元論的な歴史観(世界像)」を支えている。(図2)今でも「歴史」はあくまで人類だけの営為だとみなされるのが一般で、我々は「歴史」の主体として自然の風景や自然の動植物を想像することがなかなか出来ない。歴史番組や歴史の授業の中でも山河や動植物の話が主題となることはまずありえないが、それは、意志をもって思考が出来て創造力があるのは自分たち人間だけだと我々が思い込んでいるからである。こうした我々の二元論的な歴史観は、地球上で日々紡ぎ出される歴史の一部だけを可視化し、残りをシステマティックに認識の視野外に追いやって来たわけだが、そのこと自体が人間に平気で環境を破壊することを許して来た元凶であり、ずっと黒々とした影に隠されてきた歴史の「死角」に光を当てることが何にもまして緊急な課題であるのは、もはや誰の目にも明らかだろう。パラダイムの変革なしに本格的な変化は導けないからである。
このような状況において、クレマンの「動いている庭」は、現実レベルで生命の論理に合った造園術を展開するとともに、パラダイムのレベルで決定的な変革をもたらしてくれる。自然自身の創造力に注目する彼の作業は、認識の画面上で、まさに黒い影に隠されて見えなかった地下の部分(非人間的なものの領域)にしっかり認識の光を当ててくれるので、それによって、人間的なものと非人間的なものの間の二元論が解消されることになるのだ。(図3)



これは、かつてヘンリー・デイヴィッド・ソロー(1817-1862)7が祈念していたことにも通じている。彼が信じたように、野生、つまり非人間的な生物や環境にも意志と創造力を認めながら、それらをも歴史の主体として認識出来るような枠組み(一元論的歴史観)を作り直すことは、人間が本気で地球という惑星とともに生きていこうと思うならば、なんとしても、そして何よりも先に実現しなくてはならない課題の一つである。だが、その使命を全うするには、(この実践が現代人には完全に欠けているのだが)まず、我々全員が、日常生活の中で、自然に対してもっと注意深い眼差しを向け、生き物や植物に触れ、そして南米の森林に住むインディオたちのように自然と共生できる知性を保持する人々から、自分たちの閉じ込められている技術思考(合理主義)のそれとは異なるパラダイムや生き方について、謙虚に教えを乞うことから始めなくてはならないだろう。
我々の同時代には、既に多数の同志(優しき生の耕人たち)がこの壮大なパラダイムシフトに挑み始めている。中でも、偉大な業績の一つとしては、サルガドが八年という歳月(2005-2013年)をかけて、世界中のまだ文明に冒されていない風景と動植物、そして数千年前から自然と協調する生活を保って来た原住民たちだけを撮った壮大な写真プロジェクト『ジェネシス』が挙げられるだろう。また、人類学者のエドゥアルド・コーンが、エクアドル東部地域のアマゾン川上流の森に住む人々を観察しながら、彼らの日常生活が非人間的な存在たちのそれと緊密にからみ合いながら大きな編み目を構成している様態を、特に記号論的に考察して記した『森は考える』(2014年)も極めて重要な成果と言えるだろう。サルガドの『ジェネシス』やコーンの『森は考える』のような業績も、人類の視野から抜け落ちていた自然および先住民たちの野生の知を我々の眼前に歴史の主役として力強く連れ戻してくれる。彼らの仕事も、クレマンのそれと同じく、認識の中で黒い影に隠されていた部分に強烈な光を当てることで二元論的な歴史観を解消し、人間だけでなく非人間的なもの(野生)も歴史の主体として認識する歴史観を回復する可能性を我々に示してくれたのである。
サルガドの『ジェネシス』は、ガラパゴスのゾウガメに始まり、イグアナの足、南洋の巨大な鯨、信じられない数のペンギン、そしてブラジルの森林の中やシベリアの氷原という環境と完全に調和して生きる原住民たち、あるいは、人類の歴史を遥かに超えた時間の中で形成された壮大な風景の数々が、歴史家たちの無関心とは裏腹に、地球という惑星の歴史の「主役」として躍動していることを美しくまた力強い写真を通して教えてくれる。そこに歴史の創造力の新しいパラダイムが生まれ、新しい歴史の可能性を垣間見る事ができるのだ。
一方コーンの研究は、我々人間が使っている「記号」と同格に「記号」と言えるものが自然界の中にも無数に存在すること、そして、生命自体が一種の記号過程(意味の生成を含む、記号を伴うあらゆる形式の活動、行為、またはプロセス)であることを認識するところに、上述の二元論的な歴史観(世界像)を超越する極めて貴重な鍵が隠れていることを教えてくれる。しかし、実は、彼のようにアマゾンまで行かなくても、この新しい記号認識を身に付ける機会は、意識の持ち方次第で、身の回りにもたくさんある。例えば、連載第七回に紹介したムナーリ・メソッドの「記号(点と線)」のワークショップ二日目8の朝に宿舎からシルヴァーナ・スペラーティの教育農場までの田舎道を歩きながら参加者たちが現実の中に記号(点と線)を見い出し、撮影する課題を実践する中で、実は、コーンの研究とかなり近い作業をそうとは意識せずに行っていたことに後日気がついた。
人間と非人間を巻き込んだ大きな編み目を見いだす
あの日の朝、スペラーティの教育農場に行く田舎道を散歩しながら見出した点や線を撮影する中で、建造物や飛行機雲など人為的な活動の成果だけでなく、植物(草木)や小石などの自然物、陰影や雲などの気象現象など、無機物有機物を含む、非人間的なものの世界にもはっきり「点」、「線」といえるものが多数見つかった。(図4~9)






特に植物など自然の形象の場合、もちろん人間のような意識や内省によって生み出されたわけではないかもしれないが、そこにもある種の思考とデザインが存在し、それらの形態を人間や他の生物が記号として読み、それなりの対応を見せることから、それらの存在がただの偶然ではなく、まさに記号として機能していることが分る。コーンも言うように、すべての生命には何らかの記号過程が含まれているのである。そして、非人間的なものの中にも記号を読み取ることは、人間の記号と言語だけを特別視しないで全てを同列に見渡す一元論的な歴史観(世界像)に至るための第一歩となる。それが「人間の精神と残りの世界との間の区分けを消すこと」になり、人間を特別視して非人間的なものを歴史の舞台から排除して来た二元論的な歴史観から脱却する助けになるのだ。もちろん、本来ムナーリ・メソッド自体にそういう目的があったわけではないが、自然に常に関心を持ち、人間的なものも非人間的なものも区別なく記号として観察していた彼の眼差しのなかには、コーンが言う「記号もまた人間的なものをはるかに超えて存在すること」をはっきり理解するに至る道筋が含まれていたのである。その意味でも、あの日の朝にやったような記号観察を自然の風景の中で行うことは、人間と非人間を巻き込んだ大きな編み目を見いだすための初歩的な訓練としても大きな有効性を持っていると思われる。
また、図10~14は、スペラーティがあの時に出した課題への参加者の回答ではなく、筆者がスペラーティと自然について思考するために撮影しているものである。





中でも図10から図14に記録されたフォルムは、そのいずれもが生存のための回答としてある生物種が到達した成果(つまり、そこには、人間の合理的思考とは異なるが、生命なりの極めて洗練された野生の「思考」があり、その主体としてコーンはこれらの記号を残す生命体にも「自己 self」の概念を認めようとする)であり、同時にそれらは自らあるいは他者に対して何かを示す記号としての価値を持って風景を構成している。蟻の穴の形も尺取り虫の曲がった身体も枯れ葉の螺旋も、また特殊な花たちの形態も、何かを指示し、意味するために「自然が書いた」記号なのである。
そして、図15から図17にある雲たちの写真も記号についての興味深い思索に誘ってくれる。雲の形態は、その時点ばかりでなく近い将来の気象状況を細かく予想することを可能にし、解読能力のある者にとっては非常に豊かな情報を提供する記号である。また、図17の写真では、自然の雲と飛行機雲という人為的形象が一つの画面を構成しているが、コーンが目指しているのは、まさにこのように人間的なものと非人間的なものが同じ画面の中で混じり合いながら全体が読み取られるような枠組みを提示することである。



それだけではない。ジル・クレマンには『雲』(Nuage 2005年)という著書があって、フランスのル・アーヴルの港から出てチリのバルパライーゾの港まで航行する貨物船に乗船した彼が船上で雲を観察しながら思索する経緯が綴られる。庭の専門家がなぜ雲をと思う方もいるだろうが、著者は、生あるものを理解するには、雲を理解する必要があると言う。同書を読んでいくと、雲という「空中を漂う水」が如何に壮大な地球レベルの複雑なオペレーションの一部であるかということが見えてくるが、それ自体が壮大かつ複雑な創造行為なのである。我々素人にとっての雲は、せいぜい、空というキャンバスに描かれた白や灰色の多彩な刷毛目に過ぎないかもしれないが、雲にはその「水」の起源次第で多様な「不純」物質が含まれ、それがいつか雨となって降ることで地上のどこかの土地や植物を潤し肥やす重要な機能も担っている。もちろん雲の形態を決める要素として気温、風その他実に多様な条件も関わってくるし、その天と地に渡る壮大なスペクタクルの中に、クレマンという観客の知覚と思索も絶え間なく織り込まれてくる。こうして、クレマンのしなやかな散文は、イメージだけでは捉えきれないような、雲を巡る惑星レベルの創造力の劇場を描き出すので、個々の人間だけでなく、人類の総体も敵わないような(それでいて、我々の全てをも含み込んだ)規模の創造力が見えてくる。創造力を人為的な行為に限らず、ここまでスケールの「大きな編み目」において捉えておくことの重要さは、現状ではまだ理解しづらいかも知れない。しかし、このことは、これからの人類が真にエコロジカルな認識をもつためには、決定的な意味を持っているのである。
二一世紀の“men”
こうして「大きな編み目」をものにすることで、人間は、人間と非人間の境界を超越し始める。その時、人間は、ある意味で野生の知を身につける(と言うか、取り戻す)ようになるとも言える。ソローはかつて、この「野生の知」をしっかりと身につけているかどうかで、人間の概念を、英語で言うとsubjects(公民)とmen(人間)という、二つに区別していた。前者subjectsは、「国家機能によって統治される者」11としての「公民」を指すが、それを「創造力の木」で表現する時に見えて来るのは、権力機構としての国家に取り込まれ、本来の人間としての背骨(幹)も足(根)も弱らせ、その意味でかなり脆弱化した人間の姿である。(図18)一方、後者menは、その反対に、国家ではないさらに高い次元(野生)の法に従い、「いかなる人為的な法規の支配にもおのれを委ねることのない、個としての尊厳と良心とを持って自立した人間」12を意味する概念なので、図にはしっかりした土壌とともに根も幹も枝葉も全て揃え、完全な創造力(生きる力)を備えた樹木として現れる。(図19)そして、クレマンもサルガドもコーンも、ソローの挙げる規範に則して言うならば、いずれも見事な二一世紀のmenである。


「創造力の木」の図式に照らして見る限り、戦後のプロジェッティスタたちと二一世紀のmen(優しき生 の耕人たちも)は、明らかにかなり近い資質を持っているように見える。 ムナーリやカスティリオーニたちが登場し活躍し始めた第二次大戦後という時代には、まだ環境への意識がそれほど要求されていなかったこともあり、彼ら自身は、まだ身を持ってこの図式の地下の土壌レベル(自然環境)まで深々と沈降することはなかったかもしれないが(そこは彼らも二〇世紀の都市の人々であった)、彼らの創造力には、しっかりと根及び土壌の方に向かう「退行」のベクトルが流れていた。彼らは、クレマンのように植物や壮大な大気現象に注目したわけでもなかったし、サルガドのように自ら密林に足を運び、そこに生息する動植物を撮影して全世界に発表した訳でもない。また、コーンの観察したアマゾンの森の住人たちのように、いわゆる人間的な知性/創造力とその他の生き物たちの知性/創造力をいつも隔てなく取り混ぜながら扱っていた訳でもなかった。しかし、プロジェッティスタたちが日々活用する「創造力の木」の中には確実に「人間だけでなく非人間を視野に入れることが出来る分析枠組みを創造する」能力が潜んでいたのであり、それはクレマンやサルガドやコーンの中で「人間の精神と残りの世界の間の区分けを消す」のに必要なエネルギーと全く同質のものだったのである。
- 1. 福岡正信(1913-2008)が開発し、その後川口由一(1939-2022)らによって受け継がれ、世界的な認識も得るようになった「自然農」と言うメソッド(これは有機農法とは全く異なって、全てそこにある土壌と植物の力に任せ、一切耕さないし、肥料も一切加えないと言うもの)もこのクレマンのメソッドと同じで、自然そのものの創造力を認め、人間はその自然の創造力を補佐する者として振る舞う。
- 2. クルーズ県クロザン。
- 3. 2009年7月30日にパリのクレマンのアトリエで行った筆者によるインタビューより。
- 4. 同上。
- 5. 同上。
- 6. ヨガの本質も多様な部分が木のように有機的につながった統一体に喩えられ、その場合、当然根は重要な部分として考慮されている。(B. K. Iyengar, L’Albero dello yoga, Ubaldini Editore, Roma, 1989.)
- 7. アメリカの思想家、詩人、博物学者。著作としてはウォールデン湖畔の森に建てた小さな小屋で二年間過ごした記録を基にした『ウォールデン – 森の生活』(1854年)が有名だが、『市民政府への抵抗』はマハトマ・ガンディーやキング牧師にも影響を与えたと言われる。
- 8. 2019年3月15日。
- 9. エドゥアルド・コーン『森は考える』亜紀書房、2016年、76頁。
- 10. 同、21頁。
- 11. 今福龍太『ヘンリー・ソロー 野生の学舎』みすず書房、2016年、72頁。
- 12. 同上。
PROFILE
Yosuke Taki
多木 陽介
アーティスト、批評家