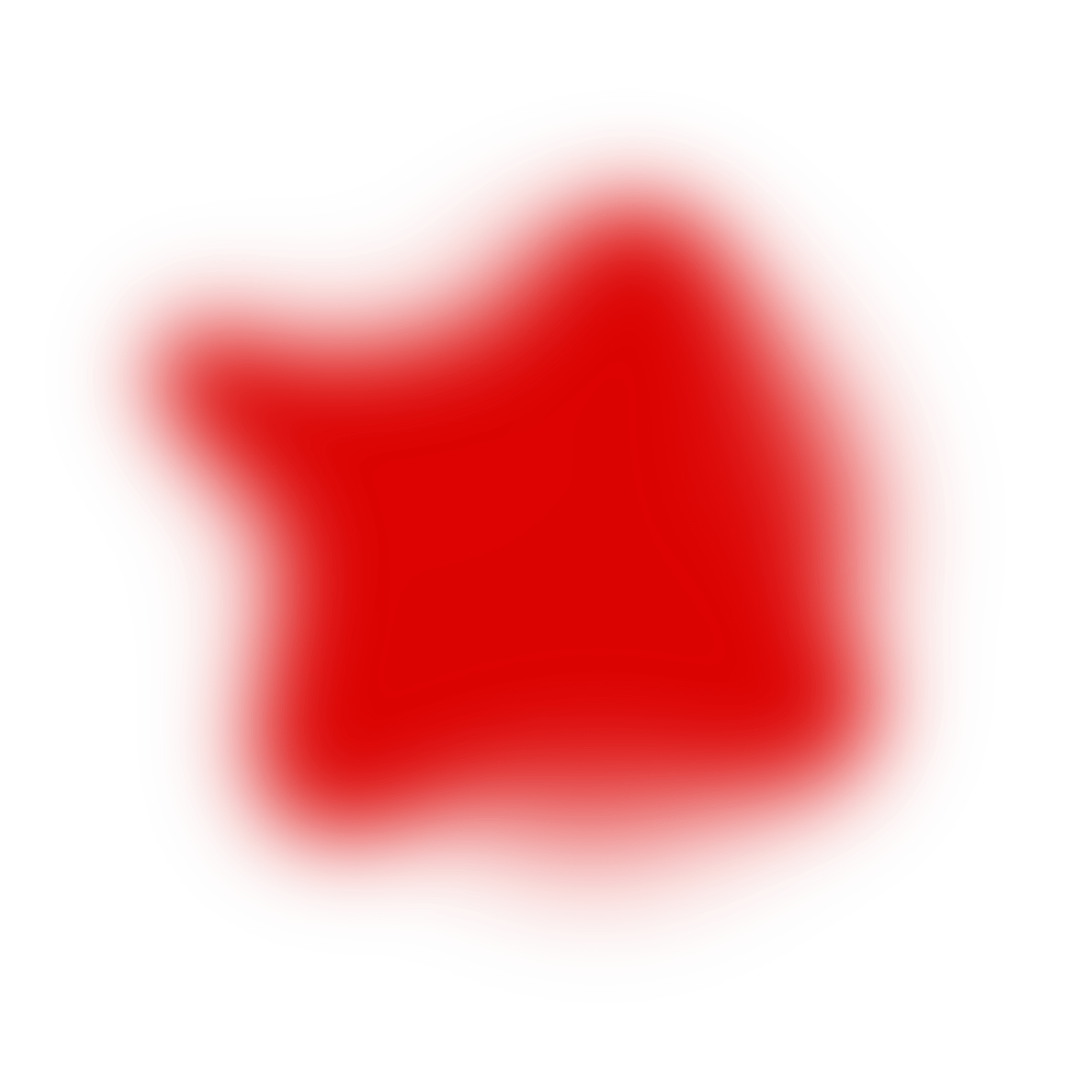2022年年末、コニカミノルタ陸上部が、オランダから1人の陸上関係者を招聘しました。マラソン世界記録保持者エリウド・キプチョゲ等が所属するNNランニング・チームを運営する世界最高の陸上競技マネジメント会社の一つ、グローバル・スポーツ・コミュニケーションのユーリ・ファン・デル・フェルデン氏です。東京五輪2020の陸上競技種目で同社の契約選手が獲得したメダル数は、金8個、銀6個、銅5個。金メダルの数は、国別首位で7個の米国をも上回ったと言いますから、私たちの想像を超えています。
今回の来日は、日本の陸上選手・チームの海外サポートを手がけるインプレスランニング社を通じて実施中のコニカミノルタ宇賀地コーチの海外研修プログラムで、ファン・デル・フェルデン氏が主任講師を務めた縁で実現しました。帰国の途につく成田エキスプレスの車中で、同氏に駅伝視察の印象と日本長距離界への提言をうかがいました。

現地で見た駅伝の印象はいかがでしたか?想像と違うところはありましたか?
駅伝の伝統や魅力については以前からいろいろと聞いていたので、基本的なことは理解していましたが、『百聞は一見にしかず』。今回、自分の目で駅伝を見ることができたことは貴重な経験になりました。特に箱根駅伝では、沿道の途切れない観衆の数もそうですが、大手町のフィニッシュ付近で各大学の応援団やチアリーダーがひしめき合うように陣取って、隣り合わせて演奏しながら応援している光景も新鮮でした。

日本のマラソン大会には何度も選手を連れて来ているので、日本人の仕事が細かいのは知っていましたが、箱根駅伝のTV中継で、往路復路それぞれ5時間以上にもわたって絶えず実況・解説しているのには驚きました。1チーム10人で21チームですから、ものすごい量のリサーチが必要に違いありません。世界のメジャー・マラソンでもそんなに密度の高い中継はありませんから、情熱とディテールへのこだわりは感嘆に値します。画面表示も親切で、日本語が読めない私でも、差がどの位で、開いたのか縮んだのかも確認できました。レース展開自体もスリリングで、コース周辺の自然や都市景観の映像も美しく、自分が携わっている長距離競技をこれからさらに発展させるために何ができるのか、私自身学ぶことが多かったです。来年100回目を迎える歴史ある大会ならではのすごみを感じましたね。ニューイヤー駅伝の関係者の方には申し訳ないですが、どうしてよりレベルが高いはずの実業団より学生の大会の方が人気があるのかもよくわかりました。
コロナ禍以降、海外の陸上関係者から駅伝への興味を耳にする機会が増えたのですが、どんな理由からでしょうか?
世界陸連から陸上界の「世界遺産」に認定されたように、以前から海外にも駅伝に関心のある関係者は多かったと思います。欧州で国際大会が開催されたこともあります。でも普段はみんな日常業務というか既存の大会で手一杯で、新たな企画に取り組むだけの余裕がありません。コロナ禍で多くの大会が中止になり、考える時間ができたこと、そして業界存続への危機感が生まれ、活性化のための新たな一手を講じる必要性に迫られたことから、駅伝が注目を集めたのです。私たちも一時は真剣に欧州での駅伝大会開催を検討していました。
国際的な駅伝大会というと、どういう形態になるのでしょうか?
例えば、駅伝の世界ツアーを組むことだってできます。数チームで、北米、欧州、オセアニアと各地を転戦し、最後は駅伝発祥の地・日本で決勝を行うのです。思いつきですが、例えば、1チーム5人でリザーブが2人、3km、6kmから20kmまで幅のある区間設定にすれば、1,500mのワイトマン、5,000mのインゲブリクトセン、マラソンのトーラなど各種目の世界チャンピョンが一同に会して共演することも可能です。いわば、陸上中長距離界のオールスター戦です。今は夢物語かもしれませんが、要はいかにわくわくするような魅力的なイベントにできるかどうか。夢は大きく持って、そこからいかに現実に落とし込んでいくかを考えることが大切です。

日本人マラソン選手の世界挑戦にあたって、駅伝の功罪が議論されることがありますが、どう思われますか?
駅伝やマラソンの人気が日本の長距離界の底上げに役立っていることは間違いありません。欧州中の選手を集めても、10,000m 27、28分台やハーフマラソン 60、61分台の選手は、日本ほど大勢はいないでしょう。では、なぜ27分、60分の壁を破れずにいるのか?アフリカ人とは人種や体型が違うと言われますが、欧米の白人選手が1,500mや5,000mで金メダルを取ったり、10,000mを26分33秒で走ったりしているのです。
駅伝は1年間という長いシーズン中のほんの1、2試合に過ぎません。世界と戦うという視点から言えば、よいか悪いかを議論すること自体がナンセンスです。駅伝自体を目的化して極端に偏重するのはどうかと思います。重要なのは、選手個人個人にあった育成・トレーニング計画を立て、駅伝もその流れの一環として捉える事です。コーチやチームは、横並びではなく、個々の選手に合わせたアプローチやサポートを提供する義務があります。個々の能力の向上が、ひいてはチーム力の強化につながるのです。
日本の特殊事情ですが、「駅伝」を通じての企業名の露出やイメージアップが実業団チームの存在理由となっているので、駅伝を最優先せざるを得ないという状況があります。
本気で世界と戦う気があれば、それは言い訳に過ぎません。選手自身が、自分の目的は何なのか今一度問いかける必要があります。生活の安定のために走っているのか、自分のポテンシャルを最大限追求するために走っているのか。海外では、多くの選手が働きながら世界を目指し、結果を出して初めてスポンサー契約がつくという厳しい環境に身を置いています。欧米では、選手がコーチを選び、自らお金を出してスタッフを雇うのが通例です。日本人は「覚悟」とか「犠牲」という言葉が好きですが、既存の体制の中でみんなと同じことをしている内は説得力がありません。視野を広く持って、自分に最適な選択肢を追求する事が大切です。
新たな試みとして、具体的にはどんな事ができるでしょうか?
ケニア、エチオピア、ウガンダの一流選手はほとんどが高地の出身で、結果を出している欧米の中長距離選手たちも一年のほとんどを高地でのトレーニングに費やしています。日本の大迫傑選手もケニアのイテンなど海外で東京五輪に備えていましたね。クロスカントリーなど不整地での練習やペースに緩急をつけるファルトレクなども、高低差やペース変化への対応、身体のコーディネーション向上に有効ですし、記録ではなく勝負にこだわる大会に出てレース感を磨くことも必要でしょう。試せることはまだまだいろいろあると思います。
トラックとマラソンの関係、駅伝・ハーフからマラソンへの移行についてはどう考えますか?
ロードや長い距離に適性があって、早くからマラソンへ進むのがよい選手もいるでしょうし、トラックに集中してスピードを培った方がよい選手もいるでしょう。具体的な例を挙げると、私が代理人を務めるウガンダのジョシュア・チェプテゲイ本人は、早くからマラソンを希望していましたが、私たちチームは、しばらくはトラックに集中するよう説得しました。パリ五輪まではトラックに専念して世界選手権10,000m 3連覇を目指します。それは、満を持してマラソンに転向する時にも決して無駄にはならない、むしろプラスになると信じているからです。同じNNランニングチームのケネニサ・ベケレ(エチオピア)やエリウド・キプチョゲ(ケニア)といった選手も、時間をかけて少しずつ距離を伸ばしました。対照的に、ウガンダの先輩にあたるスティーブン・キプロティッチの場合は、本人がマラソンは無理だと思っていた時期から、距離を意識させないよう配慮しつつ、こっそりマラソンへの移行を促した結果、五輪と世界選手権両方で金メダルを獲得するまでになりました。

今後のコニカミノルタ陸上部との活動について教えてください。
宇賀地コーチとは、この2年間にわたって交流を続けてきました。その間の主な活動は、欧州やウガンダでの視察や研修でしたが、英語でのコミュニケーション能力も上達し、今後は研修を継続しながら学んだ内容を実際の選手育成に落とし込んでいく段階になります。その一環として、コニカミノルタ選手の海外遠征や、ウガンダからの選手、コーチの来日も視野に入れています。
今回、監督や選手はもちろん、経営トップの方々とも直接お会いする機会がありました。ニューイヤー駅伝では18位と昨年から3つ順位を上げたものの、かつて「21世紀の駅伝王者」と呼ばれたチームとしては決して満足のいく結果ではなかったと思います。そんな中、大幸社長が、競技結果だけでなく、選手の「人間としての成長」を見てとる事ができた点を評価され、陸上でも社業でも「変化は必須」と「失敗を恐れず、長期的な目標に向けて挑戦し続ける」事の大切さを力説されていました。どちらも弊社の理念とも共通するもので、ぜひ共に前進していければと思っています。そして、宇賀地コーチ、あらためて母校駒澤大学の優勝おめでとうございます!観戦中、駅伝の背景や裏話をいろいろ教えてくれましたが、さすがに詳しくて感心しました。
NNランニング・チームには日本から福田穣選手が加入していましたが、今後も日本人選手を受け入れる予定はありますか?
世界のトップレベルで戦いたい日本や米国の選手がいれば、もちろん今後も歓迎したいと思います。どちらも長距離界の強豪国ですし、大きな市場でもあるので、正直なところスポンサー獲得という点でもメリットがあります。
誰もが世界と戦えるわけではないので、才能は必要です。持ちタイムがよいに越した事はありませんが、さらに重要なのは、世界を知りたいという好奇心を持ち、心を開いて新しい事にチャレンジする気概があること。そのためには犠牲も必要ですが、それをいとわず、モチベーションと覚悟を持って挑戦することができる選手といったところでしょうか。これまで通りのやり方を繰り返していては同じ結果しか生まれません。日本の実業団は非常に恵まれた環境ですが、その枠を飛び出してでも自分の可能性を試したいという選手がいれば、一緒に日本の長距離界の新たな1ページを切り拓くお手伝いができればと考えています。
次回は、いよいよシリーズ最終回。ファン・デル・フェルデン氏、宇賀地コーチとのウガンダ訪問記です。
*2023年1月の大阪国際女子マラソン、2月の別府大分毎日マラソンでも、グローバル・スポーツ・コミュニケーションがマネジメントを担当する海外招待選手たちが、1、2フィニッシュを達成しました。
COLUMN
TEXT & EDIT: Takahiro Nishida