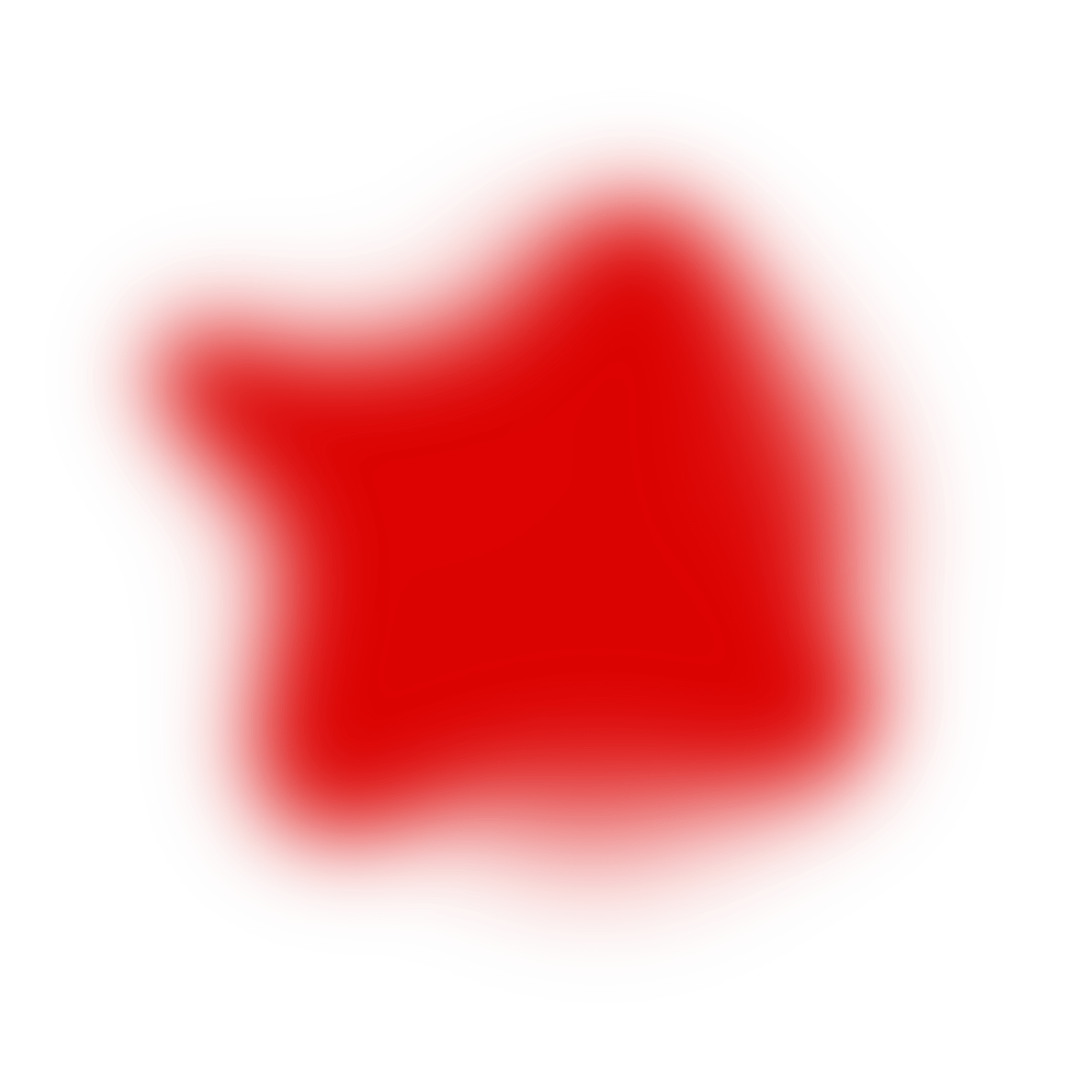第八回 物の時代の終わりに創造力について考える
今回は、ここまで何回かに分けてイタリアのプロジェッタツィオーネの「控えめな創造力」を分析して来た、その 最も深い動機について語ってみようと思う。
物に溢れるデザインスタジオ
幼少の頃に父に連れられて倉俣史朗のスタジオを訪れ、上部にベルのついたレトロなブリキの目覚まし時計(壊れて動かなかった)を頂いた記憶があるが、かつてのデザインスタジオと言うのは、大抵どこか職人の工房を彷彿させるとともに、作品以外にも多種多様な物に溢れ、とても刺激的で、子供であった自分の眼には、倉俣スタジオは文字通り「ヴンダー・カマー」(驚異の部屋)1 そのものに見えた。勿論その時には分らなかったが、倉俣に限らず、当時のデザイナーたちによって集められた物たちは、多くの場合、単なる蒐集欲のためのコレクションというよりは、物の世界に対する彼らなりの分析と批評を体現し、それが非常にフィジカル(物質的、身体的)であると同時に極めて知的な「ヴンダー・カマー」を作り出していたのである。
そのようなスタジオの典型的な例としては、既に本連載でも紹介したミラノのカスティリオーニスタジオ(倉俣スタジオよりは少し早く1961年に設立。現アキッレ・カスティリオーニ財団)が挙げられるだろう。同事務所には、自分たちの作品、図面、模型、プロトタイプ、記録写真らとともに、過去から現代までの日常生活のための夥しい数の道具や椅子類、素材のサンプル、戦前の木箱のような大型のラジオ、某前衛芸術家の作品、ゴム版のスタンプ各種、木製の定規、玩具、ポスター、大小の梯子、さらには古代ローマ時代の朽ちた木の杭から、あまり大きくてすぐに誰もその存在に気づかない巨大な鏡に至るまで、膨大な数と種類の物たちが意図的に配置され、事務所を訪れる者たちはいつもそれらの物たちの饒舌なノイズのようなものに圧倒されていた。物たちの言語はすぐに聴き取れるものではなく、それを理解するには、ある程度の修練が必要だった。(連載第二回参照)
そしてこの圧倒的な物たちの存在からは、以下詳述するように、ここで働いていたカスティリオーニ兄弟と協働者たちの創造力のあり方が読み取れる。彼らは、職人たちが道具や素材と対話する術を心得た人々であったように、いつも手元にある物質の特性や既存の道具たちの中に秘められた知性の声に耳を傾け、「作る」というよりは、それらを種にしてそこから青々とした植物を大事に「育てる」庭師か農夫のような態度で物づくりを実践する人々であった。その意味でも、ブルーノ・ムナーリの著作の題名「物から物が生まれる」(Da cosa nasce cosa)は、まさにこの時代の創造力の本質を捉えた言葉であった。














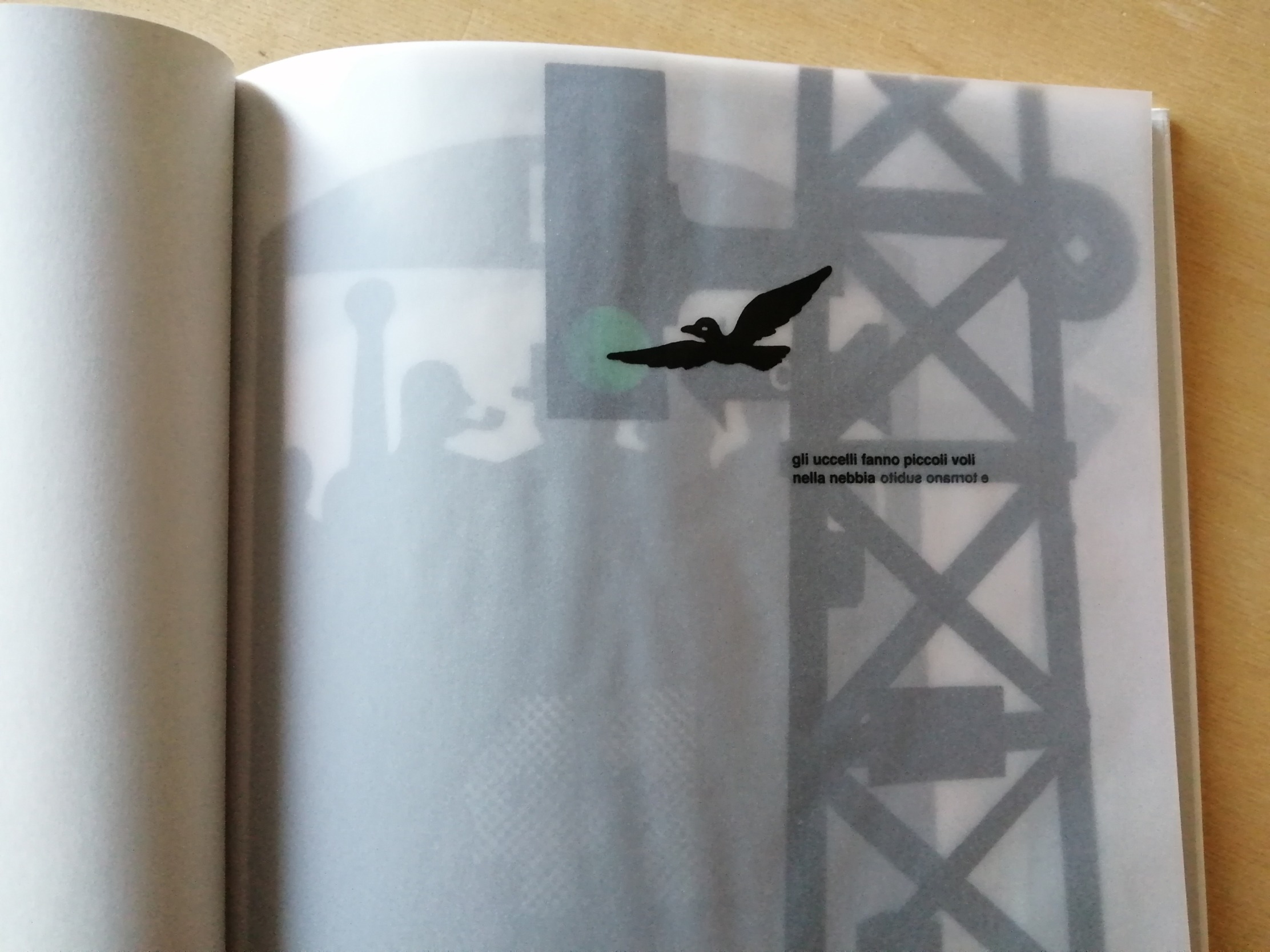

物の消えたデザインスタジオ
ところが、現代のデザインスタジオの多くからは、かつてのスタジオを埋め尽くしていた物たちが、職人の工房との親近性とともにきれいさっぱり姿を消している。大概の場合、工房と言うよりはオフィスという言葉が相応しいきれいさっぱりとした空間の中で、デスクの上のコンピュータのモニターと付箋紙を貼付けたホワイトボードがあるだけで、カスティリオーニスタジオに入った者が身体的に実感するあのフィジカルかつ知的な感触はいささかもない。ますます消費文化が狂乱し、物欲が横行する時代だが、逆説的にフィジカル(物質的、身体的)な要素が消えたデザインスタジオは、「物から物が生まれる」場所であることをやめ、デザイナーが頭で考えたことをヴァーチャルなモニター上で図面に描き起すだけの場所になっている。
この変化の直接の理由は二つある。一方でグラフィックやweb designなど、物質的な商品のデザインを手がけない事務所が増えたことが挙げられるかもしれない。これらの職種においては、現在では手描きの要素、プロセスもかなり減って来てほとんどがコンピュータの画面上で処理されるので、物質と対話する必要を覚えないのかもしれない。また他方で、具体的な物や建造物を作るプロダクトデザインや建築のスタジオでも、 『クラフツマン』の著者で社会人類学者のリチャード・セネットの指摘にもあるように、CAD (キャド:Computer Aided Design)を始め、テクノロジーを通して仮想空間内で処理されることが多くなったため、具体的な物質や物、現実の空間と対話しながらの創造プロセスがかなりの度合いで排除されて来たからとも言える2。
だが、デザインスタジオからの物たちの消滅の背後では、さらに重大なことが起っている。わずか数十年と言う歳月の中で、社会におけるデザインの対象やメソッドが大きく変容したというだけでなく、今や世界と人間の関係の変化が決定的な局面を迎えているのである。哲学者のビョンチョル・ハンは、この局面について「我々は物の時代から、物ならぬものの時代へという過渡期にある」3 と述べている。ハンの言う「物ならぬもの」とは、非物質的な「情報」のことであり、その「情報の塊が現実の前に立ちはだかって、現実を織りなしていた物たちを[どこかに]追いやって」4 しまい、今や「情報が現実ということになって」5 来ているのだ。「我々の棲む環境は、もはや大地と空ではなく、グーグルアースとクラウドになっている」6 と言うハンの言葉は挑発的だが、もはや世界は、かつてハイデガーが想定していた人間的な実存(現存在:Dasein)が手を介してつながりえた、リアルな物からなる世界ではなくなりつつあるのだ7。しっかりした存在感のある物から構成された、我々がかつて「現実」と呼んでいたリアルな環境と人間がまともに触れ合い、交信しながら創造力を働かす場が明らかに消滅しつつある。もはや我々が物の世界に生々しく手を突っ込んで関われる時代が終わろうとしているのだが、何よりも、つくり手と呼ばれる人たちが率先して物に触れる手を差し控えるようになってしまっているのだ。
リアルな世界から遠ざかった人間
人間と物とのつながりの喪失は、二〇世紀における人間と現実世界の距離の劇的な変化の最終章と言えるかもしれない。よく言われるように1914年頃以降具象から決定的に抜け出したモンドリアンの作品に代表される、現実世界をモデルに描くことを拒否した「無対象」の抽象芸術の本質は、実は平面の幾何学的な構成よりも画家たちの眼が(リアルなディテールが一切見えなくなるくらい)世界から無限大の距離に遠ざかったことにあったのだが、これは、二〇世紀の間に人類の文明(技術も芸術も)が、現実との距離を無限大に拡げていく歴史を予言する出来事であった。宇宙船が大気圏を突破する遥か以前に芸術家の眼は大地から遥か彼方の上空に遠のいていたのである。


右:『クワッド』(1981年) 演出:多木陽介(1997年):個人の特徴的ディテールを消すべく頭からつま先まで覆う衣装および辺と対角線上をひたすら反復的に歩くという行動の単純化においてベケットは、抽象芸術と言う形式をクリティカルに使いながら、人間や文化がリアルな世界から危険なほど遠のいたことを描いている。衣装の色に白と三原色を選んだことにも抽象の代表作家モンドリアンへの明らかな暗示があると思われる。主題のなかにある危機的な「標高」の意識を表現するためには、この写真にみる筆者による演出よりももっと思い切り高い視点から撮影した方がベケットのヴィジョンを効果的に描き出していただろう。
しかし、芸術や文化に従事する人間も、ひたすら新しい方法を探求したり技術の進歩に明け暮れる一方で、自分たちが人間性からも自然からも取り返しのつかない距離に遠ざかりつつあることに長いこと気づかなかった。目に見える何かを描くと言う具象の限界を超えた抽象芸術をそのような危機的視点で批評する者はいなかったし、まだ誰もが技術の発展に期待を寄せていた。だが、二〇世紀の終盤になると、現実世界から遠ざかり、かなり危険な「標高」にまで登り詰めた文明の危機的な状況そのものを精確に捉えた芸術作品が登場する。その一つが二〇世紀で最も重要な劇作家の一人であるサミュエル・ベケットによる映像作品『クワッド』(1981年)である。これは、モンドリアン的な原色(白、青、赤、黄)の衣装で全身を覆い、しっかり前傾姿勢のパフォーマーが四人、正方形(クワッド)のエリアの辺と対角線上をかなりの速度で反復的に歩き続ける姿(まるで資本主義のルーティンに呑み込まれた人類)を、高い視点(文明がリアルな世界から乖離した果てに辿り着いた危険な「標高」を暗示する)から見下ろすように撮った作品である。
また、映画監督ヴィム・ヴェンダースと作家のペーター・ハントケは、リアルな生から大きく遠ざかった人類の姿を描くために、『ベルリン天使の詩』(1987年)という予言的映画作品の主人公として物や面倒くさい感情が織りなす人間的な現実から(永遠な生命という)絶対的な距離にいる天使を選び、その天使が自分と世界との縮めようのない距離感に我慢出来なくなり、自分の永遠の生を放棄して地上界に飛び降りるという物語を描いた。

これらはどちらも、技術進歩に眼が眩んで具体的な現実世界を大事にすることを忘れてしまった(その意味で限りになく天使に似てしまった)人類に対して歴史自身が鳴らす警鐘のような作品だったが、今世紀になってから人類と具体的な世界の間の距離はますます広がり、物の存在感の希薄化はまさにその過程で一気に進んだ。再びハンの言葉を借りるならば、「産業革命は、自然と手工業からだけは遠ざかったものの、物の世界を強固なものとし、また拡大したが、デジタル化は、その反対に、物のパラダイムに終止符を打つことになった。」8 コンピュータ文明の普及(世界のデジタル化)とともに、認識の上でも実践の上でも、人類はますます現実の具体的環境から遠ざかり、メディア上で環境問題が叫ばれるのとは裏腹に、ますます人類の視野から自然環境は遠のいているし9、自分たちの手を具体的な世界の物や物質の間に突っ込んで物を作るという経験がもはや社会の中から完全に抹消されようとしている。人間はもはや手を通して物の構成する世界につながることをやめ、ただ情報を交換することにおいてのみ存在しているようにさえ見える。
世界的写真家のセバスチャオ・サルガドが1993年に発表した『労働者』(Workers 伊語の題名は『人間の手』La mano dell’uomo)という大作の写真集は、世界中の農業、漁業、手工業、重工業に従事する労働者の姿をかなりナラティブな形で写し取っているが、イタリア語版の題名『人間の手』が象徴的に語るように、まさに汗だくになって手を物質や環境の中に突っ込んで仕事をしていた人々の姿が消えつつある、その歴史的変化をひしひしと感じながら、サルガドは、こうした仕事によってリアルな世界を形成する人々が本当に姿を消す前に記録しておこうとしたのである。あれから約三十年の歳月が経った今、サルガドの写したような、世界を造作する「人間の手」が本当に地球上から消えようとしている事態に我々は直面しているのである。



手を去勢された人類の「おたく」化
ハンによれば、そんな時代に「手」を去勢され「手なし」になった人類がなお出来ることと言えば、与えられた選択肢から選ぶために(摩擦も抵抗もない)すべすべの画面上で「指」10 を滑らせることだけである。ごつごつと重みも抵抗感もある物の世界に手をつっこみ、かき回し、それらと対話する手の繊細な身振りを忘れ、本当に主体的に行動し、創造するホモ・ファーベルであることを放棄してゲームの局面に応じてボタンを押し分けるだけのホモ・ルーデンスになりつつあると言うのだ。真の自主的な生産性とか創造性などからほど遠いゲーマーと言うか、(これはハンの使う概念ではないが)「おたく」的な存在になりつつあると言っても良い。
ハンは、スマホのタッチスクリーンやジェフ・クーンズのバルーンのような彫刻の表面のように、多くの物たちが限りなくすべすべになって手触りや存在感を喪失し行く傾向に注目し、それが、世界全体がある手応え/抵抗感のある固さを失い、すべてが抵抗感なくスルーな状態(それをハンは「透明社会」と呼ぶ)になりつつあることの徴候だと言う11。この「手応え/抵抗感」のないスルーな状態は、フィジカルなレベルだけでなく、精神的なレベルでも生起している。フィジカル(物質的、身体的)な世界の変化とともに、倫理や人間らしい面倒臭さから来る「手応え/抵抗感」(その部分は全てアルゴリズムに任せてしまう)も失われつつあるというのだ。
こうした「透明社会」にいる人間たちは、与えられた選択肢の中から選んだ情報を交換することにおいてのみ存在するようになる訳だが、ヴェンダースの天使や「おたく」がそうであるように、その情報交換(つまりコミュニケーション)においても、痛みや温かみや感動など、身体的精神的に深い手応えのあるものは避けられるから、「手応え/抵抗感」から来る他者の存在をしっかり認識出来ず、ヴァーチャルなネットワークが浸透すればするほど、逆に個々の人間は限りなくエゴイスティックに孤立した存在になっていく。資本主義が人と人の間のあらゆる絆とともに共同体を寸断した後の風景に残るのは、「おたく」化した人間たちだけなのかもしれないが、奇しくもサルガドの『労働者』と同じ年に発表された、ジャン=ジャック・ベネックス監督の秀逸なドキュメンタリー映画『おたく – 仮想帝国の息子たち』が見事に描いたように、まだ若かった日本のゲーム産業が1980年代以降に「おたく」を自らの栄養源として世界的な急成長を遂げた経緯からも、人類の「おたく」化が、高度に発達した資本主義と深い関係にあることは間違いない。こうしたすべての現象が資本主義の圧力下で起っているわけだが、その中で、他者を認められない「おたく」人間たちからは、人間的な感情や善悪の判断(倫理)もするりと抜け落ちて行く。「[世界の]デジタル化とは、人間的なものの廃棄に向けた一貫性のある行程」12 なのである。
暗黙知と明示知の分離
人間とその社会に起きつつあるこの歴史的な変容をここでは特に、近代化の様々な局面で観察出来る人間の知性/創造力の変化として捉えて行きたい。これは、歴史を知性/創造力の歴史として捉える試みである。
ここで注目するその一つ目は、機械化が進むなかで起った、設計する人と実際に製作する人の分離である。ラスキンが語っていた中世の石工が全体的な図面を持たずむしろ現場の知恵や裁量でカテドラルを建造する主体であった時代とは一変して、一九世紀後半に青焼きの設計図が本格的に導入されるようになると13、物や建物のアイデアは実際に作られる前に概念的に完成され、現場はそれを出来るだけ正確に実現する過程ということになった。こうなると現場の職人はもはや本当に主体性をもって自ら判断する創造者というよりも、任された業務を精確に遂行するだけの者(工員)になっていく。ギュンター・アンダースがナチの戦犯達の間に見た、判断力を放棄した単なる遂行者としての新しい人類の形式もこの辺りに根をもっていたことになる。そしてそもそも産業社会とはそういうものだが、誰かが頭で構想したものを他の人々の手が実現すると言う形で、製造業における頭と手が切り離されることになったのだ。ただ、一九世紀後半の時点で変革が完全に達成されたというよりは、その時点から徐々にこの頭と手の分離、そしてそれに続く手の去勢が現在に至るまで加速的に進んでいると言う方が正しいだろう。サルガドの写真が証言していたように、二〇世紀の工場には、まだそれでも何らかの主体性を自らの手の中に残して働く労働者が残っていたのである。
この頭と手の分離だが、ハンガリー出身の物理化学者・社会科学者・科学哲学者のマイケル・ポランニーの用語を使えば、人間の暗黙知的技能と明示知的な認識力の分解と言うことになる。「暗黙知」(tacit knowledge)とは、経験的に知ってはいるが言語化しにくい知識や技能のことで、典型的な例としては、名医の診断とか、人の顔を見分ける能力や、料理人、職人、音楽家、運動選手などの身体と感覚にしみ込んだ技能などがこれにあたり、その多くは情報や実践が反復と慣習化によって本能的に出来るようになったものである。一方、「明示知」(ないし「形式知」explicit knowledge)とは、これと対をなす概念で、レシピのように言語化され、誰とでも共有可能な状態の知識、また、経験を俯瞰的に判断する客観的な認識力を指している。


近代社会が進めたこの暗黙知と明示知の分離とそれに続く暗黙知の社会的な抑圧(去勢)こそは、人間の包括的な知性の豊かさを破壊した本源だと言ってもいい。なぜなら、「より高度な技術の段階では、暗黙知と自覚的な認識[明示知]の間に絶え間ない相互作用が」14 あるべきだからである。そして二種類の知の分離は、大きく分けて二つの形で進む。一つは、労働、そして日常生活における便利さという口実の下で急進するテクノロジーの導入による暗黙知の大幅な去勢化。もう一つは、伝統および先進の技術者がひたすら技術の洗練、進歩に明け暮れる陰で、自分たちの職能を客観視する明示知的な認識力がしばしば 機能不全に陥ってしまうからである。
一つ目の暗黙知の去勢化だが、上で触れた製造業に限らず、現在、あらゆる分野の職種で進んでいる。例えば、各種サービスに携わる施設(役所、病院、スーパーマーケット他)においても同様で、暗黙知の部分を代行するテクノロジーの導入とともに、現場にいない管理職が合理的な視点から決めたプログラムやシステムが現場の人間が経験から習得した知識や勘、技術や調整能力と衝突し、多くの場合、それを抑圧する方向に進んでいるのが現状である。さらに、労働の場に限らず、日常生活においても、我々が日々の経験や感覚が養った知や能力が判断し、管理していた部分が、どんどん機械やテクノロジー(アルゴリズム)に代行されるようになり、人間の手と五感はあらゆる実践を放棄して、ボタンかタッチスクリーンを指先で操作して情報を取得することに甘んじ、例えば、賞味期限についても、自分の感覚(触覚、嗅覚など)に頼ることなく、食品に付された表示(明示知)に従うだけで判断するようになっている。こうした明示知的な知識には、ウィキペディアの情報と同じく、詳細な生の経験がすっかり欠けているにも拘らず。
一方、伝統芸術(工芸、芸能)の世界も現代においては同じように暗黙知と明示知の分離を経験している。こちらの場合、上記のような社会の近代化された領域とは反対に、技術至上主義の下、技術や芸(つまり暗黙知)の部分は極端に洗練されるが、そこに意識が集中し過ぎるせいか、逆に自分たちの創造行為が置かれている歴史的状況を俯瞰的に把握するための客観的認識力が欠落し、そのため現代社会において生きぬくための知性/創造力の力強さを失うことになる。これは陶芸のような伝統工芸においても能楽のような伝統芸能においても共通に見られる問題である。
そしてさらに興味深いことに、一件逆説的に聞こえるかもしれないが、明示知の欠落と言う点においては、現代の先進技術者の立場も伝統芸術家たちのそれと近似しており(第連載第三回参照のこと)、ひたすら技術的な進歩を目指す技術者たちは、自分たちの探求成果がどのような影響を世界に及ぼすかという点について、客観的な認識に欠けていることが多い。しかも、そのような状態にある知性/創造力は、自分たちの文明の環境、社会、精神にとり極めて危険な状況をもたらす可能性を孕んでいる。マンハッタン計画を指揮し原爆を生み出したが後に水爆に反対して公職を追われたオッペンハイマーがこんな告白をしている。「技術的にすごい何かを見つけたら、前進と実行あるのみ。その目的については、技術的に成功を収めてから議論すればよい。原子爆弾を作った時はそんな調子だった。」15 彼ら科学的な作業に従事する技術者にはひたすら進歩という意識しかないことが多いが、既に本連載の第三回で詳述したように、実は彼らは、一見全く無縁に見える伝統芸術家たちと極めて似通った精神状態にあるのである。
進歩と退行のエネルギーの葛藤
近代化された労働や生活の場面における暗黙知的技能の全般的な去勢と伝統芸術および先進技術を担当する技術の専門家たちにおける自らの職能の歴史的意義についての客観的(明示知的)認識の欠落のどちらにおいても、暗黙知と明示知が包括的に豊かな知性/創造力を形成することが阻害されているわけだが、こうした状況はなぜ生じたのか。ここで筆者には実証的に論証する準備はないが、そんな実証主義的な歴史家よりもはるかに歴史の機微を見抜いていたヴァルター・ベンヤミンの遺稿「歴史の概念について」(1940)の中の有名な断章IXのイメージに助けを借りてみると、現代の我々の知性/創造力の風化が、文字通りある暴風の下で起っていたことが見えて来る。「進歩」と言う暴風の下で。
「新しい天使」と題されたクレーの絵がある。それにはひとりの天使が描かれていて、この天使は、じっと見つめている何かから、いままさに遠ざかろうとしているかに見える。その眼は大きく見開かれ、口はあき、そして翼は拡げられている。歴史の天使はこのような姿をしているにちがいない。彼は顔を過去の方に向けている。私たちの眼には出来事の連鎖が立ち現れてくるところに、彼はただひとつ、破局だけを見るのだ。その破局は、ひっきりなしに瓦礫の上に瓦礫を積み重ねて、それを彼の足元に投げつけている。きっと彼は、なろうことならそこにとどまり、死者たちを目覚めさせ、破壊されたものを寄せ集めて繋ぎ合わせたいのだろう。ところが楽園から嵐が吹き付けていて、それが彼の翼にはらまれ、あまりの激しさに天使はもはや翼を閉じることができない。この嵐が彼を、背中を向けている未来の方へ引き留めがたく押し流してゆき、その間にも彼の眼前では、瓦礫の山が積み上がって天にも届かんばかりである。私たちが進歩と呼んでいるもの、それがこの嵐なのだ。」16

この断章については、マルクスの唯物史観をはじめ近代思想史における歴史観や進歩の概念についての系譜との比較を通してベンヤミンの歴史観の位置づけが論じられるのが通常だが、ここではそれよりもベンヤミンが詩的な視線を通して、現実の表層下に流れる歴史のエネルギー(それも一つの創造的エネルギーと捉えられる)を如何に見事な比喩(Sturm:暴風、嵐)で捉えていたかを確認出来ればいいと思う。産業革命以降の近代、特に二〇世紀初頭から、ベンヤミンの描写する「暴風」へと急激に成長した「進歩」のエネルギー(我々を前へ、前へと推し進めんとするエネルギー)が歴史と言う創造力を動かす圧倒的な主力となり、機械化と資本主義の発展とともに諸前衛芸術運動のそれぞれがこのエネルギーを体現した。欧州では、その旗手としてイタリアの未来派が一早く機械賛美と速度への愛を力強く謳いあげ(未来派宣言は1909年)、キュビスム、ダダ、ロシア構成主義などの前衛運動の乱立がモダニズムを引っ張って行く訳だが、彼らはいずれも「進歩」の暴風に突き動かされるように荒々しく既存の思考や論理を壊して新しい論理や秩序を作ろうとし、未来派宣言から十年後の1919年には最初のモダンデザインの学校バウハウスも開設された。「進歩」の暴風に押された社会全体がそれまでにない前のめりの姿勢で駆け出していたのである。ベンヤミンのテクストが書かれた1940年の欧州を席巻していた戦争もその究極的な表現とさえ言える。
こうして、これらの運動が強力な「進歩」のエネルギーを発散し続けるなかで、かつて人類の知を支えていた暗黙知と明示知の融合体にも亀裂が生じて来たのである。機械やテクノロジーの発展の下での暗黙知の去勢は当然な流れだが、同時に、ひたすら技術を洗練させる(その分明示知的な客観的視野に欠ける)現代の伝統芸術家の目指す芸術至上主義的な方向性も、実は、先端技術産業のそれと同じく、過剰な「進歩」のエネルギーがもたらした現象と見なすことが出来るだろう。
だが同時に、「進歩」の概念が明確になって来た啓蒙時代(一八世紀)から現在までの間に、技術の進歩、機械化、画一的な工業化などの「進歩」的な現象がどんどん強化されていく中で、これとは正反対のベクトルを発揮する人々も少なからず登場していた。その一人目として『百科全書』の作者の一人であるフランスの哲学者のドゥニ・ディドロ(1713-1784)を挙げていいだろう。セネットも指摘するように、「進歩」はディドロらが啓蒙運動へ向かうのを支えたエネルギーでもあったが、にも拘らずディドロは、逆に手工業や肉体労働を重視し、機械には出来ない不整合さ、不完全さ、個性などを大事にし、フランス中の一流の労働者を取材しては、彼らの暗黙知的技能を評価しつつも、その上でそこに明示知的な解説を与えることで、彼らの知性/創造力をさらに包括的なものとして復元しようとしていた。
一九世紀のイギリスには、ジョン・ラスキン(1819-1900)、ウィリアム・モリス(1834-1896)という二人がいた。一九世紀のイギリスを代表する美術評論家のラスキンは、時代の先端を行く画家ターナーを擁護する一方で、機械支配の時代を動かす強大な進歩のエネルギーに対して強烈に反発した人だった。物が溢れる資本主義の波に警鐘を鳴らし、機械化の波の中で軽視され始めた五感の力の回復を叫び、それを重視する職人の身体的労働の価値を擁護し、職人の社会的尊敬の回復を目指した。1850年代中盤にはロンドンのレッド・ライオン・スクエアーの一軒家に労働者大学(Working Men’s College)を創設し、ここでも職人たち(壁紙貼り職人、習字の師範、室内装飾業者、石工、煉瓦工、ガラス吹き、陶工など)に機械化時代の危機的状況を自覚させるなど、暗黙知的技能に長ける彼らに自らの職業の歴史的現状を意識させるための明示知的教育(クラフツマンの覚醒=自意識化)を施した。彼にとってのクラフツマンシップ(職人の職能)の概念には、明らかに手だけでなく頭も使う仕事という意味が込められていた。彼の場合も明らかにアンチモダニスト的な意識で暗黙知と明示知の分解を察知し、それらの再統合を図っていたのである。
また、詩人、デザイナー、思想家であったウィリアム・モリスのアーツ&クラフツ運動 の場合にも、同じく機械技術至上になりゆく時代にあって、当時の工業製品の醜さを批判して、はっきり生や人間性を擁護し、中世の工房の仕事ぶりを模範にしていた。
二〇世紀に入ってからだが、先述のバウハウスにおいても、画家で教育家であったヨハネス・イッテン(1888-1967)らが中心にいた開校当初には、中世の工房を理想として実践的工芸家の養成を目指すなど、明らかに反「進歩」的なエネルギーを孕んだ学校でもあったし、アンドレア・ボッコが指摘するように、建築家バーナード・ルドフスキー(1905 – 1988)の「近代性」へのアプローチの本質も、いわゆる合理主義やモダニズムの特徴とされる「進歩」的なものとは異なり、過去を捨てて先へ行くのではなく、「古代文明や民衆文化に見られる建設と居住の伝統の中にオリジナルの諸原理を読み取る」17 ことにあったし、またこのアンチモダニスト的な姿勢において彼が孤立した存在ではなく、同様の傾向を共有する建築家たちが(彼の前にも後にも)いたことも分っている18。彼らはいずれも「進歩」のベクトルが指し示す、機械化、高速化、合理化、抽象化という「前へ、前へ」という方向性ではなく、より環境や人間的なものを擁護すべく、過去や歴史の生み出した知性を大事にしていた。もちろん、このアンチモダニスト的なエネルギーは建築やデザインの世界だけで観察されたものではなく、文学や舞台芸術でも発揮されており、例えば日本の暗黒舞踏などにもその典型的な例を見ることが出来る。
これらの人々の活動を通して、先へ行くとか、速度を上げることよりも、ちょっと立ち止まって、反省的に考え、それによって生や創造の根源へと降りて行くことを促すようなベクトルをもったエネルギーが絶えず歴史の中には姿を現していた。ベンヤミンの歴史の天使が留まって死者を助け起こしたいと思う気持ちも同じエネルギーである。ここでは、このエネルギーを「進歩」に対して「退行」と呼んでおこう。「退行」という言葉は、もともと心理学からとったもので、発達のより前段階的な状態へ回帰することを指す言葉だが、本書ではそれを創造的エネルギーのひとつのあり方を指すものとして使って行く。言葉の響きは悪いが、「進歩」が文明のアクセルだとすると、「退行」は文明の暴走を防ぐ、良い意味でのブレーキであり、この二つのエネルギーの葛藤が近代の歴史を創って来たとも言える。両者の混ざり方、割合は、地域ごと時代ごとに様々だが、二〇世紀になって「進歩」が暴風化して以来、特に二一世紀を迎える現在の先進諸国においては、この両者のバランスは完全に崩れ、なかでも高度に資本主義の発達した東京のような都市部では、「進歩」のエネルギーが溢れ返る中で「退行」のエネルギーはほぼ完全に抑圧されている。歴史の創造力を支えるエネルギーが決定的にバランスを喪失している状態、我々はその中に生きているのである。
プロジェッタツィオーネ再考
そんな現代に生きる我々だが、これまで「進歩」一色で来た技術と資本主義の文明の自己破壊的な創造力を修復すべく、それとは根本的に異質な創造力を発揮する人々が今世紀になる頃から様々な分野でようやく目につくようになって来た。彼らは、建築、デザインばかりではなく、町づくり、食、医療、芸術、その他の職能を通して、自然、社会、精神の環境におけるエコロジーを実践しながら、従来の文明の創造力の歪みを修復しようとしてくれている。そして、彼らの活動を観察すると、いずれもが現代世界の主流とは逆に「退行」のエネルギーを多く持っているのだが、とは言え、「進歩」に支えられた近代的な知性を完全に排除することが目標ではない。国際スローフード協会の会長カルロ・ペトリーニがかつて2010年のテッラ・マードレの開会式で述べていたように、これからは、先進の技術と伝統の知性を如何に協調させるかが我々の生存の鍵となるはずである19。
ペトリーニの言葉を我々の文脈に沿って翻訳すると、歴史を日々作って行く創造力のエネルギーが健全な形で機能するには、「進歩」と「退行」のどちらもが必要だということになるが、実は、この二つの相反するエネルギーを絶妙なバランスで兼ね備えた創造者たちが、第二次世界大戦直後のイタリアにまとまって登場していたのである。未来派を輩出しながらもこの頃まで近隣諸国に比べ後進性に特徴付けられていたイタリア社会が背景にあったこともあるだろうが、やはり戦争の経験が大きかったのではないだろうか。戦前の合理主義建築の教えを受けながらも、社会的にも精神的にも多大なカタストローフを生産した「進歩」の強風に押し流されまいと「退行」のエネルギーを己の創造行為の中にしっかりと呼び戻した彼らは、今一度自分たちの生活と文化の根っこを見直し、過去の知性を受け継ぎながら焦土の中から自分たちの社会を再生する道を探したのである。二〇世紀初頭の先輩たちが「進歩」の風に強く背中を押され、『クワッド』のパフォーマーみたいな前傾姿勢で必死に疾走していたのと比べると、彼らは後方(過去)にもしっかり視線を送りながら前(未来)に進む術を心得ていた。孔子の説いた「温故知新」を地で行く人たちが二十世紀半ばのイタリアに少しまとまって登場したのである。そして「温故知新」を通して前近代的な職人に近い物質世界との対話能力を近代的な合理主義的思考に接続出来た彼らは、まだ明らかに「物の時代」の住人でもあり、その分、暗黙知と明示知を再統合させた知性/創造力を実践出来る人々であった。「退行」エネルギーの回復が、彼らに古くて新しい創造力を授けることになったのだ。
この「彼ら」とは、冒頭にも触れた、ブルーノ・ムナーリ(1907-1998)、ピエールジャコモ(1913-1968)とアキッレ(1918-2002)のカスティリオーニ兄弟、エンツォ・マーリ(1932-2020)など、普通イタリアンデザインの父祖とされる巨匠たちに代表される建築家・デザイナーたちのことであるが20、当時、イタリアではまだdesignと言う英語が人口に膾炙していなかったこともあり、本人たちは自分たちの職業のことを「デザイン」ではなく「プロジェッタツィオーネ」(原語のprogettazioneとは、ある複雑さをもつ目標(progetto = プロジェクト)に向けて、それを発案、準備、実現させること 意味する)、またそれを実践する自分たちのことを「デザイナー」ではなく「プロジェッティスタ」(progettista:プロジェッタツィオーネの実践者)と呼んでいたが、「プロジェッタツィオーネ」は、現在使われている「デザイン」とはかなり意味が異なるし、また「プロジェッティスタ」も現代の「デザイナー」の同義語とは言えない。
彼らプロジェッティスタは、まず、その大半が建築家の肩書きを持ち21、現代のデザイナーよりもはるかに豊かな教養と文化、社会、政治、経済など広範な領域に対する批評能力を身に付け、ある領域に専門化することなく22、スプーンから都市まで人間の生活に関わる物すべてを区別なく扱っていた。さらに、現代のデザイナーの多くが基本的にプロジェクトの最終段階にある製品の外観の「スタイリング」だけを担当するのに比べ23、プロジェッティスタたちは、ひとつのプロジェクトのかなり「上流」から関わり始めていたから、その守備範囲は企画から諸段階を経た最終的な完成、場合によっては販売に関する教育に至るまでとかなり幅広く、各段階で多様な専門家と協働しながらプロジェクト全体を統轄する監督のような存在であった。
この時代(戦後から1970年頃まで)のプロジェッティスタたちは、企業の利潤ではなく人間の生活環境の改善を第一の目的とし、創造のあらゆる側面、あらゆる段階に目を配り、人間的、社会的、倫理的な原則を重視したプロセスで作業を実践し、また、最終的な製品の外観だけではなく、プロセス全体の「正しさ/美しさ」によってプロジェクトを評価する能力を備えていた。
しかし、その後二〇世紀後半から終盤にかけて資本主義が果てしなく強大化する中で、本国イタリアでもデザインのあり方は大きく変わり、プロジェッティスタの中の数人が巨匠(ブランド)化される一方で、彼らが実践し、理論化もしていたプロジェッタツィオーネ的な創造行為自体は、完全に主流から外れていく。ラディカル・デザインなどの登場した六〇年代後半から、市場で主役になれる「顔」(消費される記号)を商品に与えることがデザインの主な仕事になっていったのだ24。その流れで現在まで高度に発展した消費文化の中では、ムナーリやカスティリオーニ、マーリというプロジェッティスタの作品すらもカリスマ的な「顔」としてもてはやされるばかりで、それらを生み出した実践としてのプロジェッタツィオーネの思想や方法論が如何に反資本主義的なものであったかなどはとうに忘れられ、現代の有名デザイナーたちとムナーリやカスティリオーニたちが明らかに異なる系譜に属していることも正確に認識されていない。オリジナルな概念としての「プロジェッタツィオーネ」も「プロジェッティスタ」もその意味では、今や「死語」と化している訳だが25、現代世界の環境、社会、精神が直面している極めて危機的な状況とそれをもたらしている現代文明の知性/創造力の状態を観察していると、その状況の解決の糸口として、今こそプロジェッティスタたちの思想と方法論を学び直す必要があると確信しないではいられない26。
控えめな創造力
では、プロジェッティスタたちから学びうるものは何か。「進歩」の暴風圏の中で、人間と物との関係の著しい希薄化とともに暗黙知と明示知とを繋ぐ接合点をも見失った人類の能力は、科学技術の進歩の陰で、劇的な劣化の一路を辿っているわけだが、人間が人間らしい知覚力と創造力と心を取り戻す(それなしには環境問題も考えられない)ためには、まず、「もの言わぬ存在」へと落ちぶれ、誰にもその言葉を読み取ってもらえなくなった物たちの言葉に今一度耳を傾け、そのアルファベットや文法を学び直すところから始める必要があるのではないだろうか。人類の歴史を形成して来た物や物質との密接な関係を回復するために。なぜならば、ハンも言うように、具体的な物たち、そしてそれらが構成するリアルな世界との関係こそが人間の生を癒し、しっかりとした現実に我々を引き止めてくれるからである。
こうして物の言葉を学ぶとともに、人類は自分が唯一の主体(subject)として思い描いたイメージを対象(object、この場合、素材、人、地域社会など)に対して押し付ける形で「作る」のではなく、物とともに空間や人にも耳を傾け、それらの対象と対話をしながら、そこから何かを引き出し、その成長を助けながら「育てる」農夫か庭師のような創造力を取り戻す必要があるだろう。創造力の根本的なパラダイムシフトが求められているのだ。このタイプの創造力にイギリスの社会人類学者ティム・インゴルドは「控えめな」(humble)という形容詞を付けて注目しているが27、この「控えめな創造力」(humble creativity)は、それ自体が物を通して世界と対話する能力であり、また世界と主体的かつ共生的な関係を結びながらその中で生きて行くためのサステイナブルな生存能力の鍵となるものでもあり、これからの世界を生き抜く人類が何より身につけるべき基本ではないかと思われる。そして言うまでもないが、戦後イタリア社会に登場したプロジェッティスタたちは、この「控えめな創造力」の見事な使い手たちであったのである。
- 脚注
- 1. 一六世紀の貴族たちが芸術作品も動物の標本も同一のコレクションとして区別せず収蔵していた部屋のこと。
- 2. リチャード・セネット『クラフツマン – 作ることは考えることである』筑摩書房、2016年、79−88頁。
- 3. Byung-Chul Han, Le non cose – Come abbiamo smesso di vivere il reale, Giulio Einaudi editore, 2022, Torino, p. 6.
- 4. Ibid., p. 72.
- 5. Ibid., p. 71.
- 6. Ibid., p. 6.
- 7. Ibid., p. 9.
- 8. Ibid., p. 8.
- 9. セバスチャオ・サルガドが八年という歳月をかけ、世界中のまだ文明に冒されていない風景と動植物、そして数千年前から自然と協調する生活を保って来た原住民たちだけを撮った壮大なプロジェクト『ジェネシス』(2005-2013)は、人類の視野から抜け落ちていた自然を歴史の主役として力強く連れ戻したと言う意味で、非常に重要な意義をもっている。
- 10. 興味深いことにイタリア語では「デジタル」(digitale)と言う語には本来「指の」という意味がある。語源はラテン語で「指」を意味するdigitusだが、数を数えるのに指を使うことから、英語で数字を意味する言葉digitになり、そこから数量を数字で掲示する「デジタル」という意味が派生した。
- 11. ビョンチョル・ハン著『美の救済』、『透明社会』など。
- 12. Byung-Chul Han, op.cit., 2022, p. 90.
- 13. リチャード・セネット、前掲書、83頁参照のこと。
- 14. 同97頁。
- 15. 同18頁。
- 16. 「歴史の概念について」〔歴史哲学テーゼ〕IX、『ベンヤミン・コレクションI 近代の意味』 所収、筑摩書房、1995年、653頁。
- 17. Andrea Bocco Guarnieri: Bernard Rudofsky: A Humane Deisgner (Springer Verlag, 2003) 邦訳は『バーナード・ルドフスキー – 生活技術のデザイナー』鹿島出版会、多木陽介訳、2021年、46-47頁。
- 18. 同上。
- 19. 多木によるThink the Earth の地球リポートvol. 55 「テッラ・マードレ=母なる大地から始まる新しい世界の動き」(2010年11月29日)を参照のこと(http://www.thinktheearth.net/jp/thinkdaily/report/2010/11/rpt-55.html#section4)
- 20. さらに、これらの巨匠に比べると知名度は低いが、彼らの思想をそのまま受け継ぎ、今なお活躍する、建築家でトリノ工科大学の名誉教授であるジャンフランコ・カヴァリア(1945-)もこの系譜に含めておいてもいいだろう。
- 21. イタリアの場合、デザインのメッカでありながら、長いことデザイン学校やデザイン学科がなく、大半のデザイナーが大学で建築を学んだ建築家であった。その点、日本におけるような建築家とデザイナーの区別がなく、いずれも生活環境を改善するための創造家(プロジェッティスタ)として、建物を作るか、物を作るかだけの違いであった。ブルーノ・ムナーリとエンツォ・マーリの二人は、そう言う中では例外的に芸術家としてキャリアを始めていた。
- 22. 例えばイタリアでは「家具デザイナー」という専門特化した職能のあり方はありえなかった。
- 23. 正確に言うと、この十年ほどは、日本でデザイナーと言う肩書きで仕事をしながらも、その実状はかなりプロジェッティスタと言える人達が特に若手の間で増えているのも事実である。彼らは製品の外観をデザインすることには飽き足らず、より「上流」からプロジェクトに関わり、プロジェクトの全体の方向性をリードするとともに最終的な外観を担当するなど、日本語で言う従来のデザイナーよりもかなり守備範囲が広い。
- 24. ただアメリカでは既に1930年代に明らかに市場のための「顔」をデザインする「スタイリング」が隆盛していた。
- 25. 現代のイタリア語では、「プロジェッタツィオーネ」は、戦後当事者たちが自分たちの職能に対して与えていた特別な意味で使われることはほぼなく、ニュートラルに「プロジェクトを実践すること」「設計すること」と言う意味で使われるのが普通で、「プロジェッティスタ」と言って人々が真っ先に思い浮かべるのは、助成金の申請書を書くプロのことである。
- 26. この確信のもと、筆者は、2015年よりクリエイティブネットワークセンター大阪メビック(大阪市経済戦略局が設置し、公益財団法人大阪産業局が運営するクリエイティブ産業振興施設で、大阪で活動するクリエイター同士やクリエイターと企業等とが“顔の見える関係”を築くためのコミュニティづくり、競争とコラボレーションによる新たなビジネスや価値が生まれる環境づくりに取り組んでいる)その他の希望者のために「移動教室」と称して、現代のイタリアにおいてなおプロジェッタツィオーネの思想と方法を受け継ぐ形で活動をしている様々な分野(デザイン、建築、出版、町づくり、教育など)の人々のもとを訪問して話を聞いたり、ワークショップを受けるツアーを企画している。
- 27. ティム・インゴルド著『メイキング』、左右社、2017年、55頁。邦訳では、この humble という語を「慎ましい」と訳しているが、本連載では一貫して「控えめな」と訳している。
PROFILE
Yosuke Taki
多木 陽介
アーティスト、批評家