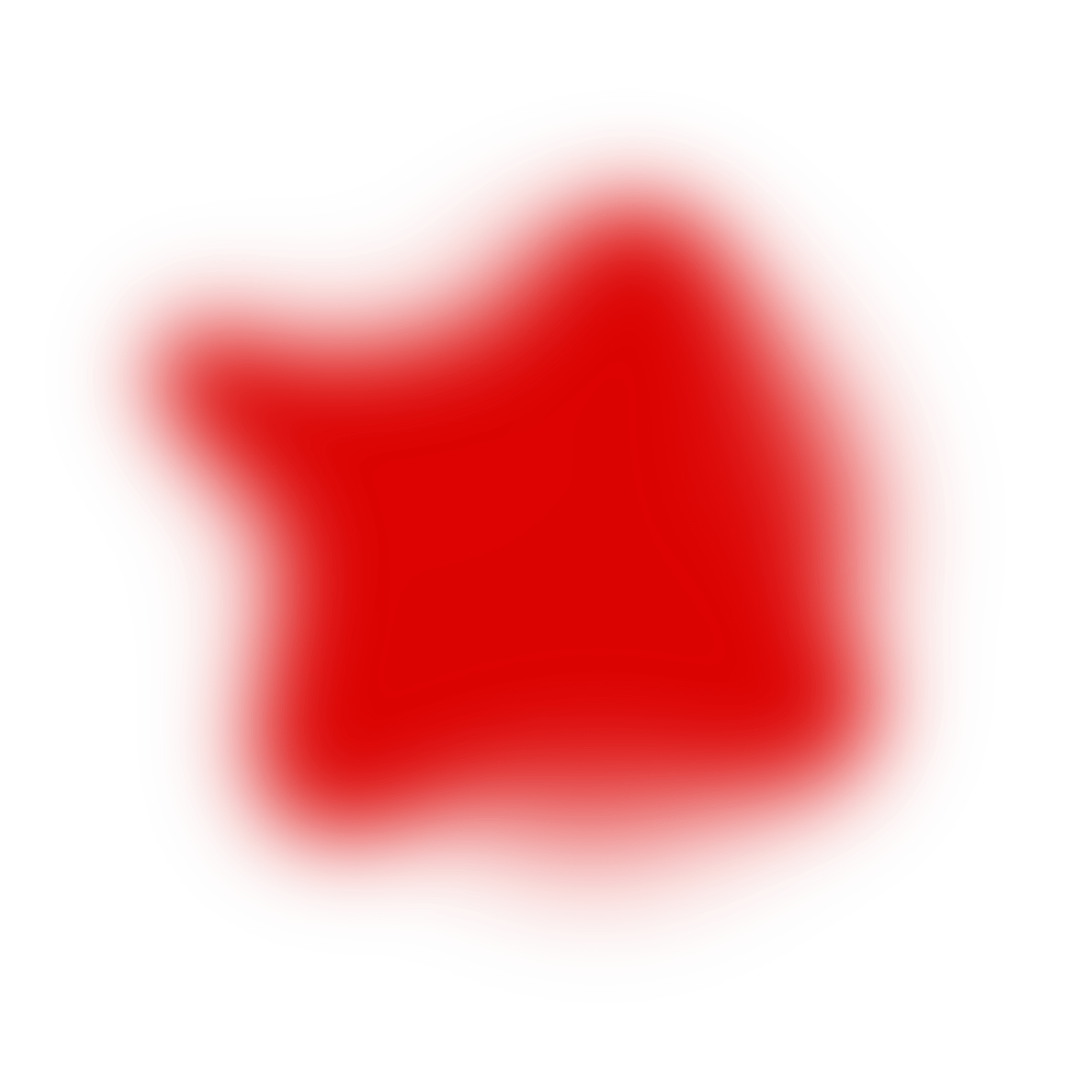サッカーW杯の興奮も覚めやらぬまま、日本の冬の風物詩、駅伝の季節が巡って来ました。元旦には実業団チームの全国大会「ニューイヤー駅伝」、そして1月2日・3日には、関東の有名大学がしのぎを削る「箱根駅伝」が待っています。2001年から2014年にかけて8回ニューイヤー駅伝を制し、当時「21世紀の駅伝王者」と呼ばれていたのが、コニカミノルタです。現在は世代交代を含むチーム変革の過渡期にあり、「世界と戦える」チームづくりを目指してさまざまな施策に取り組んでいます。その一環として、2022年11月、同陸上部の宇賀地コーチと共にウガンダへと10日間の現地視察に赴く機会がありました。宇賀地氏自身、駒澤大学では箱根駅伝優勝、コニカミノルタではニューイヤー駅伝優勝を経験しています。しかし、高校から実業団に至るまで多くのチームが海外出身選手を抱える日本の駅伝界を見回しても、ウガンダ人選手の姿は見当たりません。では、なぜ今あえてウガンダなのか?今回はまずその背景について触れてみたいと思います。
上の写真は、2017年ハンブルク・マラソン準優勝に際してウガンダ国旗を掲げるスティーブン・キプロティチ選手。撮影:西田孝広
長距離・マラソン界におけるアフリカ勢の存在とは
長距離・マラソンと言えば、世界のトップを占めるのは、アフリカ勢。とはいえ、アフリカ全土から有力選手が輩出されているわけではなく、そのほとんどが、ケニアとエチオピアという東アフリカの2国に集中しています。エチオピアといえば、忘れてはならないのが、裸足で金メダルを手にしたローマ大会に続き、1964年の東京オリンピックで史上初の五輪マラソン2連覇を達成したアベベ・ビキラです。その後も、ハイレ・ゲブレシラシエ、ケネニサ・ベケレなど長年にわたって実績を残し、語り継がれる名選手を多く生み出してきました。
一方、ケニア勢が五輪のマラソンで初めて表彰台に立ったのは、意外にも1988 年になってからのことです。その年、ソウル五輪で銀メダルを獲得したのが、瀬古利彦に憧れて19歳でエスビー食品入りしたダグラス・ワキウリでした。1993年には、そのワキウリに憧れて陸上の道を志したエリック・ワイナイナが、当時のコニカ陸上部に入部。1996年アトランタ五輪で銅メダル、2000年シドニー五輪で銀メダルを獲得しています。そして、2008年北京五輪でケニアに悲願の金メダルをもたらしたのが、仙台育英高校、トヨタ自動車九州出身のサムエル・ワンジル。日本でも、「都大路が生んだオリンピック金メダリスト」として讃えられました。こうして振り返ると、あらためて日本がケニア・マラソン界の黎明期に果たした役割の大きさが感じられます。その後、ケニア勢は名物イタリア人コーチ レナート・カノーヴァ氏の貢献などもあり、世界で押しも押されもせぬ地位を確立しました。2021年に開催された2020年東京五輪で、世界記録保持者エリウド・キプチョゲが圧倒的な強さを見せつけて連覇を果たした姿は、まだみなさんの記憶にも新しいことでしょう。
ケニア人選手とウガンダ人選手の共通点
一流長距離・マラソン選手の出身地は、ケニアとエチオピアに集中していますが、国籍に関わらず共通しているのが標高の高いいわゆる「高地」の出身だということです。世界中の多くの選手が高地での合宿をトレーニング・プログラムに組み込むように、高地での生活やトレーニングには酸素運搬能力改善などの効果が期待されることが知られています。かつては、来日して成功するケニア人の多くが、ニャフルル出身のキクユ族でした。ニャフルルは標高2,300mの高地で、キクユ族は同国の多数派民族にあたります。最近でも、日本の駅伝でも大活躍したビダン・カロキ(トヨタ自動車)などが該当し、同郷で地元クラブの先輩でもある「ワンジル選手に憧れて」来日したのだそうです。しかし、世界でさらに圧倒的な実績を残しているのは、「マラソンの聖地(Home of Champions)」と呼ばれるイテン周辺に多いカレンジン族の選手たちで、キプチョゲなどもそうです。近年は、来日する選手にも、この地域・部族出身の選手が増えているようです。

ウガンダ版「マラソンの聖地」が、エルゴン山北嶺の標高1,800mほどの場所にある美しい村カプチョルワです。住民はケニアのカレンジン族と同じくカレンジン群に属するセベイ族。人口約4,700万人のウガンダにあって、36万人ほどの少数民族です。エルゴン山の東側に回るとそこはもうケニア。入国に際しては両国共通の「東アフリカ・ビザ」も取得可能だったりして、ウガンダとケニアはいろいろな意味で「近い」のです。道路整備が進んだ今では、イテンからカプチョルワまでは車で5時間ほどの距離。ウガンダの首都カンパラ近郊のエンベデ空港から移動するよりも、イテン近郊のエルドレッド空港から向かう方が快適だと言われるほどです。
ウガンダ人選手の活躍とウガンダ訪問の経緯
ウガンダ人選手の活躍は今に始まったことではありません。2012年のロンドン五輪ではカプチョルワ出身のスティーブン・キプロティチがケニア勢に先んじてマラソンで金メダルを獲得、翌2013年のモスクワ世界選手権でも見事優勝を果たしました。しかし、当時はまだ「ウガンダ勢」として注目するほどの数ではなく、個人レベルでの活躍だと見なされていました。少し話がそれますが、キプロティチの名字もケニアのカレンジン族の多くの選手同様「キプ(Kip)」という文字で始まるのにお気づきでしょうか?カレンジン語では、生まれた時刻や環境などに応じて名字をつける習慣があり、「キプロティチ」は、「放牧地から牛たちが戻ってくる時間(夕方)に生まれた」ことを表すのだそうです。
ウガンダが一気に世界の長距離界の注目を集めるきっかけとなったのが、近年のジョシュア・チェプテゲイやジェイコブ・キプリモといった選手たちの活躍です。チェプテゲイは、5,000m、10,000mの現世界記録保持者にして、2020年東京五輪5,000m、2019年ドーハ・2022年オレゴン世界選手権10,000mの金メダリスト。キプリモは、2020年東京五輪・2022年オレゴン世界選手権の10,000mで銅メダルを獲得しています。女子では、2019年ドーハ世界選手権 800mでハリマ・ナカーイ、2020年東京五輪3,000m障害でペルース・チェムタイが、世界の頂点に立ちました。

今回、ウガンダ行きの決め手となったのが、2007年に欧米人の陸上関係者として真っ先に現地を訪れて以来、ウガンダ人選手の発掘、育成に尽力してきたオランダ人マネージャー、ユーリ・ファン・デル・フェルデン氏(NNランニングチームを運営するグローバル・スポーツ・コミュニケーション所属)の存在です。キプリモを除く上記全選手を担当するなど、ウガンダ長距離界発展の功労者の1人です。そして、現在同氏は、2021年に開始された宇賀地コーチの海外研修プログラムのメイン講師を務めており、同プログラム立案・実施に協力しているインプレスランニングの代表 柳原元氏にとっては、同時期に世界陸連の公認代理人資格を取得した代理人仲間でもあります。さらに、筆者にとっても、国内外のマラソン大会を通じて長年交流のある旧知の友人です。そんな縁もあり、今回カプチョルワでの密度の濃い現地視察が実現したのです。

そのファン・デル・フェルデン氏が、コニカミノルタ陸上部の招聘で、2023年のニューイヤー駅伝、箱根駅伝視察のため間もなく来日します。次回は、彼の目から見た日本の駅伝の印象や日本人選手が世界と戦うための提言、続く第3回目は、ケニアや日本との違い、宇賀地コーチの考察を含むウガンダ現地視察レポ~トを、陸上界における今後の日本とウガンダの交流の可能性ついても展望しながら記す予定です。ぜひご期待ください。
COLUMN
TEXT & EDIT: Takahiro Nishida