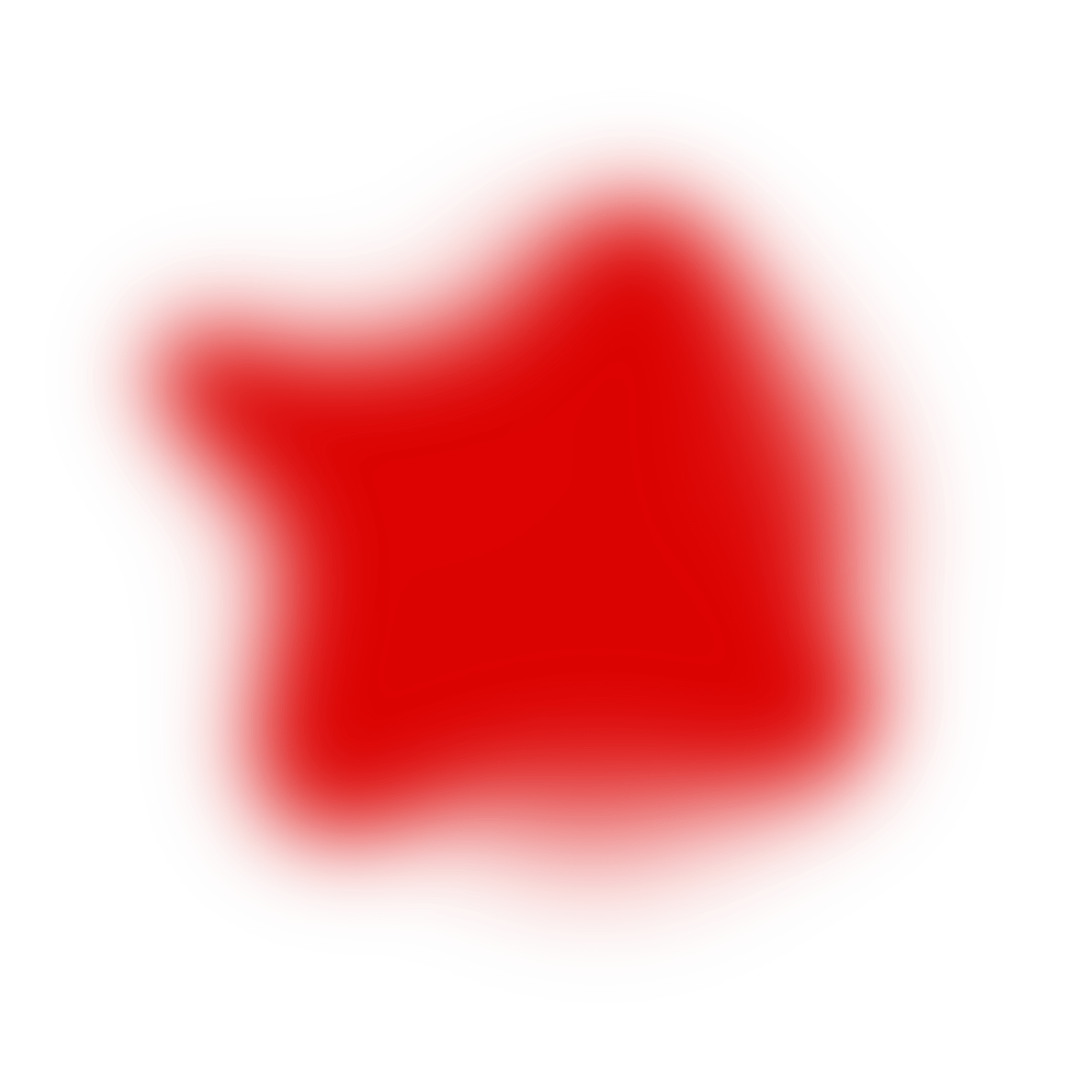PAGE.2
PROFILE
TRANSCREATION®Labのインタビュー第一回は、どうしても市耒健太郎さんにお願いしたかった。Labの編集長である私の会社員時代の先輩という存在をはるかに超えて、上野のちいさな蕎麦屋でもニューヨーク・ブルックリンの寂れたビルの屋上でも、会うたびに、そして何年も会っていなくても深遠なインスピレーションを授け続けてくれる人である。市耒さんに会うと、壮大なのに繊細で慈悲深くて、まるで大自然に包まれているかのような不思議な感覚になる。市耒さんの、その霊性に満ちた創造力がどこからやって来るのか、お聞きしました。
Interview by Yasuhiko Kozuka
Text by Yuto Miyamoto
Photographs by Keisuke Nishijima
「人間ならざるものたちの言葉」に耳を澄ませること
── 市耒さんは常に非言語の体験とか身体性を大事にされていますが、それと同時に、市耒さんは言葉の表現がものすごい明瞭で、ほかの人が使わない表現をされているようにも思っています。「言葉を信じていない」とも話されていた市耒さんの、言葉との付き合い方をあえてお伺いしてみたいです。
言葉ねぇ……言葉を話すことで、自分がリミットされないようにしたいとは常に思ってます。ぼくは「エコ・エゴ・エロ」の3つが大事だと思っていて。エゴっていうのは個としての最適解。エロっていうのは生命とか細胞レベルでの最適解。そしてエコっていうのは、共同体のための最適解。これら3つが連鎖して社会ができていると思うんです。最近はやたらエコを謳っている企業が多いけど、エコだけ言ってる人って、ぼくはちょっと信じられないんです。やっぱりエゴとかエロがないと、鮮やかにドライブしない。
そのときに、もしエゴを微分したものがエロだったら、そしてエゴを積分したものがエコだとしたら、言葉はどう変わっていくだろう? ひとりの人間って、タイムライン上で80年くらいぶらぶらとさまようわけじゃない。そのときに、まず初めの言葉を持ってるのはエゴ=個人でしょ。今日のインタビューでも、ぼくらは1対1で言葉をやりとりしなくちゃいけない。細胞レベルでは言葉を持っていない。でも細胞は、微分的に何かを連鎖的に峻別してると思うんです。そしてこのインタビューが記事になったりすると、それが他者や社会に対しても影響を与えていく。エロやエコまで包含したら、言葉のインパクトとか可能性も変わってくると思うんです。
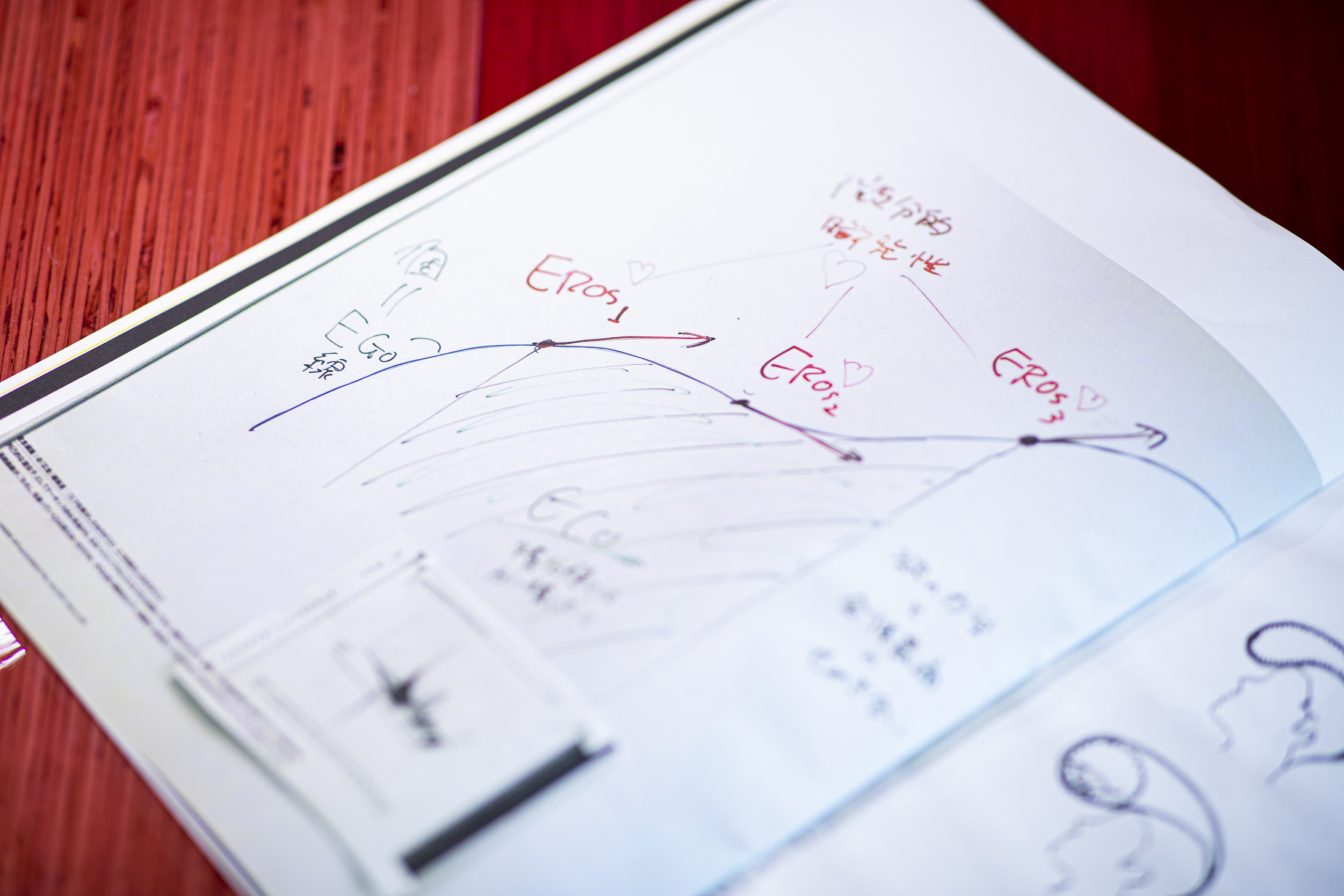
例えば都市計画をつくるとき、「エコロジカルでサステイナブルで人にやさしい」とかいわれて、大体似たような感じになるじゃないですか。公園とか植栽のつくりが。だけどぼくらのチームでは、もし「菌主体の都市」をつくったらどうなるんだろう?みたいなことをシミュレーションするわけです。例えばこれ(下画像)は、アスペルギルス・オリゼ(麹菌)を主体に、菌が街全体をはびこりながら、菌のアニミズムを愛でながら人間が生活するような都市をビジュアライズしたものですが、人=エゴではなく細胞=エロレベルでの都市計画だから、ぼくらが知っている都市とはまったく違うものになる。
人間の身体には37兆もの細胞がありますが、腸の中にはそれよりもはるかに多い1,000兆の微生物がいる。リチャード・ドーキンスは、人間は利己的な遺伝子のビークルにすぎないって言ったけど、人間の全細胞の30倍近くの生命がここに生きていることを考えれば、ぼくらは微生物のビークルだとも言えるわけじゃないですか。だとしたら、人間が言葉を使って「個」という単位で都市をつくるんじゃなくて、微生物との共生という視点で都市をつくることも必要なんじゃないか。そうして生まれたのが、この菌至上主義の都市のアイデアなんです。
もしかしたらこうしたアイデアは、子どものときに水中眼鏡をかけて川を下りながら見てたような景色や感じた匂い、自然のもつ「秩序あるカオス」への憧憬から来ているのかもしれません。人間の世界だと、秩序は秩序でつまんないし、カオスはカオスで最悪だし。でも、地球の自然のなかにはエコエゴエロが溶け合った「美しいカオス」みたいなものがあって。そうしたカオスを前に、あくまで言語はすべてを均一化しようとする。再生しきれていないのにわかったふりをする。AIの時代には、それがもっと記号の上で最適化されていってしまいます。ぼくは、そこを1回リセットして、微視的=エロな視点と巨視的=エコな視点を投げ込んでいきたいのかもしれない。

── まさにいまのお話が、今回のインタビューで聞きたかったコアだったなと思っています。なぜ『Transcreation Lab』として市耒さんの話をいちばん最初に聞きたいと思ったかというと、「言語による最適化」のつまらなさみたいなところに問題意識を持っているからなんです。言語はmorphの仕事のコアですけど、その言語によってつまらなくなりたくない、という思いが強烈にある。今回お話いただいた非言語の体験とか、自然のカオスとか、そうした言語の可能性を拡張するためのヒントを何か掴みたいと思って、市耒さんのお話を聞きたかったんです。
AIによって言葉がますます均一化していくことに対して危機感があるとおっしゃっていましたが、これからの時代に市耒さんは、人間と言葉の付き合い方、人間にとっての言葉がどうなっていくといいと想像されていますか?
まあ、とにかくユーモアが圧倒的に足りないよね。この時代、いろんな意味でそうだと思うけど、やっぱり同調圧力が強いから。人と違うことを言うとか、空気を読まないことを言うことに対するつるし上げが強くて、なかなか派手なユーモアが生まれてこない。ユーモアってある種の趣向的な実験でもあるわけだけど、それを許容する社会が必要だし、とくにいま、この0.1ミクロンの見えないものに世界が覆われている大変なときこそ、やっぱユーモアの力が必要だと思う。ユーモアによって言葉が思考の桁を外すことができるわけで、常識のタガも外せるしね。
「多様性」とか「SDGs」とかカッコいい言葉を使わなくとも、さっき言ったように小学生のときにおもしろかったやつがおもしろいままバーンと弾けられるような、天才の素材がそのまんまドクドク&ジューシーに弾けられるような世の中になったらいいですよね。
── 同調圧力が強い日本社会では、それはとくに大きな課題ともいえるかもしれません。一方で、日本ならではの創造性、日本だからこそ発揮できるクリエーションの可能性があるとしたら、それはどんなものだとお考えですか?
日本の未来といえば、それはもう「アニミズム」ですよね。宇宙がもつ森羅万象性に身を委ねて、八百万に神が宿ることを感じれる文化。人間と自然とテックを等価に混ぜて、それを愛でながら新しい社会アーキテクチャをつくれるということ。そうした思想の宿った文化を、日本は古来からアニミズムとして継承してきていますし、ぼくはそれを現代的に解釈し直せば、新しい文明創造への兆しになると考えています。
この違いは、例えば教会と神社の建ぺい率(敷地面積に対する建築面積の割合)を見れば一目瞭然で、教会の建ぺい率ってだいたい100%じゃないですか。それに対して神社って数%くらいなんですよね。そこにおいては石が主役だし、風の通り道が主役だし、木も川も主役である。そうした空間の、奥まったところに神儀のための建物がぽつんとある。この違いを見ても、日本の文化がいかに人間を「中心に置いていない」かがわかる。
人新世の時代といわれるいま、その考え方は世界でものすごく見直されているし、そこは日本が先駆的に取り入れていけるところなんじゃないかな。空海も未来のビジュアライザーのひとりだったと思うけど、そうした思想を現代にアップデートしなきゃいけません。日本はこれ以上、原点回帰も西洋化もしなくていいけど、「原点進化するアーキテクチャー」があるっていうのは強みじゃないかなって思います。
さっきはエロ=微生物の視点で都市をつくる可能性について話しましたけど、もうひとつのエコ=共同体の視点を、そうしたアニミスティックな意味で捉えていけば、本当に新しい世界のつくり方につながると思います。そういうことを楽しく、ユーモアを持ってやりたいなと思っているんです。
── 最後に、このメディアはトランスクリエーションを軸にしているので、今後いろんな人に共通質問として「あなたにとっての翻訳とは何ですか?」という問いを聞いていこうと思っています。翻訳を言語に限らない、「何かから何かへと変わっていくプロセス」という広義の意味で捉えたときに、市耒さんにとっての翻訳とはどんなものでしょうか?
(長く考え込んで……)ふと頭に浮かんだのは「シャーマニズム」かな。
シャーマニズムって、特殊な状態を通じて何かを出現させるってことじゃないですか。自分自身を「インスピレーションを交換するビークル」と捉えると、きっとまったく違うものが生まれてくる。舞城王太郎さんや最果タヒさんのような書き手はきっと、シャーマニズムに近いかたちで言葉を使っている──つまりエゴの言葉を扱おうとするのではなく、言葉を超えたところに何かを置いていくような作業をされていると思っていて、その感覚にはすごく共感するんです。だからぼくは、デザインでも教育の仕事でも、すべてを言葉で伝えようとは全然しないんです。霊性みたいなのを置いていきたい、という感覚が常にどこかにあるんです。

PROFILE
KENTARO ICHIKI
市耒 健太郎
UNIVERSITY of CREATIVITY主宰
博報堂クリエイティブディレクター
Interview by Yasuhiko Kozuka
Text by Yuto Miyamoto
Photographs by Keisuke Nishijima