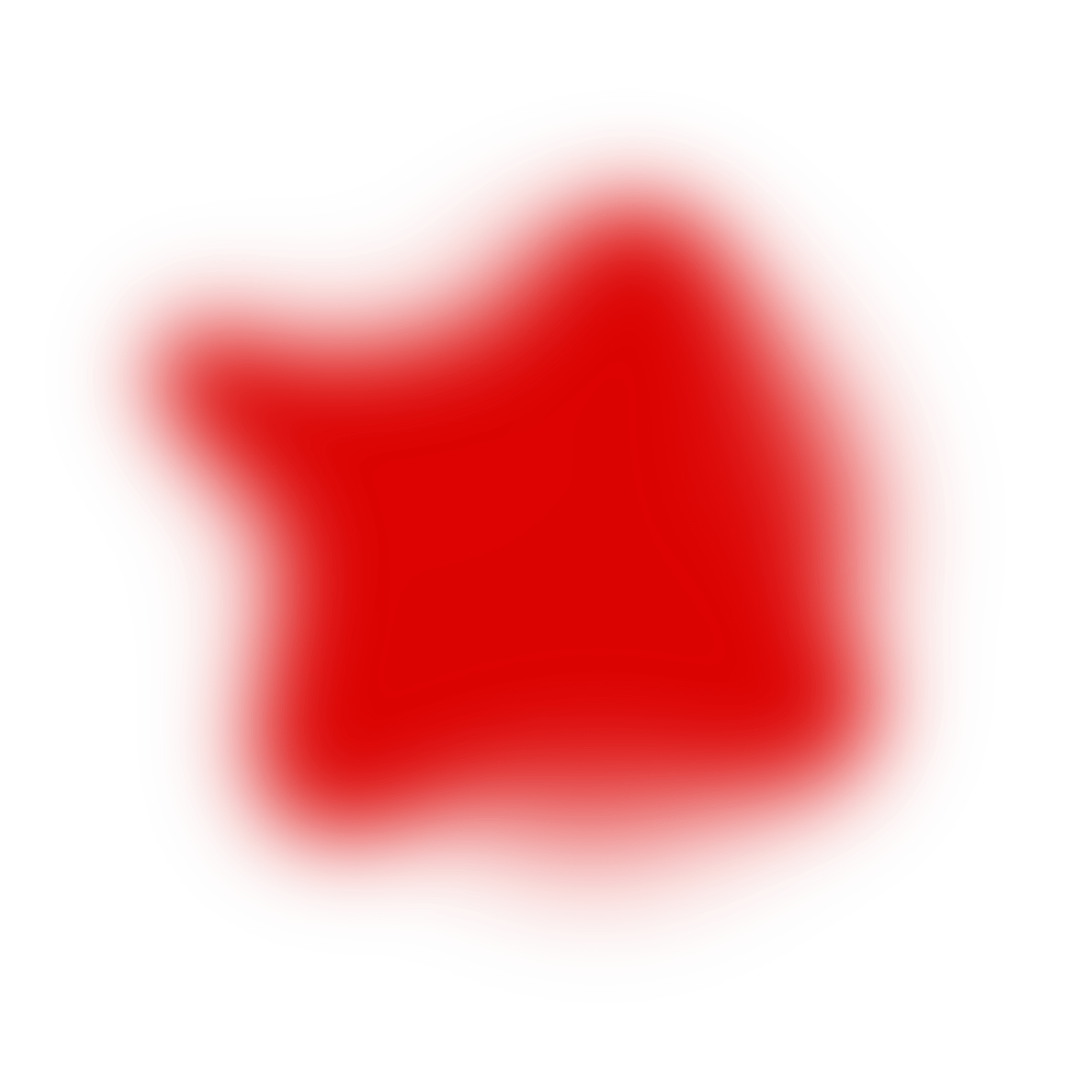第三回:創造力の木
前回の最後で、本格的に作り始める前にまず「物(創造)の根源へと降りて行く」ことがカスティリオーニやムナーリらのプロジェッタツィオーネ(デザイン)の重要な特徴であることに触れた。今回と次回の二回は、日伊二人のデザイナーが、それぞれ九州の波佐見と唐津の伝統工芸の職人たちを相手に行った二つのワークショップを扱うが、そのなかで二人とも「根源へと降りて行く」作業を軸にして脆弱化した伝統工芸の創造力を再活性化していくのだが、そのどちらもが、創造力についての深い思索を促してくれるものであった。
日伊二世代のプロジェッティスタ

その二人とは、エンツォ・マーリ(1932−2020)と城谷耕生(1968−2020)の二人である。
エンツォ・マーリは、元々芸術家としてデビューしたが、その後、それこそカスティリオーニ兄弟のある展覧会を見たことを切っ掛けにデザインの道に転身した人で、彼の生み出す洗練されたフォルムには、美的な価値だけではなく、必ず社会や経済に関わる多様な価値や動機が込められており、その膨大な数のプロジェクトは、いつもそこに関わる人々と社会に具体的な変容をもたらすことをめざしていた。デザインや生産活動のもつべき倫理性にことさら厳しく、イタリアンデザインの巨匠と見なされる存在でありながら、完全に消費社会の奴隷と化した(彼はそう思っていた)近年の「デザイン」が(その実践も言葉も)大嫌いで、講演や授業においても消費主義的なもの作りに従事する大半の企業やデザイナー、またそれらに迎合するメディアや学校に対して罵詈雑言を平気で叩きつけるような激しい人でもあった。
城谷耕生は、ミラノに拠点を置いて活動した1991年から2002年までの特に後半に、ある大理石メーカー[1]のアートディレクターとして同社にデザインを提供していたアキッレ・カスティリオーニやエンツォ・マーリらと関わりを持ち、プロジェッタツィオーネと言える時代のイタリアのデザインの一番良い部分をしっかり吸収して帰国した数少ない(筆者が知る限り唯一の)日本人デザイナーである。帰国後は故郷の長崎県小浜町に事務所[2]を開き、竹細工や陶芸など九州の伝統工芸とも深く関わり、地元小浜の北刈水地区のエコ・ヴィレッジ構想(2012)[3]を提案するなど、消費主義文化の中のデザインとは一線を画した注目すべき活動を続けていた。ミラノ時代からマーリの影響が強く、互いにインディペンデントな関係でありながら、師に心酔する弟子のようにマーリの哲学(特にフォルムのクオリティと創造における倫理性の重要さ)を吸収していた。マーリが亡くなった昨年十月には、筆者ともこれから自分たちがマーリの哲学を引き継いで伝えて行かなくては、と誓い合っていたのだが、その二ヶ月後、彼も師の後を追うかのように思いもかけない形で急逝してしまった。以下、この二人への深い敬意を込めて記したいと思う。
職人たちのために
クオリティにおいても経済的にも沈滞する各地の伝統工芸の産地では、よく著名な芸術家やデザイナーを招聘しては、作品をデザインしてもらうことに助成金をつぎ込むケースが多いが、マーリ自身も言うように、このような形の助成は、イベントが終われば、何も残らず、産地の育成にも何にもならない。なぜなら、「招聘された芸術家やデザイナーたちは自分の作品を完成させることにしか関心がなく、職人たちとじっくり時間を掛けて話し合うと言う気持ちも能力もないことが多い」[4]からだ。本当は、指導者となるデザイナーは、作家的な自己顕示欲を捨て、謙虚(humble)な黒子となって、自分ではなく、教え子となる職人たちの能力に焦点を当てながら、その可能性を最大限に引き出すことに全力を傾けるべきなのだ。そして、「何より必要なのは、各産地に小さくてもいいからやる気に満ちた職人たちのグループが生まれ、自分たちの文化的成長を自発的に考えようとするようになることである。それも(現在のところ盲目的な)行政官たちの判断に良い影響を与えるくらいの運動にならなければならない。そして、この思考行為は、土地の伝統工芸品や他所の作品のもつポエジーの質、原理を彼ら自身が理解、評価出来るようになるくらい、自分たちを鍛えるものでなければならない。」[5]
伝統の技術によって巨匠の作品を残すのではなく、地元の職人の意識を覚醒させ、彼らが現代世界の中で生き延びて行けるための力強い思考力、技術を支える幅広くまた深い知力を育てることこそが必要だとマーリは考えていたのだ。次回詳述するように城谷がワークショップで伝統工芸士たちに向き合う姿勢も全く同じである。
マーリは、常にこうした考え方でデザイナーと言う以上に教育者として欧州各地のクラフツマン(職人)と関わり、産業革命以降、疎外されて来た手仕事とそれに携わる人間の尊厳を回復すべく、いつも非常に具体的な形で各地の手工業の再興に携わって来た[6]。「消費者ではなく作り手のためにデザインする」デザイナーなのだ。そのことを良く理解していた城谷は、自らが関わっていた波佐見焼の産地の沈滞した現状を少しでも改善したいという強い思いから、マーリを講師に迎え、波佐見焼の職人(この場合は特に絵付け師)を対象に、波佐見とミラノでワークショップをしてもらうことを企画した。
波佐見焼の問題
波佐見町は、長崎県中央部にある人口15000人弱で、就労人口の40%ほどが窯業に従事するまさに陶芸の里で、一六世紀末に始まる波佐見焼は、比較的安価で大量に消費される[7]磁器(青磁、白磁)の日常食器の生産で知られ、単色(藍)の軽やかな筆遣いの絵付けを特徴とする。波佐見焼の資料を前もって受け取ったマーリは、それだけで波佐見焼の直面している問題を鋭く見ぬき、来日前にワークショップの課題を精確に見定めていた。
マーリは、伝統工芸を大きく二つのカテゴリーに区別していた。その一つ目の中でも代表的なのは、極めて技術の高い職人(名工)が古典から受け継いだ意匠やフォルムをひたすら再生産して行くもの。彼らは「脳の技術」は一切使わず、ひたすら手を動かして行くわけだが、時間も掛かり製品は相当な価格で売られる。
一方、二つ目のカテゴリーに属す波佐見焼の特徴は、それなりの安価な製品を大量に製作するところにあるので、波佐見の絵付け師は、どうしても短時間で安易に出来るモダンデザインや漫画風の稚拙な図柄で満足する傾向があり、マーリの目から見ると、いずれも芳しいクオリティに到達しておらず、現場の本人たちも自らの仕事に情熱や尊厳を感じるのは難しかった。「彼らは「伝統とは何か」がわからなくなっているのではないか」[8]とマーリは感じた。そこで、いつも極めて知的だが、同時に現実的なアプローチを採るマーリは、この条件の中で、どうしたら彼らが尊厳を持って働き、生き残ることが出来るかを探ることにした。
そして一つの戦略が見えて来た。全員が全ての図柄において名人の域に到達するのは難しいが、各人が何か一種類の図柄の名手になることは可能だし、それによって産地全体としては、競争力の強化につながると考えたのだ。つまり、波佐見焼のための戦略として、個々の絵付け師のさらなる専門化による技術の向上を奨励しようとした訳だが、後述の通り、彼のアプローチは決して単なる技術至上主義ではない。
もう一つのポイントは、彼が来日前にプロの書道家[9]の協力を要請したことである。受け取った資料に、日本の伝統芸術に特有の、一瞬の切れで表現する表情豊かな筆致(線)が全く見られないことには愕然としながらも、「書の筆跡には美的価値があるだけでなく、経済的な価値が備わっている」[10]と考える彼は、クオリティの上で、また波佐見焼の絵付け師に求められる生産効率性の観点からも、この一瞬で勝負する筆の技術の習得こそが彼らの将来にとって鍵になると判断したのだった。
ワークショップ
こうして、2001年9月[11]に波佐見にやって来たマーリは、長時間の講義とともに、上述の戦略に沿った具体的な作業を開始した。マーリは、まず、参加した絵付け師たちが自分たちの絵のクオリティを客観的に判断する能力を身につけられるように、ギリシャ、エジプト、エトルリア、中国、日本などの絵画、工芸の古典を鑑賞、分析して、表現のクオリティ、線のクオリティについて(例えば、兎という主題が各文化の中で扱われる際、構図はどうか、ポエジーはあるか、筆の技術を十分に活かしているか)研究させることにした。
次にしたのは、一番可愛く見えるポーズを探しながら、兎等、生きている対象を写生すること。これも、彼らが普段、習ったまま無意識に反復している狭い様式的な頸木を外して、絵を描くことの基本に返るためだった。
この後、前もって依頼していた書道家に多様な筆遣いの技術を見せてもらい、わずかな動きによって、優れた表現を如何に可能にするかを学んだが、その作業は、日頃自分たちが使っている筆の表現技術の可能性を見直す場となるとともに、一瞬にして美しさを実現する書道の筆の技術の中に、安価な大量生産を義務づけられた産地の絵付け師たちがクオリティを犠牲にせずに生産効率性を達成するための鍵が潜むという認識を全員に植え付け、この後の彼らのスケッチに影響して行く。絵筆の技術のクオリティが単に美的な問題ではなく、そこに社会的、経済的な問題まで解決する機能が潜むという認識は、まさにマーリならではのものであった。
ここまでした後で、六人の参加者は、挙げられた六つのテーマ(木、鳥、魚、兎、人、椅子)からそれぞれが今後発展させるべき主題を一つずつ選び、まずは鉛筆、ペン、次いで筆によるスケッチという形で、いよいよ個々が自分の担当する主題に対する技術を磨く段階に入った訳だが、この、実践に入る前にまず、絵を描く行為そのものを「より広く、より基本から(根元から)」学習し直すというマーリのプロセスは、ムナーリによる創造力学習のプロセス(ムナーリ・メソッド)ともよく似ていて、まず一歩、二歩戻ってからはるかに遠くに行く、この二重のベクトルをもった創造力は、プロジェッタツィオーネの重要な特徴であった。



dav
波佐見での作業は、ここまでだったが、その二ヶ月後にミラノに再び集まり、それぞれの図柄をどうやって現代的にするかについての作業が行われ、習作の一つ一つをマーリが厳しく講評しながら、それもなるべく少ない要素で俳句のように表現する道が探求された。
途中で脱落者もいたが、最終的に残った、鳥、兎、魚を担当する三名[12]は、波佐見に帰った後も練習を積み重ね、習作をマーリに送っては、それにマーリがコメントすると言う形でやりとりが続き、ようやく2002年の春に染め付けを施した陶板を焼く所にまで辿り着く。さらにマーリと城谷がデザインした花器と半月皿に絵付けをした製品が2002年夏に完成した。開始から約一年で、ワークショップのプロセスも詳しく解説する図柄のカタログ(『INVENTARE UNA TRADIZIONE – 新たなる伝統』)、展覧会[13]、そして製品化へと進んだ成果にはマーリも満足していたようである[14]。

手の技術、脳の技術
後日城谷に聞いた所では、マーリは、「職人たちは、みな手の技術には優れているが、脳の技術が足りない」と言っていたそうだ。彼は職人たちの「技術」の高さは認めながら、それ以上に大事な要素が決定的に欠けていることに着目していたのである。
伝統工芸や伝統芸能等、伝統の芸術に携わろうとしてその道に入る若者は、まず、形(様式、型)から入る。それを師匠から教わるままにひたすら模倣して、伝統文化の歴史の中で既に成立している型、フォルムを再現再生出来るように努力する。大抵の場合、理屈は教えられず身体で学べと言われる。もちろん若者にとって、つべこべ言わず、技術をまず手や身体にしみ込ませることは非常に重要なことである。言葉にならずともむしろ暗黙知として技術を持っていなければ、芸術家としてそれを使いこなすことは出来ない。理屈では楽器は弾けないし、轆轤を引くことも叶わない。しかし、そういう彼らの多くは、美しい物を作りだしながら、なぜ自分たちがその素材を使うのか、なぜそうやって作るのか、また、なぜ、どうして、それが美しいのか、そして特にそれが現代にとってどんな意味を持つのか、という問題を自らに問いかけたことがないのである。「脳の技術が足りない」とは、そのこと、この客観的認識力の欠如を指していたのであり、マーリは、波佐見でも参加者達のより専門的な技術的向上の前提として、職人たちに自らの仕事に対する客観的批判的な思考と認識能力(脳の技術)を持つことを求めたのである[15]。
時代とともに社会の状況や需要が変わるとき、いくら洗練され、完成されたかに見える伝統文化も毎回実践する度に当事者が自分たちのart(芸術 = 技術)の基盤を厳しく見つめ直さない限り、質においても経済的にも生き延びる力を持てないとマーリは考えていた。自分の芸に対する客観的な分析眼がないと時代の動きへの対応も出来ない。伝統文化が生き延びられない時には、大抵そこが欠けている。伝統的な「技術」を習得するだけではなく、それに生命を与える、人間性や社会性、環境にも関わる、より広い知を備えた「創造力」をもつ必要がある。これは、重要なポイントである。技術=創造力ではないのだ。むしろ、洗練された専門技術を持つ人達ほど、逆にそれを支える豊かな創造力の土壌から乖離していることは珍しくない。技術と創造力の間のこの有機的な関係を取り戻さない限り、伝統文化(伝統文化だけではないが)が生き生きと存続することは不可能なのである。
創造力の木
ところで、ここで言う、「技術」と「創造力」の間の有機的な関係をもう少し具体的に視角化しようとすると、かつてパウル・クレーが芸術家の創造力について想像したように[16]、一本の大きな木のようなものが見えて来る。それは、個々の人間の営む活動がもつ創造力にも、その総体としてのある職能や文明全体(歴史)の創造力にも適用出来る図式で、ここでは「創造力の木」と呼ぶことにする。
この「木」の図式においては、大地(土壌)が、人が住む地域の自然や地域社会、そして歴史的遺産も含めた生活基盤をなす「環境」、その中に広く深く伸びている根とその上に立ち上がる太い幹の部分が「人間」の身体と精神、そしてそれに支えられて無数の枝を空間のあらゆる方向に広げている樹冠の部分が「技術(文明)」にあたり、「環境」「人間」「技術」の三要素は、ここではまさに一本の木のように有機的につながっている(図1)。
また、「創造力の木」が文明全体の創造力を表す場合、樹冠を構成する各枝のまとまりは個々の専門分野を表している。(図2)そしてこの木の中を樹液のように上下にエネルギーと物質が流れている訳だが、上向きは前へ前へと創造や生産を後押しする、文明のアクセルとも言える「進歩」のベクトル、下向きは、逆に反省的思考によって文明にいい意味でのブレーキをかける「退行」のベクトルを表している(図3)。歴史の創造力は、常にこの二つのベクトルの総合として作用する訳だが、個々の人間の創造力を観察しても同様のことが言える。

図1:創造力の木 
図2:枝のまとまりが各専門分野 
図3:進歩と退行の二方向のベクトル
この図式で見ると、高度に洗練され、専門化された伝統工芸は、一見逆説に見えるが、実は先端技術の諸分野と同じく、極細の枝先に位置する。(図4)「伝統」と言いながら、実は、「創造力の木」の根っこや大地からかなり遠い所にあり、「技術」の大元にあるはずの人間の生(幹、根)や地域の自然、文化、歴史(大地)との関係は希薄化していることが多い。そんな枝先に届く樹液は、質量ともに稀少で、枝先に閉じこもって創造力の全体性(つまり「創造力の木」の全身)を見失った伝統工芸は、やがて乾涸び枯れるしかない。にわかに高い技術がある分、それだけでやれると錯覚しがちだが、創造力が木のようなものだと考えれば、細い枝だけでは続かないのは明らかだ。そんな創造力は脆弱至極だ。一見完成されたかに見える伝統芸術も、毎回実践する度に、必ず、普段使う「技術」よりも下位にある創造力の幹や根、大地のレベルまで一度降りて(創造の根源へと降りて)行かないと、自分の創造力を生き生きと力強く維持することが出来なくなってくるのである。この認識こそ、マーリのワークショップから(マーリの言葉以上に)見えてくる最大の教えである。

マーリの出会った波佐見焼の絵付けも例外ではなかった。波佐見焼の絵付けも「創造力の木」のある一本の非常に細い枝先にいる。(図5)マーリが求めたように、中国やギリシャなどの異文化の絵画や工芸のクオリティを理解するには、図6に見るように、一旦、自分たちのいる細い枝先から、相手の芸術文化の枝との接点となる、少し太い部分まで降りて来なければならないが、枝が太くなれば、それだけ流れる樹液の質も量も豊かになる。この図で低い所に降りることは、創造力を活性化することを意味するのだ。また、同じ筆とは言え、絵画ではない書道がもう少し遠い枝にあるとすると、その筆の技術をものにしようとする時、さらに下の接点まで降りることになるが、それが質量ともにさらに豊かな樹液をもたらすことは必定であった。また、上記の古典芸術の知識を歴史的遺産と位置づければ、それを学ぶことは、枝⇒幹⇒根を経て、真っすぐ大地(土壌)まで降りることを意味する。(図7)
こうして見ると、マーリのワークショップでの作業は(最終的には個々の職人のさらに専門化された技術の向上を目指しながらも)、いずれもが、高い枝先に閉じこもった絵付け職人たちを少しずつ(より豊かな創造力の樹液の流れる)根の方に引き摺り下ろすことで、彼らの創造力を再活性化させようとするものであったことが分る。(図8)そして実は、前回もムナーリのサングラス「パラルーチェ」の例で見たように、一度「創造力の木」の根元まで降り(退行)、豊かで多様な質の樹液(多様な知識、情報、その他)を汲み上げた上で、根⇒幹⇒枝と再上昇(進歩)して、最後枝葉のレベルにある「技術」の領域に戻って創造行為を完遂するという、この上下二重のベクトルによって「創造力の木」の全身をフルに活用するやり方は、そもそもムナーリやカスティリオーニらのプロジェッティスタたちがいつも意図的に実践する方法だった。(図9)
プロジェッタツィオーネを育んだ戦後のイタリア社会においては、進歩と退行の二つのベクトルの間に、短い時期ではあったが、奇跡的に均衡な状態が可能になっていたのである。それは、自然の創造力の状態にも近く、極めてサステイナブルな創造力の環境(humus)であったが、その後二〇世紀後半の資本主義経済の急速な発展のなかで、イタリアも含め、大概の先進国の文明は、ほぼ完全に「進歩」のベクトルに呑み込まれ、特に都市部においては、「退行」のベクトルは、ほぼ完全に排除されてしまった。資本主義の圧力の強烈な東京等の現代の大都市においては、この二つのベクトルの間のバランスは完全に失われており、全てが前のめりに超高速度で実行され、ゆっくりと振り返って反省的な思考を巡らす余裕は許されない。
こうして「創造力の木」に独占的に充満した「進歩」のベクトルが大量に枝先に集中し、頭部が鬱血状態になった「木」は、どんどん頭部だけが発達し、頭でっかちになる一方、 「退行」のベクトルが十分に降りて来ない根は、土壌とともにやせ細り、文明の「創造力の木」は、今や倒壊寸前のかなり危険な状態にあるが、実は、これこそが現代世界のかなり真実味のある肖像なのである。(図10)日本の都市部で生活し、働かれている方々は、自分の営みの中で、日々どれくらい意識的に「退行」のベクトルに身を任されているだろうか。高度に発達した資本主義社会の中で、短い時間ですぐ答えを出すことに慣れ切っている方々は、もう長いこと「退行」のベクトルなどには触れた記憶すらないかもしれない。普段、意識もされないことかもしれないが、それこそ非常に危険な「倒壊寸前」の徴候なのである。過労死するのは、個々の人間だけではない。社会や文明自体が各部門に劣化症状をきたし、倒壊の予兆を既に聞きつけている人々も少なくない。
この図を見ても、近代以降に大幅に忘れられてしまった「退行」のベクトルを個々の人間が生活、そして仕事のなかで回復し、この木(文明の創造力)の健全な状態を取り戻すように努力することが、集団としての現代人にとっての最大の使命であることは明らかだろう。「三つのエコロジー」が究極的に求める所もゴールは同じである。残り時間も少なくなった今、プロジェッティスタたちがかつて日々活用していた、二重のベクトルが均衡を保つ「控えめな」創造力のあり方を学び直すことは、あながち無効ではなさそうだ。

このマーリのワークショップの経験に大いに影響を受けた城谷は、その後、消費社会の商品を作るようなデザインの仕事からは少し距離を取り、むしろ、九州の竹細工や陶芸に従事する職人たちに対して、教育的な立場で積極的に関わるようになる。まさにマーリの教え通り、控えめな黒子となって「消費者ではなく作り手のためにデザインする」ことを選んだのだ。その中でも特に2008年に佐賀大学の主催で始まった、唐津の若手の陶芸家のための特別講座「ひと・もの作り唐津プロジェクト」の講師として二年目に行ったワークショップは、マーリの波佐見でのワークショップのアプローチのスケールをさらに大きくした、素晴らしい作業(筆者は彼の最高傑作だと思っている)なので、次回は、これについて語ろうと思う。
- 脚注
- 1. UPGROUP
- 2. スタジオシロタニ。
- 3. 長崎大学の環境学科の主導の下で小浜町に予定されていた地熱のバイナリー発電の実験活動をサポートするために、2012年8月、同町北刈水地区を町民の環境意識を刺激するいくつかの機能を備えた場所(エコヴィレッジ)として構想する提案を学生達のワークショップを通してまとめた。指導は城谷と多木。
- 4. 『INVENTARE UNA TRADIZIONE – 新たなる伝統』(KAZAN プロジェクトの成果をまとめたカタログ、Aura Inc.製作、2002年)4頁。これは、エンツォ・マーリ自身の言葉。
- 5. 同上。
- 6. その代表的なものが、1990年代にKPM(ベルリン王立磁器マニュファクチャー)のためにした仕事である。
- 7. 1990年代前半には全国の生活雑器のシェアの1/4から1/3を占めたこともある。
- 8. AXIS、2003年3・4月号、76頁。
- 9. 馬場直記氏。
- 10. 『INVENTARE UNA TRADIZIONE – 新たなる伝統』9頁。
- 11. 2001年9月10日~12日。
- 12. 宮崎綾子(鳥)、山口祥治(兎)、関宏昌(魚)。
- 13. 「デザインの仕事展 – アウラの新たなる伝統への挑戦」、於AXISギャラリー、2002年12月12日~27日。
- 14. このプロジェクトは、その後、城谷と参加者によって、継続性のあるアイデンティティを与えるために「KAZANプロジェクト」と名づけられたが、同ワークショップに同席し、カタログの執筆者でもある田代かおる氏によると、マーリが火山好きだったこともあって、「KAZAN」(火山)と付けられたのではないかと言うことだった。
- 15. 実は、ラスキンの労働者大学がこれと全く同様に職人の知的覚醒を目指していた。
- 16. かつて、パウル・クレーが芸術家の創造力のプロセスを一本の木に喩えたことがある。クレーによると、芸術家は、極めて複雑な世界に身を沈めており、彼の自然と生についての知識の体系は、地下でありとあらゆる深さと方向に張り巡らされた根に喩えることが出来ると言う。その根から上ってくる樹液は芸術家の身体に染み渡り、その目に溢れることになるが、そうなった芸術家は一本の木の幹のようなものになる。この樹液の流れに満たされ、突き動かされる芸術家の精神の中では、想像力が疾駆し、さらに時空の中を無数の方向に分かれて枝が伸びて行くように、創造力のプロセスは展開し、その中で幹として立つ芸術家について、クレーは、下手に何かをせずに、ただ地下から来るものを、上へ、上へと渡して行く役割だけを担うべきだという。
PROFILE
Yosuke Taki
多木 陽介
アーティスト、批評家