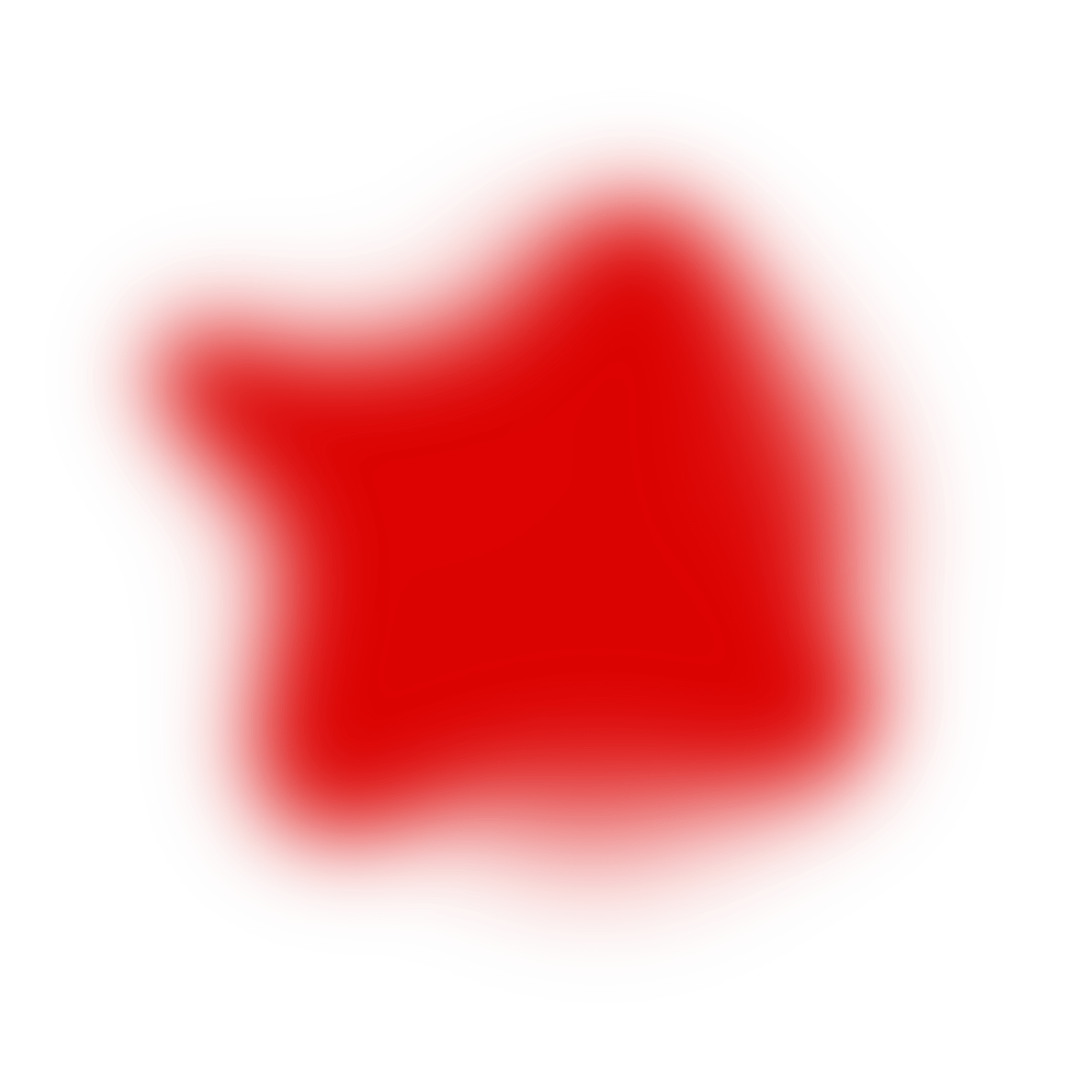(このテクストは、1997年10月パリのテアトル・ドゥ・ラ・ヴィルにおいておこなわれた文楽公演のパンフレットのために書かれたものである。演目は「義経千本桜」、「曾根崎心中」であった。はじめて文楽を観るフランス人のために、文楽のドラマがどう生まれるのか、その生成の「秘密」を語ろうとしたものである。)
文楽の人形には頭と手足しかない。というのも、着物の下、胴体はないからだ。心(臓)は一個の無である。まさにその無をこそ主遣いの左手が埋めるのだ。手が頭を支え、眼を、眉を、口をコントロールする。その無を通して、人形は、内側から、演じられる。
つまり、人形は、舞台で、ただ模倣的な演技を行っているのではなく、みずからの内部の固有の生によって生気づけられなければならないということ。
他のすべての演劇とは異なって、そこでは生を表現するのではなく、まずなによりも、生をとらえ、受肉し、あるいは人形に受肉させるのでなければならない。
実際、太夫はただ口をきかない人形にかわって語っているのではない。同様に、三味線もただ歌や語りの伴奏をしているわけではない。
三味線の撥こそが、すべての出来事の空間を開く
逆なのだ。すべては三味線とともにはじまる。その撥こそが、すべての出来事の空間を開く。ときにはメロディー的に歌うように、ときにはリズム的で異様な趣きで、三味線はそれだけでドラマの空間のすべての動き、すべてのモチーフを挑発する。
文楽とは、見るものであるより前に、まずは聞くべきもである。だから、心に触れる三味線の音こそがまずは、われわれに出来事へと耳を開くことを教えてくれるのだ。
三弦からなる三味線のなかでももっとも重い*太棹を聞くと、われわれの魂は、来るべき出来事を待ちつつ、われわれ自身のもっとも深くあるものを振動させる。だから、大事なことは、あなた自身を十全に三味線の音楽のなかに突き入れること、そして他のすべての要素を召喚しつつ運命のドラマを言いつけるこの奇妙な力に身を委ねること。
太夫の語りは、登場人物に「存在」を与え返す
だが、三味線によってディテールに至るまでドラマの運動が喚起されるのだとしても、音楽だけでは、ドラマを人間化するには十分ではない。本来の意味でのドラマが開花するためには、三味線が喚起する音楽から、そのドラマを同化したいくつもの人間の声が鮮やかに立ち昇ってくるのでなければならない。
そして、それこそが語り手であり歌手である太夫の役目であり、かれは、まるでプリズムのように、音楽によって描き出されたドラマの流れに、声、感情、性格といったすべての音階を与える。だから、太夫がなすのは、それだけで、すでにドラマのまったき分析であり、まったき解釈である。
太夫の語りを聞きながら、われわれはすでに、ひとりひとりの登場人物がそれであるもの、その人物が経験すること、欲望すること、その人物を待っているものを、その人物自身が知っていることを超えて感じるのである。太夫は、ただただその声によって、それぞれの登場人物にいわばそれぞれの「存在」を与え返すのだ。
太夫にとっては、問題はさまざまに異なった声を演じわけることよりは、それぞれの個別の性格とその特異な運命とともに、それぞれの人物の「存在」が涌きあがってくるもっとも深い源を探りあてることである。だから、それはただ美しい声というわけではない。そうではなくて、太夫は、さまざまな異質の波(周波数)をそなえた、深く、謎めいた声をつかみとらなければならないのだが、そのためには、ときには数十年にも及ぶ稽古を通じて、「みずからの本来の声」を「忘れる」ことすら学ばなければならない。
太夫の声は、喉からではなく、「腹」から、内蔵から出るものでなければならない。すると、その声を通して、それぞれの人物の生、それぞれの魂が独自の色を帯びてくるようになる。そして、特異な、比類のない一個の運命が花と咲き出でる。それをこそ、われわれの耳は追っていかなければならないのだ。
人形は内側から生を吹き込まれて、運命の瞬間を生きはじめる
そして、そのときはじめて、人形が命をもつ。人形が、きわめて微細な行動そして情動にまで、眼に見える正確さを与えてくれる。人形遣いは、みずからそれを演じているかのごとく、太夫の驚くべき声によって展開される生命の流れをつかまえる。すると、人形は内側から生を吹き込まれて、みずからのもっとも強力な運命の瞬間を生きはじめる。
文楽において、顔が隠されていようが素顔のままであろうが、人形遣いの存在が観客の想像力にとってまったく邪魔にならないのは、そこでは、一般の演劇とは異なって、人間が演技をするのを見るのではなく、命なきものである人形が突然に、一個の生、一個のパッション、一個の運命を受肉することをこそ見るものであるからだ。人形は出発点ではなく、生命のドラマティックな流れの到達点である。そこではドラマの表現は、どんな人間の演技力をも超え出た途方もない正確さの演技のうちに成就する。指の動き、瞬き、眉の動きに至るまで、われわれは生命の正統性がそこで脈打ち、溢れ、流れ出てくるのを目の当たりにする。
文楽の奇跡!
そうだ、じっさい、われわれは、きわめて強い情動に動かされた人形の頬が赤く血の気に染まるのさえ目の当たりにするのだ。
文楽の「いま、ここ」に、運命を分有する
これが文楽の秘密である。
すなわち、三味線によって始動させられ、太夫の声によって運ばれた、劇的情動の巨大な流れが演劇空間の全体に浸み渡り、そして人形のウルトラ級に細やかな演技のうちに結晶化する。
人間によく似た人形という類似を通じて、ときには悲劇的である人間の生なるものが、究極的な形態として現れる。こうして人間の苦悩が、歓喜が、美学的、形式的な完成に到達する。
そしてそれは、観客にきわめて強いカタルシスをもたらす。そしてそうであれば、舞台に喚起された魂たちにも、どうして一種の「救い」をもたらさないことがあろうか。
三味線の音楽に、そして太夫の神秘的な声に浸されて、われわれ観客もまた、ここでは、まったく人形と同じように、そこで演じられる運命を分有するのだから。
三味線と太夫の床が、舞台の中にではなく、前に飛び出た位置にあって、一方では人形へ、他方では観客へと向いていることはけっして偶然ではない。われわれもまた、人形と同じく、生の、パッションの、そして運命の「容れ物」である。われわれもまた、人形と同じように、その運命を分有し受肉するのだ。
そうして他の運命を分有すること――それこそが、人間という存在のもっとも固有なことなのであり、それを、いま、ここで、行うこと、それこそが演劇の崇高な使命にほかならない。人間存在の劇的な運命は、多くの人々によって分有される流れとして流れていく。
人間の生は、まるでひとつの旅だ。そこではつねに、人間固有の愛と運命の残酷な必然性が絡みあい織りなされている。これこそが、文楽のドラマツルギーの基にある「哲学」なのである。
*三味線には、長唄などに用いる「細棹」、清元節・常磐津節などに用いる「中棹」、義太夫節などに用いるこの「太棹」の三種類があり、棹が太い種になるほど、胴も大きく、また弦も太くなり、重低音まで出せる。義太夫節の代名詞ともいえる。
COLUMN
TEXT & EDIT: Yasuo Kobayashi