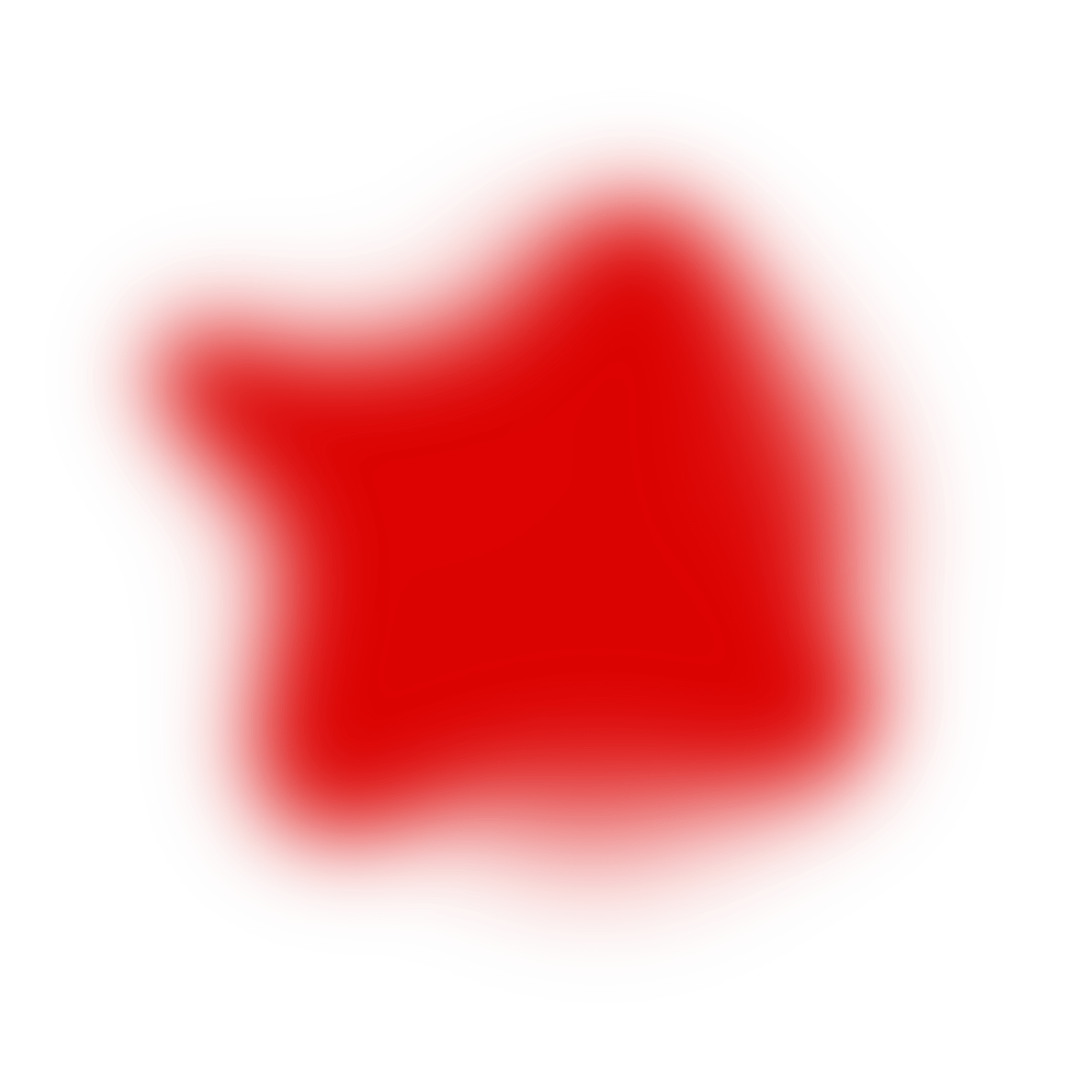PAGE.1
PROFILE
TRANSCREATION®Labのインタビュー第一回は、どうしても市耒健太郎さんにお願いしたかった。Labの編集長である私の会社員時代の先輩という存在をはるかに超えて、上野のちいさな蕎麦屋でもニューヨーク・ブルックリンの寂れたビルの屋上でも、会うたびに、そして何年も会っていなくても深遠なインスピレーションを授け続けてくれる人である。市耒さんに会うと、壮大なのに繊細で慈悲深くて、まるで大自然に包まれているかのような不思議な感覚になる。市耒さんの、その霊性に満ちた創造力がどこからやって来るのか、お聞きしました。
Interview by Yasuhiko Kozuka
Text by Yuto Miyamoto
Photographs by Keisuke Nishijima
「言葉にならない体験」をどれだけ持っているか?
── まずは、市耒さんのクリエイティブの根底にある考えからお聞きできればと思います。
ちょっと自分なりに切り込むことを話すと、結局ぼくは言葉を信じてないんですよ。それが根源にあるものですね。どういうことかというと、言葉って、過去と現在を低く握手させたり、人と人を低く握手させたりするものであると。例えば、本当に好きな子が目の前にいたときに、「おまえを好きだ」と言うのも言葉だけど、「おまえなんて大嫌いだ」って言っちゃうのも人間じゃないですか。言葉にはそういうところがあるなということは常々考えていますね。とはいえ、言葉で表現することも諦めてはいなくて、ぼくらの仕事はある種未来のビジュアライザーでなくちゃいけないので、「未来をビジュアライズする言葉って何だろう?」「そのためにどういう言葉を使わなきゃいけないんだろう?」ということは考えている。だから、いままで言語化されてないことを表現する言葉とか、感覚的なことにたどり着くための言葉みたいなものをずっと探している気がします。
あとは、あんまり難しく考えないようにしてる部分もあって。ぼくは小学1年生でその人の得意なことやパーソナリティがだいたい決まっちゃう「小1決定説」を唱えているんですけど、小1のときに圧倒的におもしろい子とか、圧倒的に美しいものを描ける子とかって必ずいるじゃないですか。その子が無垢に持っているものがちゃんと社会に出れば、もっとおもしろいものとか美しいものが生まれてくると昔から思っているわけです。でも、かつてのおもしろかった子とか美しいものを描けた子に大人になって会うと、けっこう、がっかりすることってありますよね。あのギャップって一体なんなんだろうって、ずっと考えているんです。
すると、そういう人が本来持っていた創造性とか才能をつみ取っているものがあるんだろう、と。それは、受験と就活ですよ。教育とか社会のなかには、子どもの才能をつぶしながら「イコールの記号」を結ばせて「ひとつの正しい答え」に導かせるような型が蔓延していることに気づく。そのなかで、野放図におもしろいやつとか、美しいものをつくれる子の芽が摘まれているんだなと気づくわけです。そこに対するアーキテクチャーのつくり直しっていうのを、ぼくはすごく意図しているんですよね。どうやったらもっと、わくわく、ドキドキする世の中になるんだろうということを、いつも考えています。
──「言葉を信じていない」という考えは、どんな経験から生まれているんでしょうか?
ぼくは子どものとき、ずっと鹿児島とか茨城とか神奈川とかの山野で遊びまわって育ったんです。家がちょっと変わった家だったから、野菜も無農薬自給自足だし、養鶏とかもしていて。「健太郎、卵取ってこい」と言われて毎日まだあったかい卵を手に取って、感謝して食べる。その鶏が年をとって息絶えた時も、まさか……と思ったら、夜、鍋になっているんですよね。泣きましたね。本当にいろんな動物がいる土地で育ったから、時の移ろいとか生死とか、爪の間から洗い流せない土とか血の香り、夏の初夏の川ゴケの香りとか、そういうものと一緒に育ったんです。
ぼくが子どもの頃にいちばん好きだったのは川遊びで、おやじが毎週金曜から学校サボってクルマで川に連れて行ってくれるんだけど、数キロくらい上流にぼくを降ろして、自分は下流に戻ってアユ釣りをやってるわけ。それでぼくは、その川をずっと下まで、親父の釣りしてるところまで流れてくるわけ。おやじはいい水中眼鏡もつくってくれて、水の中をずっと見ながら何キロも川を下っていると、それはそれはすごいアメージングな映画だったんです。川虫がいたり、ヤゴがいたり、アユやイワナがいたり、蛇が泳いでたり。おやじがアユ釣ったら、焚き火しながら焼いて食べる。そうした生物への慈しみとか、自然の不思議を小さいときに叩き込まれたのは大きいですね。
ある夏の朝、いきなり群馬にひとりで行けって言われて。行ったら、牛のお産の手伝いだったんです。そのときに子牛が落ちてきた羊水のドロドロドボドボッって音がまだ頭に響いているんです。そういうのを思い出しているとき、なんか感覚が洗われるような気がするんです。そこには、東京で感じる、いわゆる「作品」っていわれている閉じた創造物とは、まったく違うリズムと解像度がある。ぼくは、そういうものを忘れないようにしているというか、大事な判断のときに東京的な言葉のほうに持っていかれないようにしているっていうのはあるかもしれません。

──市耒さんのように自然のなかで育った経験のない人たちが、そうした非言語体験の重要性に気づくためにはどうすればいいと思いますか?
自然や都会にかかわらず、やっぱり言葉にならない体験を、言葉とかシステムに「つながれちゃう前」にどれだけ持てるかがすごく重要だと思います。だって、言葉っていわゆる再生装置でもあるから。雨が上がったときのあの匂いとか、森の深みや川ゴケの匂いとか、あるいは友達との取っ組み合いでもいいかもしれない。そういった体験が先になければ、どれだけ再生装置があっても概念が空回りしちゃう。
正しくないかもしれないけれど、おもしろいもの
── 市耒さんは、博報堂のなかでずっと新しい問いをつくり続けている存在だと思います。そんな市耒さんが、どうやって新しい問いをつくっているのか、そのプロセスについて今回のインタビューではお伺いしたいと思っていました。
シンプルに、ぼくはやっぱり退屈なのがいちばん嫌なんです。「Fight against boredom」ってよく言ってるんだけど、やっぱり人と同じことはしたくないし、昔と同じこともしたくない。最適化や合理化には絶対に抗う。特にAIの社会って、すべてが最適化されていくじゃないですか。そういうものに抗わなければ、「○○が好きなら△△も好きなはずです」って、リコメンドエンジンの牢屋のなかに生きているみたいになってしまう。これはすげえ反感を買うと思うんだけど、やっぱりぼくにとっては、正直、データは過去で、クリエイティブが未来なんです。いざスマホとかAIがもう少しいばり始めたら、水かけちゃうぞってどっかで思ってます。寝室や居間にも持っていかないようにしてるし。
社会にもそういう部分があるじゃないですか。例えば高層ビルから外を眺めても、世界中のどこの空港に降りたっても、まぁこの50年でずいぶん似たような感じになっちゃって。100年前や200年前は全然そうじゃなかった。都市が合理化された結果、形も素材も共通化されていってしまったんです。だからこそ、例えば、このUNIVERSITY of CREATIVITYの空間は、裸足がベースで、かつ、不規則曲線でつくることにしてみたんです。 曲線のコルクでしょう? こういうのをつくるのはすごく大変なんだけど、やっぱり均質化に抗いたいという気持ちがある。「一点物」をその時空に刻み込むっていうことは、ある種の「やんちゃ」を応援をするっていう態度だと思うんです。だから、何かそういう部分はあるのかもしれないね。でも迷ったら、あんまり深く考えないようにしています。最後は、頭ではなく、腹で決める。

── 退屈じゃないっていうことは、おもしろいということでもありますよね。
そうそう。
── 市耒さんは常に、「正しくないかもしれないけれどおもしろいもの」が大事だと言い続けていますが、その「おもしろい」をもう少し因数分解すると、市耒さんにとっての「おもしろい」とはどういうものなんでしょう?
おもしろいっていうのは因数分解できないものかもしれないと思いつつ、「おもしろい」ということに関してぱっと思い出した話をふたつすると、ひとつは「制作論のひつまぶし」。ぼくはCMを企画する仕事を10年くらいやっていたんだけど、最初、クリエイティブ配属したときの師匠、河野さん(河野俊哉ECD、カンヌフェスティバルで金賞など受賞多々)が、映画代全部出すから、とにかく1年中たくさん見てこいって言ってくれたんです。だけど「同じの、3度見に行け」って言われたの。例えば『アバター』を見るときに、1回目はバーンと普通にリラックスして見ろと。2回目はおもしろかったところを「何でおもしろいの?」って分析しながら見ろと。そして3回目は、「もし自分がその作品を撮り直すんだったら、どうするんだ?」を考えながら見ろって。そうやって3回見ろって言われたわけ。ぼくはそれを「制作論のひつまぶし」って呼んでるんだけど、とにかく同じ作品は3度見る。それはいまでも癖になっていて、どんなデザインを見ても、どんな作品を見ても、「何がおもしろいのか」「自分だったらどうおもしろくできるか」を考えるようになっちゃった。病気だよね。
もうひとつは芸大大学院のときに研究室の手伝いをさせていただいた故・石岡瑛子先生(コッポラ映画ポスター、ターセム映画衣装デザイン、ビョークPVなど。アカデミー衣装デザイン賞、紫綬褒章)がよく言っていたことで、とにかく創造には「発想のモチーフ」がすべてなんだと言い続けていました。例えばいま、時代ごとの流行りのトーンとかマナーとかがあるじゃないですか。そういうものを見ちゃ絶対ダメで、インスピレーションは悠久のものに持たなくちゃいけないんだと石岡さんは言うんですよ。それで、学生のぼくが何を話してもけちょんけちょんに言われるから、「じゃあ石岡先生はどういうものにデザインのインスピレーションを感じるんですか?」って聞いたら、「セミの腹」とか言って。あ、そこか!みたいな(笑)。でもたしかに、セミの腹、すごく強いわって。空気なんて読む必要ない。そういう自分なりの制作論とかインスピレーションの持ち方をつくり出すというのが、作家性にはいちばん大事なんだと肌で感じさせてもらった。
あとは、おもしろい論で言うと、企画が出たときに、みんなが一同うなずいているものは信じない。すぐ合意が得られるってのは、たぶん正しいんだよね。おもしろすぎるものが出てきたときは、絶対誰か不安そうな顔をしてる人がいるんです。「やばい、これほんとに進める気じゃないですよね……」みたいな(笑)。そういう雰囲気になったらいいサイン。だって見たことないものが多ければ多いほど、既視感がなければないほど、それはおもしろいってことに包含されるわけだから。
── 説明し過ぎるのも野暮な気もしますけど、あえて市耒さんの話を別の言葉で言い直すと、「これまでの物差しで測れないもの」こそがおもしろいものであると。
そうね。広告でもテレビでも出版でも、企画を出して「ああ、わかるわかる」と言われたら、それはクリエイターとしてはおしまいな部分があるんですよ。だって、新しい価値を生み出してないってことだから。だから、よくほら、「普通にうまい」って言うじゃないですか。クリエイターは、普通にうまいものを出したらもうおしまいなわけです。「なるほど」って言われるものはダメで、「まさか!」というものじゃないと会議には出しちゃいけないですよね。
次ページ:「人間ならざるものたちの言葉」に耳を澄ませること
PROFILE
KENTARO ICHIKI
市耒 健太郎
UNIVERSITY of CREATIVITY主宰
博報堂クリエイティブディレクター
Interview by Yasuhiko Kozuka
Text by Yuto Miyamoto
Photographs by Keisuke Nishijima