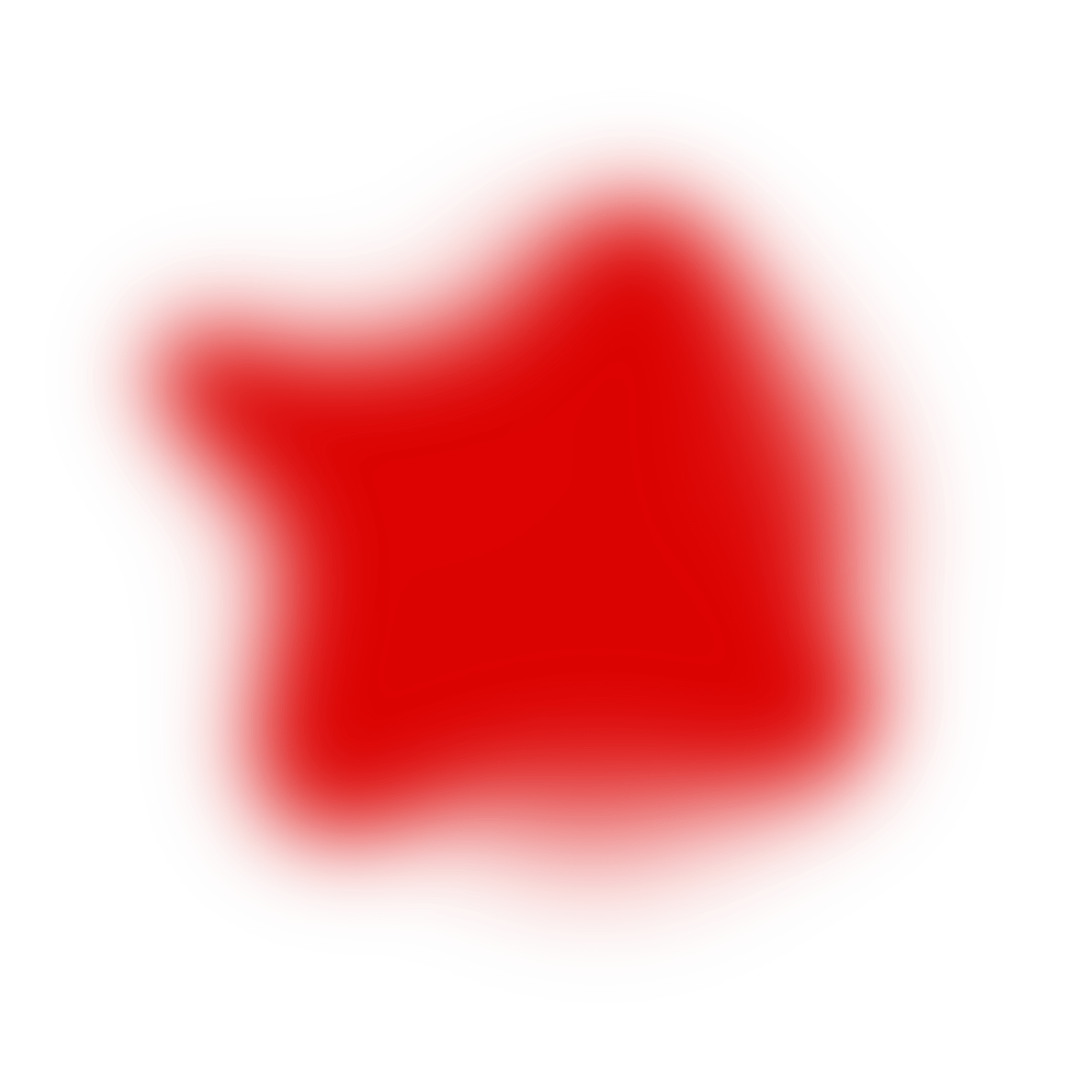多言語の達人
かつて、自分がクルーズ船で世界を2周していた、名付けて大航海時代。同じ通訳スタッフの中に、それはそれは、すごい男がいた。
当時27歳にして、12言語ほどを操っていた、アメリカ人のベン。
彼は、毎度寄港地に寄っては、
「今日は、トルコ語が話せてよかった」
「今回は、クルーとインドネシア語で盛り上がった」
と、こともなげに言う。
船内では、英語のみならずスペイン語の通訳もつとめ、そして、日本語は帰国子女たちよりも達者に操り、漢字の変換も高速でこなす。てにをはを間違えない外国人に出会ったのも、これが初めてだった。
その頃、通訳駆け出しの若い自分はまだ、英語のみで手一杯だ。
「ど、どうすれば、そんなにたくさん言語をしゃべれるの?」
シンプルに聞いてみた。
「簡単だよ〜」と、気の抜けるほどの声でベンは答えてくれた。
「自己紹介文を、その言語で作ればいいんだよ。それも、とびきり面白く」
それで友達ができれば、学びは続くから、と。
本当に、夕食を食べながらのものの10分かそこらの会話だったはずだ。しかし、この時「達人」から直で学んだそのアドバイスは、自分の言語学習観を大きく変えた。
ことばを丸ごとものにする
英語通訳の現場では、必ずしも、ハーフ(ダブル)とか帰国子女じゃなく、いわゆる純ジャパニーズに出会うことは多い。自分もまた、旅は、本当にいろんな国に行ったけれど、どこか海外に住んだことは一度もない。
皆に共通しているのは、何かしらで、英語を「まるごと」身体に取り入れて、ものにしていること。それが洋楽で完コピする人もいれば、映画やドラマを暗唱する人もいれば、自分のように、出会ってきた英語の文章を、ひたすら音読しまくったタイプもいる。
実際、語学といえば、ほとんど音読しかしてこなかった。中学の頃から、英語の教科書のCDを、単に聞くとかわかるでなく、完全にその通りの間合い、声の太さ、ノリも含めて「成り切る」ことに努めた。その甲斐あってか、主人公のMike Davisがハンバーガーを2つと、アップルパイを注文するLesson6の場面を、今でも完璧に再現できてしまう。
高校も大学も、基本的にやっていたことは同じで、定期試験も、英語の受験も、好きな本の一節も、理解した後は、30回の音読を目指してひたすら読んでいた。毎回読み終えたら、豚のスタンプをひと押しして、苦労というより、声を出す=身体を使うエクササイズのような感覚だった。
自分だけの教科書をつくる
だから、原稿という「自分だけの教科書」を作って、とにもかくにもまるごと覚えて使ってみる、という、ベンのアドバイスはとても腑に落ちた。A4を1枚も書いてみれば、単語も構文もしっかり詰まっていて、それは違う文章にも応用ができる。何より、自分のことだからすぐに使える。
なるほど、とこちらはそれに愚直に従い、まずは1枚の自己紹介を作る。覚えたらさらに想定質問への問答まで作り込み、原稿は2枚、3枚、と増えていった。
その後は旅をしながら、仲良くなった人を見つけては、その国の言葉で原稿を翻訳、声をスマホに録音させてもらう、という、世界の音の収集が始まった。時にはビールをおごり、時にはチップを払いながら、フランス語、スペイン語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語、中国語、果ては広東語……と、言葉の世界はどんどんと広がっていった。
シュールなスペイン語学習
非常に面白いのは、この手法によれば、話す聞く、読む書く、のうち、一般的にもっとも日本人が苦手だとされている、「話す」能力。これがもっとも得意となる……というか、むしろ、これしかできない日本人が誕生する。
スペインの巡礼路を40日かけて900キロ超歩いていた頃、北スペインの田舎町でエネルギー補給にバルに寄れば、ん?英語?何言ってるの?、という雰囲気があって、ごく当たり前にスペイン語を話さねばならなかった。
日本での2週間、原稿の用意と練習はしてきたから、その仕込みの成果を繰り出す他ない。
「私は、日本から来た。この巡礼にずっと興味があった。旅が好きだ」
ここまでは言える(原稿どおり)。
「じゃふぉぢうあうぇおんぁんくぇ??」
でも、相手の返答が何を言ってるかわからない。
なので、原稿の次パラグラフに強引に移る。
「私の家族は5人。酒飲みの父は建築士だ。昼の3時から事務所でお茶の代わりにお酒を出す男だ!」
「えあぱおあんぁとぴえわふぁ!」
むこうも、なぜこちらがこの答えを言ってるのかがわからなくて、驚いた表情をしている。
しかし、こちらのそれぞれの物語は、ベン仕込みのユーモアたっぷり、しっかり面白く作られている。なので、ストーリーとして、相手を魅了してしまう。
「ろふぃえぽんあくぇしおうん?」
さらに聞かれるけれど、わからないし、噛み合わない。こちらは、冷や汗をかきながらも、用意したパラグラフを語り続けるのだ。
とてもシュールな時間だが、ここまでくると「どうもおもしろい日本人が来たぞ」という印象を与えるには十分。時には人だかりができ、歓待され、そういうことが続けば、スペイン語習得へのモチベーションはさらに高まる。
単語や文法も、ああ、さっきうまく言えなかった、と、ピンポイントで知りたいことがあるので、強い目的意識を持って、急速に吸収していく。巡礼路を歩きながら、片耳ではイヤホンで、ぶつぶつスペイン語の単語を聞きながらつぶやき、かつてないスピードで上達していった。
楽に、楽しく、急速に学ぶ
お仕着せの教科書でなく、まずは、自分(の家族や意見や体験)について、相手に楽しく伝えられること。すれば、いつか、友達ができる、のではなく、即、友達ができて、そこから必然的に、その言語を使っていく。
この「現場ありき」という、帰納法的アプローチは、どの多言語国家で育ったpolyglot(多言語話者)の友人たちから聞いてもその通り、だと言う。文法や単語を積み重ねて、いつか話せたら、ではなく、もう、今すぐでも私は話せる(ネタはこの原稿にある)、という臨戦態勢にまで仕込むこと。
言葉とは、結局、使う必要性と、現場の切実さから学んでいくのであって、教室と教科書に守られた場所では、野性の言語習得スイッチはなかなか入らない。しかし、そのスイッチが入り、モチベーションの波に乗れば、行きつ戻りつも、かけた時間に応じて成長していける。
このメソッドを続けてきて思ったのは、言語習得は、これほどまでに楽しく、楽なことだったのか、という感動に尽きる。もちろん、言葉は母語でさえも使いこなす、というレベルは難しく、先は長い。でも、間違いを恐れ、自分を表現したり、交流を楽しむとはほど遠い、トラウマ量産の英語学習に対して、この喜びは、大きな希望を与えてくれる。
どの言葉も、深めていけば、言葉にならないくらい深い。だからこそ、語学学習には、常に軽やかな楽観主義が似合う。
Polyglotへの道は続く
さて、達人のべンはその後、中国にわたり、あの国の複雑な、東西南北のあらゆる方言を完コピしては、自分で演じ切るというとんでもないことをやってのけていた。
その信じられない動画をぼんやり見ながら、あまりにも、それぞれの言葉と一体化する彼に、何を話してるのか、以上に、この人は一体誰なの?という感覚にさえなる。
言語を学ぶとは、真似ること。突き詰めると、それは成り切ることであり、憑依なんだ、ということをつくづく感じた。
以来、自分もまた言葉の学びを加速した。まったくのサラで始めた中国語の自己紹介にいたっては、A4 1枚をみっちり麻辣な火鍋への情熱で埋め尽くし、それはその後、スピーチコンテストの原稿となり、大阪大会での優勝へとつながった。
さらに、英語とフランス語とロシア語と中国語を話している時の、まったく異なる身体部位の使い方を突き詰めたり、複数の英語なまりを使い分けたりをしていて、少しずつ、あの達人の水準にも向かっているのかもしれない。
COLUMN
TEXT & EDIT : Kei Nakayama