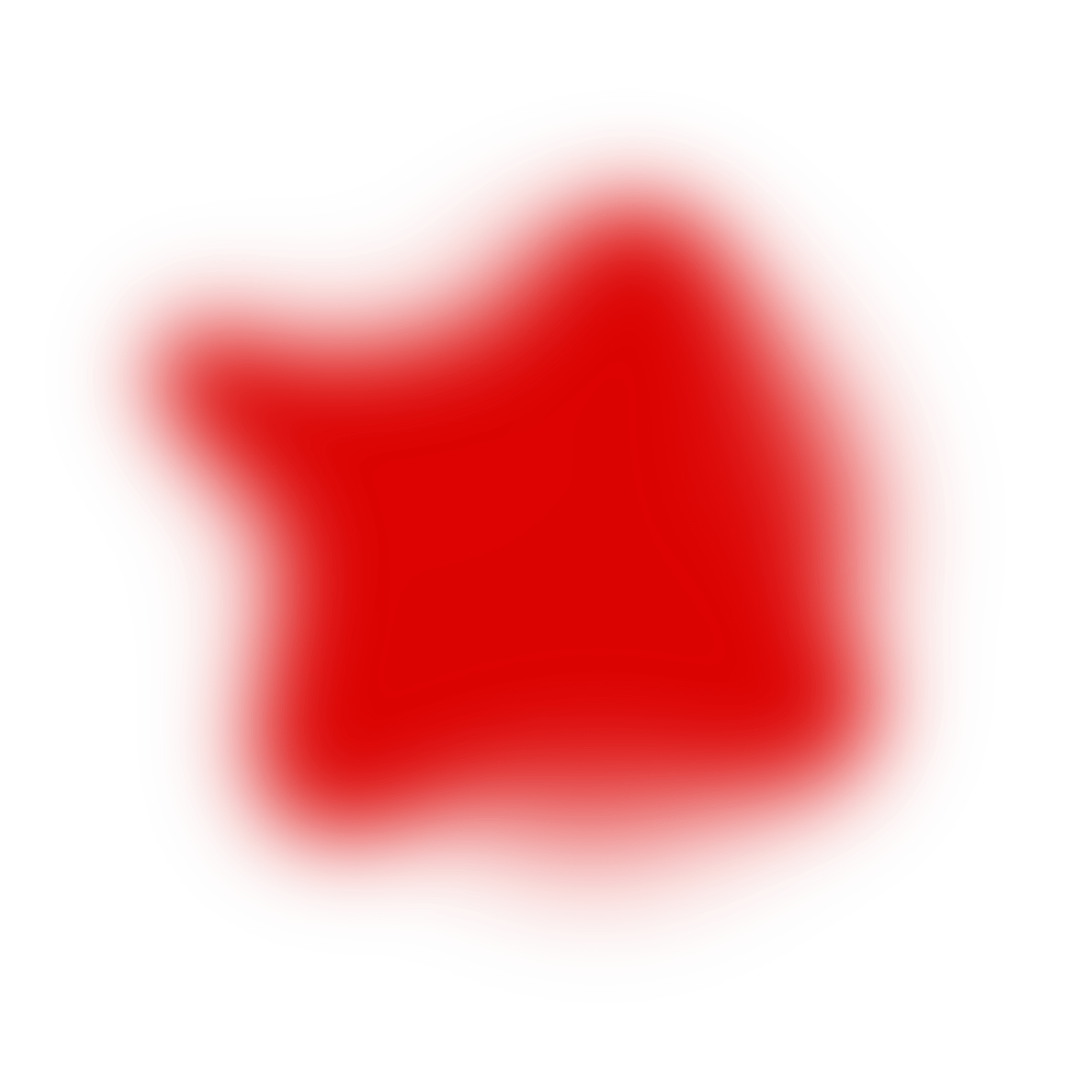講義でも通訳でも編集でも、いろんな仕事をする中で、いったい自分が何をしているのかと問えば、結局それは、場を作る、ということだと思っている。
場、というのは、グループ・ダイナミクスが起こる、ぬか床のようなもので、そこで交わされているものは、ことばを起点として、情報も、感情も人柄も、信頼から創発にまで及ぶ。
それをことばの冒険、と思うのは、いつもやりとりされることが、事前には予想しきれない、生き物のようなものだからだ。だから、作る、というよりは、それが生まれるために、自分が媒介者となる、という感覚を持っている。
冒険の手ほどき
大学卒業後には、世界を船で2周し、多い時には、年の半分を海外で過ごし、どこにいようが、コロナがあってもなくても、常に異文化の人たちと一緒に仕事をするのが、今では当たり前になった。
新年ということで、帰省しながら、改めて思い出していたけれど、ことばの冒険、に最初に誘ってくれたのは、思い返してもやはり、父だった。
父は建築設計士で、もともとたいそう寡黙な人だったが、自分が小学校の頃、縁あってミャンマーで仕事をするようになり、彼の国と行き来をするうちに、そこから、人が変わったように、いえーい、とテンションが上がって帰ってきた。その後も、上海で長く、現地の建設計画に関わったりと、その時は中国語をかなり短期でものにしていたり、なかなかのたくましさを見せていた。
そんな父が、仕事のクライアントと一緒に、南の島へ行くという。自分にとっては、初めて足を運ぶ海外。それもパラオ。友達が皆聞いたこともない、ミクロネシアの「地球最後の楽園」だ。15歳の自分は、ぜひとも一緒に行きたい、と志願した。
血と心が通うことば
パラオでのガイドはナカムラさん、という現地の日系人だったと思う。
得意の黒いサングラスをかけた父は、ミスターナカヤマ、となり、いえーい、わっほー、だな、と勢いで、せめるせめる。だいたい聞こえてきたのは、ノープロブレム、とか、グレイト、とか、ベリーベリーイージー、とか、そういう単発単語と、ほぼ日本語のミックスだった。
正しい学校の文法英語か、あるいは憧れの映画のネイティブ英語みたいに思っていた自分は、脳天に衝撃をくらった。あれ、これで、皆がハッピーにニコニコ過ごしている。これが、世界を生きてきた男・・・!
ことばと言っても、思考する道具にもなれば、ビジョンを表現したり、はたまた階級やら出身を示してしまうような、政治的な側面もある。しかしそこで見たのは、言うなれば現場でことを起こしたり、心を通わせたりする、生の異文化コミュニケーションだった。
異文化と交わる現場
パラオ体験からしばらくして、高校2年の夏に、イギリスはオックスフォードに短期留学をした。シャーロック・ホームズに憧れ、日本では人との語り合いが好きで、得意だった自分。しかし、それが多国籍の人たちが盛り上がる場に入った時、何が語られ、起こっているのかがどうもわからない。押しの強さや個のパワーに気圧され、さらに、もっと問題なのは笑いのツボがつかめないこと・・・目の前で腹を抱えて笑うメキシコ人が、もはや宇宙人に見えていた。
この瞬間から、自分の「正しい英語」は何らの実効性を持たないことがよくわかった。笑いのツボがわからないのはむこうも同じで、こちらの渾身のジョークにきょとんとして、お互いが未知との遭遇状態。自分の、日本人にしか伝わらないハイコンテクストなジョークが、いかに内目線なのか、と己を知ることにもつながった。そう、いまや自分に必要なのは、このクラスの講義を、放課後のパーティーを、席巻する言葉なのだ。
それ以来、ずっと、いかに、自分のポイントを、楽しく、勢いをつけて伝えるか、ということを考え続けた。それは単なる語学、を超えた、通い合う、とはどういうことを突き詰めることであり、エネルギーの発現回路を作っていくことだった。
強引さもだが、当然、伝える内容には、深さと、楽しさの両輪がいる。しかし、グダグダと伝えても、すぐに、I’m sorry, what? と、白目を剥かれてしまう。ここは学校ではなく、異文化交流の現場なのだ。
相手との共有できてない背景を想像し、都度都度理解度を観察する。言葉を噛み砕くか、言い換えをして、伝わらない具体的なディテールを少し離れて、俯瞰したり、大局観を出す。むこうが食い付いたら即座に追加情報を投げ込み、隙あらば、パッションというガソリンをドボドボと注ぐ。
場作りの実践は、大学になっても、自分の部屋を知人が気軽にやってこられる、しゃべりBarにしたり、外国人留学生寮にサロン空間と称して遊びに通ったりと続き、さらに10年近くシェアハウスに住み、最後は運営までしていた。
東京は代官山の古い一軒家で、ドイツ人やフランス人、アメリカ人たちと住みながら、日がな放置され続ける炊飯器を誰が洗うのか、に、滔々とロジックを展開するドイツ人ジャーナリストと当たり前に侃侃諤諤していると、だんだんと、世界との渡り歩き方が見えて来たような気がした。
物事は、習熟すると、脊髄反応で相手への対応が出てくる。喧嘩とか恋愛とか、そういう、当意即妙が求められる浮世の事柄の場合、このスピード感は大切で、影での英語の音読という、「身体トレーニング」がものをいった。
修羅場にもなる場
場を作る、ということを追求し続けていたら、それが嬉しくも仕事になっていった。
クルーズ船の通訳者として、船内の対話の場をコーディネートをしたり、雑誌の編集をしながら出版元の旅行会社に、世界の秘境ツアーに添乗員として送り込まれ、旅体験をリードしていくことも大きな経験となった。
結果として、20代の頃にべらぼうな数の国を仕事で訪れることができ、このツアーという世界遠征体験は、場と、それを構成する人間に対する重要な学びを与えてくれた。
ツアーが始まれば、初めてのモロッコ、パタゴニア、それにブータンである。わーい、などと、ワクワクしている時間も余裕もない。
参加者の7割以上をゆうに占める、好奇心旺盛なマダムたち。そのさらに2割のオピニオンリーダー的な、声の大きな人たちをどう導くか。それが問題である。ツアーのうちの、特に最初の3日は、楽しい雰囲気を作りながら、抑えるところを抑え、信頼関係が醸成されるよう全力を注ぐ。
もちろん会社からは、口が裂けても、初めて来たというなかれ、という厳命。事前リサーチしてきたことを、あたかも昔から知ってるかのように、自信と思いをもって伝えられるかどうかがキモだ。現地で、時には頼りになったり、時には絶望的に使えないガイドから、情報を引き出しつつ、遠隔で調べてきた客観的情報と、現地ならではのローカルストーリーを交えて、場を作っていく。
情報を伝える言葉と、行程を伝え、喧騒の中で、動線や時間や安全喚起を呼びかける言葉は、また別物だ。後者は、とにかく、くりかえし、何度も問いかけ、とにかく一点の曇りも誤解も生まれないクリアさを追求する。
自分の考える正しさではなく、その場とその状況を主語に、どうやって健やかな場が生まれるか、ということに苦心していくと、実際に作り上げられていくのは、まさに信頼を肝とする「世論」だったりする。
なんせ、旅をするのは秘境界。やれ、迷子にはじまり、腹痛だの、バスが来ないだの、ダブルブッキングだの、橋が洪水で流された、火山が噴火した(すべての交通網は麻痺だ)、と、トラブルが起こらない、ということが、むしろない。この修羅場をくぐり抜けられるかに、己の実力がかかっている。
初速の対応には神が宿る。あるいは、そこを間違えると、神が荒ぶる。
あらぁ、いい添乗員さんね、と、前半に醸成された世論が中山さんは悪くないわよ、とかばってくれることもあれば、一歩ボタンを掛け違えると、最初から中山さんはダメだった(あの青二才どうかと思ってたわ)というような遡求的な不条理に、参加者のマダムたちも、態度を状況によってコロコロ変える。本人たちにその自覚はなくとも。
ここまで、政治学を専攻して学んだ「世論」というものを、自分ごととして、なまなましく感じたことはなかった。だから、いかにして、10日間とか2週間というツアーの間、自分の得意な知識や言語をどう伝えるか、一個一個の起こる現象が、いかに特別で恵まれているか、ということを、場に注入し続けて、皆のいわば士気を上げ続ける、ということをしていた。
場は山場を迎える
そうこうしていると、ツアーの後半には、ひとつの山場がやって来る。
勤務先の旅行会社特有の慣習。それは、異郷の地で胃袋が疲れたお客様のために「そうめん」を作るというイベントだ(そして胃袋と心を掴み、リピーター率は7割を超えていた)。
初めて行ったモロッコでは、アラビア語もフランス語もしゃべれない中で、しかし時間もなく切羽詰まっているので、迷わず厨房に突撃。両手には、20名分を超えて重い、高級「揖保乃糸」に、むろん薬味とつゆ(原液)がある。
え?何?となっているシェフに、さあ、パスタジャポネを作ろう、と言い放ち、必死に限られた時間の中で湯を沸かし、冷水で冷やし、盛り付ける。厨房をかけずりまわる、まさにドタバタ。ある種の不条理なタスクだったが、それが完了した時に、ああ、成し遂げた、と、自分の境界をひとつ超えたような気持ちになった。
皆が喜び、士気が最高になった場に身を置きながら、プロであり、利他であり、行であり、いろんなことを、身をもって理解できたように思った。
どだい、外国語を学習すると、どうしても勉強とか、正しさ、にとらわれがちだが、実際、ことばは、正しい運用方法では、なく、表現のあり方であり、それによって自分と他者のどういう関係性、通い合いが作られるか、なのだと思う。
ことばは、エネルギーとなって、場を生み出す。参加者の持つさまざまな現場が接続され、場そのものも、修羅場や山場を持ちながら、収束していく。そのダイナミズムを、通訳でも、教育でも、ガイドの現場でもいつも感じている。
海外のツアーで学んだことは、自分が今度は、京都の里山でインバウンドのガイドになったり、そのガイドを育てる時に、途方もない気づきの視点を与えてくれる。その意味では、本当に得難い体験だったと今でも思う。
しかし、今でも。あ、集合時間寝坊した、とか、やばい、早くそうめん作らなきゃ、という夢に、冷や汗とともに、時おり起こされることがある。
COLUMN
TEXT & EDIT : Kei Nakayama