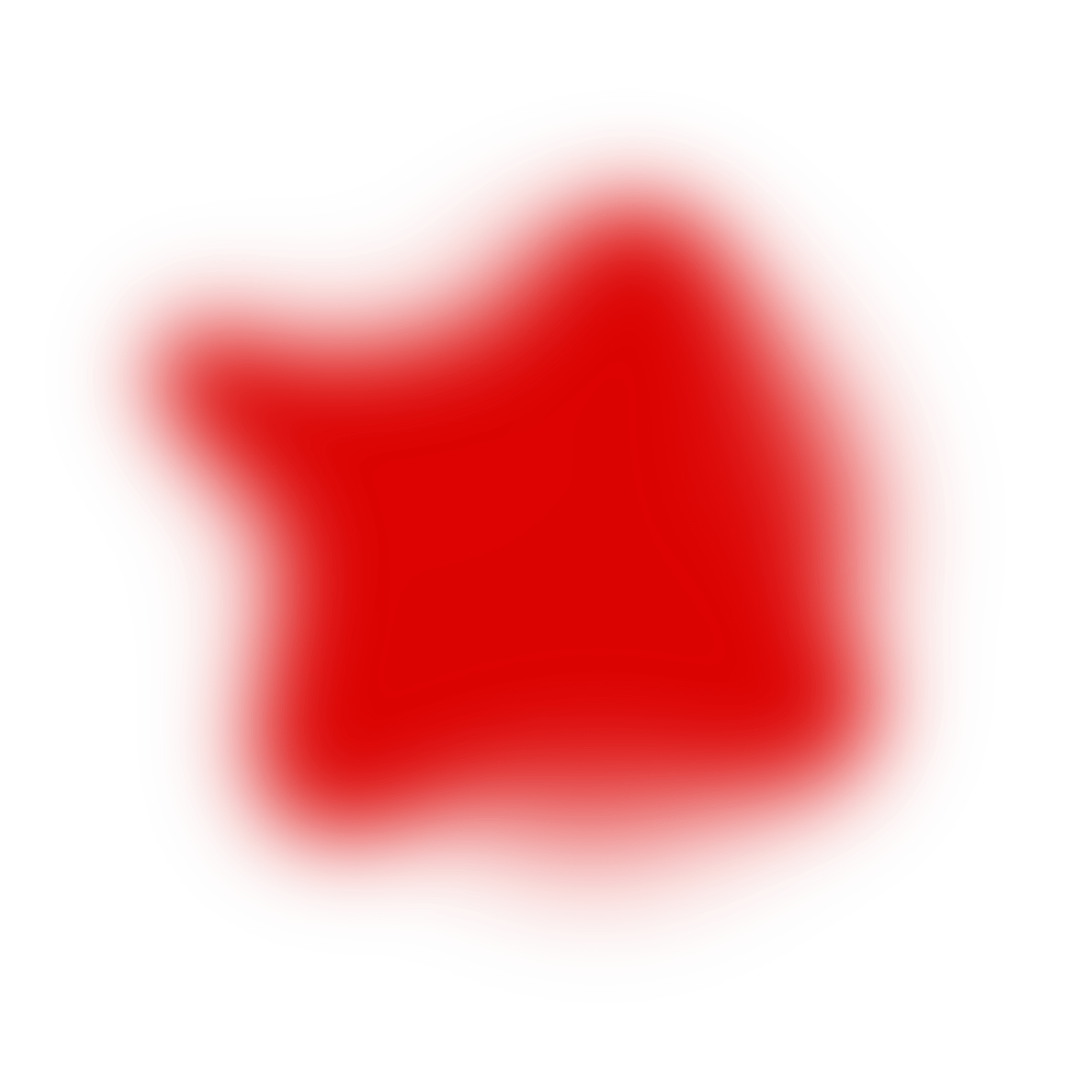はじめまして。私は大学院を出てから28年間製薬企業に勤め、創薬研究、経営企画、広報などを行ってきました。現在は、現代アートと産業をつなげて産業界にイノベーションを興す仕組み作りにチャレンジしています。いずれの場合も、「新しい物事を創造して社会をよい方向に変える」ということがキーポイントになります。このような創造の場では、取り組んでいる人の中で「思考の飛躍」が起きています。Transcreationでも、元の言語の世界観から大きく飛躍することで新しい表現を創造できるのではないかと思います。
そこで私のコラムでは、「思考の飛躍」に焦点をあて、どういう時に思考が飛躍するのか、どうすれば思考を飛躍させることができるのかといったことを考えてみたいと思います。
思考の飛躍がつないだmRNAワクチン開発
製薬業界での最近のイノベーションは、なんといっても新型コロナウイルスに対するmRNAワクチンでしょう。mRNAという物質を医薬品に使った初めての事例であるだけでなく、通常数年を要するワクチン開発を1年かからずに達成してしまったのです。しかし、このワクチンの誕生には、一人の研究者の長い長い戦いがありました。
ハンガリー生まれのカリコー・カタリン(Karikó Katalin)が大学生だった1976年、RNAが有用な物質の生産に使えるという報告が、彼女の思考を飛躍させました。以来、mRNAの可能性を信じて研究を続けることになります。1976年というと、バイオベンチャーのパイオニアであるジェネンテック社が設立された年、ものすごく早い時にmRNAに着目したのです。この後遺伝子工学が急速に進歩し、遺伝子治療という概念も出てきますが、主流はmRNAではなくDNAでした。DNAは安定で使いやすいのに対し、mRNAはすぐ壊れてしまうのです。医薬品は、製造から患者さんに投与され薬効を発揮するまで安定である必要があります。当時、多くの研究者は、mRNAは薬としては使えないと考えていました。カリコー博士の思考は常識に囚われないものでしたが、その分なかなか理解されず研究費を獲得するのにも苦労しました。
米国ペンシルベニア大学に移っていたカリコー博士が、たまたまドリュー・ワイスマン(Drew Weissman)教授と出会ったことで時計の針が動き始めます。2005年にmRNAが医薬品としての可能性を示唆する結果を、2012年には動物に投与したmRNAが効果を発揮する結果を示すことができました。しかし、それでも製薬企業は興味を示しませんでした。そんな中、2005年の論文を読んで、これは独創的で画期的な研究だと思考を飛躍させた研究者が2人いました。デリック・ロッシ博士とウール・シャヒン博士。その後ロッシ博士はモデルナ社を、シャヒン博士はビオンテック社を創業。この2社が、今回のmRNAワクチン開発を実現させました。

私達が、ウイルス発見からわずか1年あまりでワクチンを接種できるという恩恵は、カリコー博士が45年前に飛躍させた思考がかろうじて受け継がれてきたことによるのです。そして、この研究はワクチン開発の概念を根底から覆すと期待されています。
捨象された色を掬う
私が「思考の飛躍」に注目するようになったのは、現代アートに出会ったことがきっかけです。「AOYAMA Unlimited」というアートイベントを主宰し、ギャラリーを訪れ多くのアーティストと話をしています。彼らが社会を観る視点や思考のユニークさにいつも驚かされます。どうして常識を覆すコンセプトを創ることができるのかと聴くと、丹念にリサーチして根本から考えていると思考が飛躍すると言います。
現代美術家の杉本博司氏は、写真を中心に発表しており、写真装置の研究を続けています。研究を続けていると、写真装置だけでなく光そのものをも研究する必要があると気づきました。
光の研究の先駆者はアイザック・ニュートン、白色と思われていた太陽光をプリズムで分けると虹色になることを見つけました。ニュートンが光の研究を行ったのは、ロンドンがペストのパンデミックに見舞われ、故郷のウールソープに滞在していたときでした。

杉本氏は、ニュートンの分光計を改良し光を分けてみました。太陽光は7色(赤、橙、黄、緑、青、藍、紫)から成ることは皆さんもよく知っていると思います。杉本氏は、赤と橙の間にも無数の色があること、そのグラデーションがとても美しいことに気づきます。製造中止になってしまったポラロイドフィルムを買いあさり、このグラデーションを撮影し『OPTICKS』として発表しました。
この作品を制作している過程で、飛躍した思考が杉本氏の頭に生まれました。「科学は世界のいろいろな事象に名前をつけることで理解しようとする。しかし、名付けることで世界の微細な全体を切り落としてしまうのではないか。捨象されてしまった色の間でこそ世界を実感できるような気がする。そして、科学から落ちこぼれる世界を掬い取るのがアートの役割ではないか。」
このコンセプトは、杉本氏が科学や歴史の研究も丹念に行っているからこそ導くことができたのだと思います。そして、科学や産業とアートとのあるべき姿を示してくれています。
詩的な技術の創造を目指して
新型コロナウイルスのパンデミックは、テレワーク関連の技術を急速に進歩させました。これらの技術によって私もかなり助けられました。しかし、テレワークによって絶え間なく会議が入るようになり、出社していた時よりも忙しくなったという人がけっこういます。この状況に対して大阪市立大学の斎藤幸平氏は以下のように語っています。「最近登場したのは『管理機構的な技術』ばかり。いつでもメールが書け、仕事ができるようになったがタイムマシンのような『詩的な技術』は現れない。労働生産性や生活の効率が高まるだけで、人生は豊かにならない。詩的な技術を生むには、たくさんの自由な時間が必要だ。まずは我々が管理されていることを自覚し、詩的な技術が生まれやすい環境をつくる必要がある。」
詩的な技術を生むには「思考の飛躍」が必要です。そのためには丹念にリサーチして根本から考えることのできる時間を確保しなければなりません。
アーティストの久門剛史氏は、「アーティストはあえて極端な非効率性を求め、その無駄の細部に真実を見いだそうとする場合があるが、企業では効率性が求められる。しかし、双方とも世界をより良くしようとしている点では共通しているので、お互いがフラットな関係を持てる場をいかにつくっていくかが重要だ」と語っています。
アーティストが思考の飛躍させるために取り入れている非効率性の効果を科学や産業界も目を向けるべき時がきています。自分が興味をもった事象をじっくり観察し、考える。そして「思考の飛躍」がいかにワクワクすることかを実際に体験する。このような環境ができてくれば、効率を求めるなかでふるい落としてきた事象や、カリコー博士の研究のようなマイナーな分野をも掬い取ることができ、多くの詩的な技術が創造されるに違いありません。
COLUMN
TEXT & EDIT: Kazuhide Hasegawa