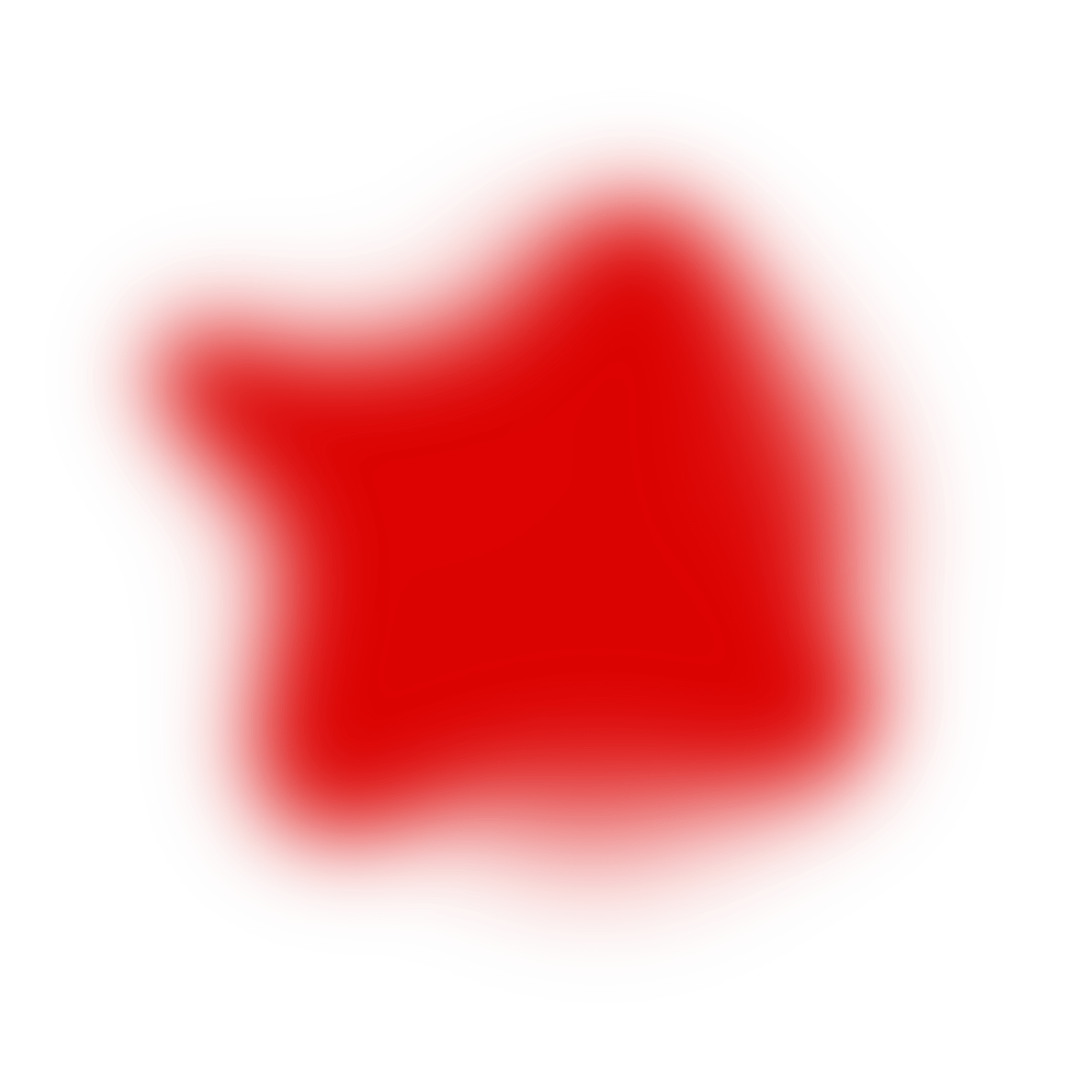優しき生の耕人たち
彼らの仕事を眺めながらまず気づいたことは、いずれもがエコロジー、デモクラシー、あるいはポエジー(芸術一般)のどれか(あるいはすべて)に携わっている非常に尊敬出来る素敵な人達だということであった。しかも分野の多様さにも関わらず、世界観だけではなく、仕事のメソッド、そして自分たちもしばしば気づかないまま目指している究極の方向性においてまで、多くの共通点をもっていた。その後間もなく、フランスの哲学者、精神分析医で、環境運動家でもあったフェリックス・ガタリ(1930−1992)の『三つのエコロジー』に出会い、この三つ(エコロジー、デモクラシー、ポエジー)の活動が、ガタリの言う三つの環境(自然、社会、精神)において発揮されるエコロジーのことだと気づくことになった。
通常エコロジーと言うと、自然環境の問題とだけ考えがちだが、エコロジーをその語源に帰って*5「ある環境が健全に成立するための条件を研究し実現するための営み」と解釈する時、それは、社会環境にも、我々の精神の環境にも応用出来るものである。いわゆるエコロジーとは自然環境に対して適用されたエコロジーであり、デモクラシーは、社会環境に適用されたエコロジー。そしてポエジー(芸術一般)は、精神療法や哲学とともに、精神環境に対して適用されるエコロジーということが出来るのだ。すべてエコロジーなのだから、彼らが互いに似通って見えたのも道理である。ガタリは「精神、社会、環境に対する行動を切離す」のを不適切とし、「この三つの領域の劣化を直視」*6して、三つ(二つでもいいだろう)の領域を緊密に関係づけながら、エコロジーを実践して行く必要があると説いた*7。例えば、「ひきこもり」は当事者にとっては、精神環境の問題であるが、同時に、それを生み出す社会環境の問題として捉えない限り、その真の原因を究明することも、根本的な解決を探る可能性も断たれてしまうだろう。
ガタリは、こうして、三つの異なる環境における問題(危機)を解決する作業のすべてを一様にエコロジーと定義しながら、同時にそれらの背後に共通の核心的な原因を見定める視点を提示してくれたのである。この連載でも、一見かけ離れた多くの分野で活動する人々の仕事が、専門を分ける境界の奥底で、どうつながり合っているのか、書き進めるうちにその辺りも明らかにして行ければと思っている。
ここで、多岐に渡る分野において登場して来た人々が「優しき生の耕人たち」と言えるための基本的な必要条件をいくつか列挙してみるが、いずれもが微妙にずれながらもかなり緊密に重なって、あるテクスチャーを織り上げているのが分るだろう。
まず、先ほど挙げたhumbleという形容詞が誰にも当てはまるが、そこには複数の重要な意味が含まれている。英語のhumbleは、ラテン語のhumusという語から派生しているが、humusは、土、土壌、腐食土等を意味する言葉で、人間に適用されても当然大地(よって、自然)との結びつきを強く感じさせる。そして土に近い人と言う意味を経由して、腰の低さ、謙譲さ、身分の低さなどを意味するイタリア語のumiltà (英語のhumbleness)という言葉にもつながっている。従ってhumbleとは、自然の知を学びながら育み創造することを重視し、また社会的に恵まれない境遇にある人達をも大事にする態度を示す言葉である。「優しき生の耕人たち」は、現代の多くのクリエイターや専門家たちのトレンドとは反対に自己顕示欲を抑え、名声を求めることを目的とせず(今回扱う対象には著名な人々も入って来るが、彼らとて、名声が目的ではない)、つねにhumbleな(控えめで、社会的な弱者を慮り、自然を尊重する)姿勢を堅持している。
トリノ工科大学建築学部の教授でこの研究の共同研究者であるアンドレア・ボッコ*8によれば、スーフィズムにあるQutbという概念が、ここで言うhumblenessの質を的確に表しているという。Qutbとは、スーフィズムにおいて、軸、柱、中心、等を意味し、神と直接につながり、民を正しく導く賢者を指す言葉であるが、Qutbの存在は大衆には知られていない、否、知られてもいけないことになっている。自らが消えることで他者の役に立つ、究極の黒子のような存在である。「優しき生の耕人たち」の多くは、人知れず、またしばしば自らも意識しないままに、この世界においてQutbとして機能しているような人々なのだ。
また、古代中国のQutbとも言える老子の「生而不有/為而不恃/功成而弗居」*9((聖人は) 何かを生み出しても自分の物とせず、何かを成してもそれに頼らず(それを自分の功にしない)、成功してもそこに留まらない。)という言葉には、自らの作業の成果に対する所有欲の決定的な欠如が謳われているが、「優しき生の耕人たち」と言える人々も、自らの知や方法論を正確に伝達することには尽力するが、その独占性や知的所有権には興味がなく、経験や知恵を自慢せずに惜しみなく他者と共有する。つまり、彼らの創造行為は「作者」に密着した「作品」という、閉じられた枠をもって完結することを目指さず、常に「開いた」状態を作りながら、他者の生や知との関りの中で展開されるのである。
例えば、演劇において演出家が自分の舞台作品の美的側面とその帰結としての成功を一番の目的とせず(とは言え、舞台の芸術的価値を疎かにすると言う意味ではない)、それを作る上で、役者たち本人の人間性や観客の置かれた社会的状況等と真剣に対話しながら、そのプロセスにおいて、自分が関わる人々の生に具体的な変化をもたらすことに専心するとき、その仕事は演出家の名前と密着した「作品」であることをやめ、そこに関わるすべての人々に「開いた」真のコミュニティ的な状態を生むことになる。「優しき生の耕人たち」の仕事には、往々にして、斯様な特徴が見られる。
そして今言ったように、彼らの活動が、必ず何かを「具体的に変容させる力を持っている」と言うことも重要である。変容の内容は、社会のあり方、人の態度や能力、環境の状況、物づくりの方法など、多種多様だが、理論のレベルに留まったり、「作品」創造に拘るのではなく、それを通して他の人や生に具体的な変化を生むことを目指しているのである。例えば、建築家が、自分の建築を「作品」として完結させようとしているのか、それを利用する人々の生活環境を具体的に改善することにフォーカスを置いているかの違いである。
そして、この「変化」というのは、しばしば、「治癒」(ケア)ないし「修復」的な意味を持っている。そもそもエコロジーとは、ある環境内における不健康な状態の「治癒」であり、「修復」の作業なのである。その意味では、先ほどのエコロジーの解釈を「ある環境内のあらゆる要素の間にハーモニーが戻るべく、治癒、修復する作業」と言い換えても良いかもしれない。ただ、ある環境内における不健康な状態の治癒、修復とは、必然的に、そのような状態を生み出した現代文明の創造力に対する治癒、修復となる。ある意味で、こう言えるかもしれない。エコロジーを考えるとは、究極的には、人類の創造力について考えることなのだと。
- 脚注
- 5. 「エコロジー」(ecology)は、通常「生態学」と訳されるが、エコノミー(economy)とともに、「エコ」(eco)という接頭語を持っており、それはギリシャ語のオイコス(οἶκος)、つまり「家」を意味する語に由来している。エコノミーの本来の意味が「エコ」(家)+ノモス(秩序、管理)つまり家の正しいやりくりだとすると、エコロジーは、家が成立するための学問(ロゴス)ということになるので、少し広義に考えれば、家=ある環境が健全に成立するための条件を研究し実現するための営みと言うことが出来る。
- 6. フェリックス・ガタリ著『三つのエコロジー』平凡社ライブラリー、2008年、20頁。
- 7. これに近いメッセージをやはり世界レベルで発信したのは、現法王フランシスコである。彼は2015年の回勅ラウダート・シの中で、自然環境のエコロジーと社会環境のエコロジーを連携して実践することの重要さを強調していた。
- 8. 彼の著作のなかでも、『石造りのように柔軟な – 北イタリア山村地帯の建築技術と生活の戦略』(2015)と『バーナード・ルドフスキー – 生活技術のデザイナー』(2021出版予定)の二冊は、拙訳により鹿島出版会から出版されている。
- 9. ブルーノ・ムナーリがその著作『モノからモノが生まれる』の巻頭の題辞として引用している。
次ページ:創造力について考える
PROFILE
Yosuke Taki
多木 陽介
アーティスト、批評家