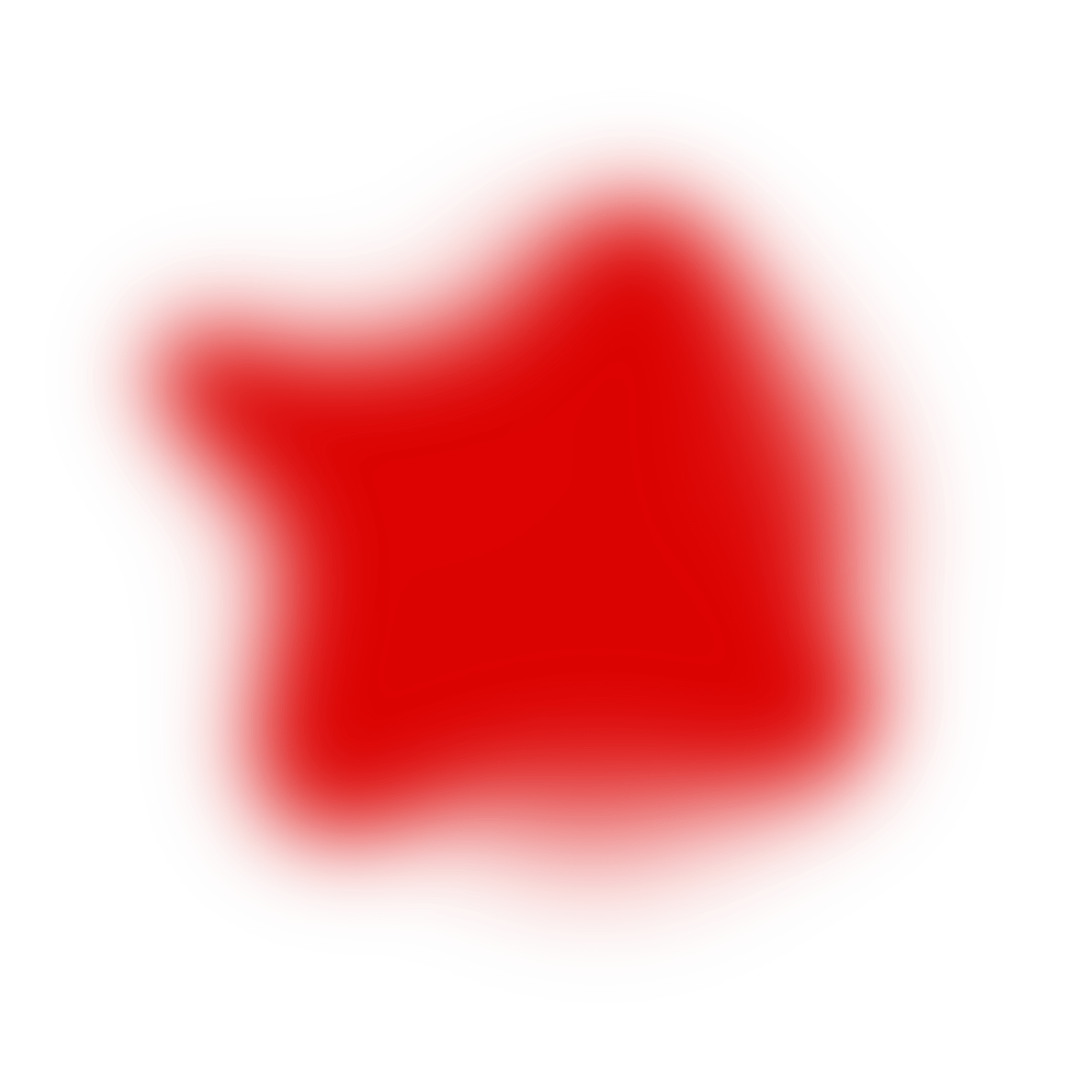創造力について考える
ところで、創造力とは、芸術家や科学者らだけの有する特殊な能力だけではない。もっと日常レベルでも、家の片付けや料理に始まり、あらゆる行為の中に生きている。問題を見いだし、計画性を持って、あるいは即興的に解決して行く、生存のための知恵と技術全般を指すと言えばいいだろう。ただ、我々がつい忘れがちなのは、地球上で創造力をもつのが、我々人間だけではないという事実である。自然にも見事な創造力が備わっているのに、歴史は人間が唯一の創造者であるかのように語って来た。歴史書や歴史の授業に自然が登場することはまずないし、たとえ登場しても、それは、創造力はおろか、生命すら通わぬ背景画として描かれるだけだった。まして洗練された広告技術の駆使する創造力の系譜を辿ると実は両生類の誕生の瞬間とつながっている等と考える人はまずいない。
ところが、歴史的に見ても、創造力(creativity, creatività, créativité, creatividad, Kreativität)とは、元々創造主だけに許された特権的な能力を指す言葉で、人間に許されていたのはせいぜい発明(invention)であり、創造(creation)と言う言葉が人間の属性になったのは、やっと一八世紀から一九世紀になる頃であった。
産業革命を経て、人類の創造と生産の力が爆発的に強大化するのと創造力(creativity)という語が人間の手中に収まるのが時期を一にしているのも偶然ではない。機械文明とともに近代に突入する時期に、人類自身の創造力に変化が起こり、人間と技術と自然の間の関係は激変する。そしていよいよ人類が創造主となったかと思いきや、それもつかの間、一瞬にして人類は歴史を創造する舞台の主役の座を追われ、多くの思想家や歴史家が指摘するように、今や技術(ないし技術文明:単に全てのテクノロジーの総体ではなく、その裏にある徹底した合理性を追求する論理を指す)そのものが、歴史を紡ぎ出す「創造力」の圧倒的な主体となっている。疑問をもたずに資本主義社会に生活する人間は、みな、自律した主体であることを放棄し、技術の機構に奉仕する作業員に成り下がっている。テクノロジーを使いこなしているつもりで、実は訓練を受けてそれに奉仕する端末と化しているのだ。ギュンター・アンダースが言ったように、人間は「時代遅れ」になってしまったのである。
そもそも、創造力とは、「自然」と「人間」(身体およびその意識、無意識を含めた精神の働き)と「技術」という三者が輪舞を踊るように調和をもって発揮される能力で、その内部におけるバランスは非常にデリケートなものである。ところが、産業革命以降、「技術」だけが異様に強大化し、三者間のバランスは完全に失われ、協合することを忘れた「技術」が人間を抑圧、調教し、自然を搾取するというのが、現代の創造力のモデルになってしまっている。
個々の人間の創造力だけでなく、ある時代の歴史を刻一刻紡ぎ出す、壮大な「歴史の創造力」というものを想定するとき、それが今や、極めてアンバランスで、危険なモンスターとなって地球に伸し掛かっており、そこに生じる各次元のストレスは、もう限界に達している。気候変動や各種の汚染が自然環境を苛み、社会格差がエスカレートし、特に高度な資本主義の圧力が限界に達している先進国では、人間の絆の場であった社会が単なる経済交換の場に変容し、ひきこもり、鬱病、社会的孤独など、精神面に関わる多様な問題も発生している。そんな自然、社会、精神の各環境における危機的な現象の数々も、その元凶はここにあると言えるだろう。
創造力に常にこの危険性が潜むことは、古代ギリシャ以来知られていたことだ。創造力は、一方では人々の糧と美、そして幸せを生み出すことが出来るが、他方、甚大なカタストロフィ(破壊と病、孤独と苦悩)をもたらす原因にもなる。『クラフツマン』のなかでリチャード・セネットが指摘するように*10、火山と鍛冶の神で平和文明の創造者の象徴とされるヘファイストスの対には、破壊の神パンドラがいつもいたのであり、この両者が人間の創造力の二つの側面を象徴していた。神話の中では神からの恐ろしい贈り物として描かれるパンドラの箱だが、近現代人はそれが人間自身の創造力によって作られていることを知っている。二十世紀最大の発明である原子力が史上最大の悲劇をもたらしたことを思い出すだけで十分だろう。このカタストロフィを、文明という蛹の中で成熟しゆく黒い大きな蝶に喩える時、蛹の中で巨大な黒い蝶が変態に至るまでの間にその成長を助けるのは、文明そのものの創造力である。地震とか津波という自然のエネルギーや戦争がカタストロフィをもたらすと思いがちだが、実は、戦争や災害のもたらす巨大なエネルギーがすることと言えば、蛹の殻に亀裂を入れるだけであり、問題はそれまでに内側で蝶の成長が完了しているかどうかである。地震や津波を予防することは出来ないが、その衝撃で万一殻に亀裂が入っても、内側で羽化の準備が出来ていなければ、カタストロフィにはつながらない。 逆に蝶が羽化してしまったら、お終いである。原発事故の瞬間を想像して頂けばいい。阪神淡路大震災での神戸の悲劇も、地震だけのせいではなく、ああした密集した都市を人間がつくりあげていたからこそ起こったものだった。巨大地震が砂漠に起こってもそれはカタストロフィにはならなかっただろう。黒い蝶が絶対羽化しないように、前もって幼虫の変態を抑止すること、成長を促進する現在の文明の危険な創造力を安全な創造力に変換させる修復作業に勤しむこと、それこそが、現代を生きる我々全員の最大の使命であることは明らかだろう。そして、それを既に実践し、我々にその可能性を教えてくれるのが「優しき生の耕人たち」であり、彼らの「控えめな創造力」なのである。
次回から、それぞれの「優しき生の耕人」がどのような形で(しばしばそのことを明確に認識することもなく)歴史の創造力の修復作業に貢献しているかを具体的な事例にそって見て行くことにする。現在のところ、ほぼ十回を予定しているが、世界(人間)像の修復を目指す芸術(写真、文学、他)、控えめな創造力を発揮するデザイン、植物の創造力に任せた庭づくり、演者の人間性から出発する身体芸術、患者の人間性への視線を回復する医療、生命体のように立ち上がる建築、市民が自ら責任と創意をもって作り、管理する公共空間(みんなの場所)、エコロジーと深く結びついた食の探求、そして監獄における文化芸術活動など、多様な領域から多彩な形で「控えめな創造力」が発揮される事例を拾い上げて紹介して行くつもりである。
- 脚注
- 10. リチャード・セネット著『クラフツマン』筑摩書房、2016年、18頁
PROFILE
Yosuke Taki
多木 陽介
アーティスト、批評家