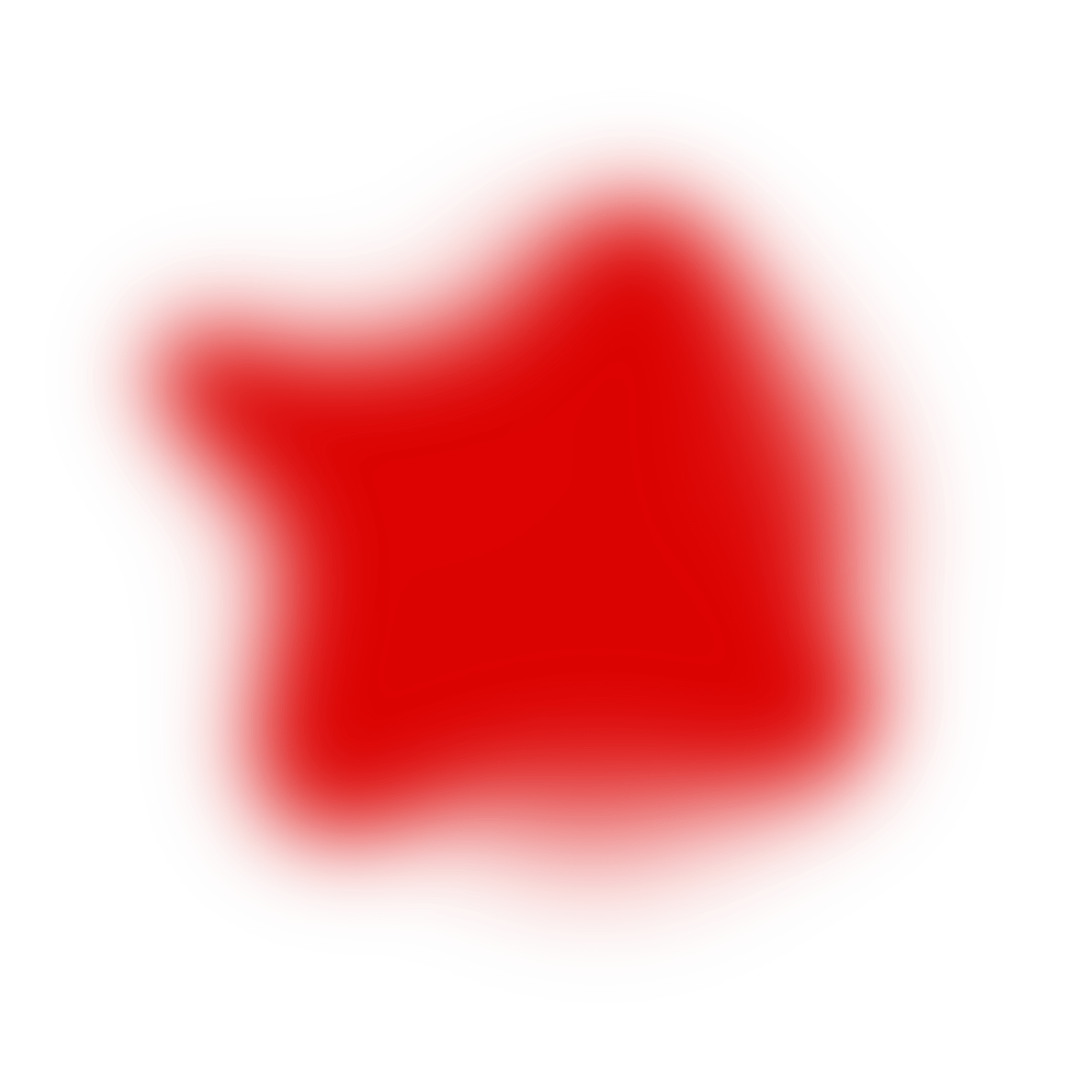第一回:はじめに
言葉の根っこ
トランスクリエーション(transcreation)という用語は、本来広告やマーケティングの業界の用語で、メッセージの本来の意味や求めたい効果を変えずに、だが、新しい言語で伝わりやすいく、またより魅力的な形で伝えるための翻訳術を指している。そして、そこには、翻訳された新たな言語でメッセージを受け取る人への心理的、文化的配慮が大きく盛り込まれている。全く新しい内容を発明することではないが、異なるコンテクスト、文化においてオリジナルの内容をより効果的に伝えるための基本的だが、非常に重要な手法である。ただ、私のように、長年異国に外国人として生活し、翻訳業にも携わる人間にとっては、トランスクリエーションは、仕事だけでなく日常生活の中で、日々否応なく使うことになるごく当たり前の生存戦略でもある。日本の様々な現象をただ現地語に訳しても、日本の社会、文化、芸術などの背景を知らない相手に対して、それでは何も正確に伝えることにならないからだ。場合によっては、若干の補足説明を必要とするし、場合によっては、こちらの人達の想像力に訴えやすい比喩や表現に頼る必要があるわけだが、いずれにせよ、双方の言語環境、文化環境、それぞれの国民の心理などにも精通している必要がある。
ここで、広告業界というコンテクストを離れて、トランスクリエーションという言葉の根っこの方に降りながら、そこで働く創造力に注目してみよう。「トランスtrans」という接頭語には、「越えて、移って、横切って、通り抜けて、ずれて…」というような意味があるが、ということは、いつも元、原点があるということである。ゼロや無から出発することはしないで、必ず何か元があり、そのオリジナルの本質を損なわない形で少しスライドさせて新しい生命を与える、言って見れば「転用」の創造力(creativity)なのだ。
「転用」と言えば、日本の伝統にも「本歌取り」とか「見立て」と言う手法があるように、非常に古い創造力の形式であるが、さらに言うと、人間の歴史を超えて生物の進化のプロセスでも度々利用されていた野生の創造力なのである。例えば、魚類が陸に上がって来た時、呼吸のためにエラを大改造して肺を作ったのではない。魚の体内には、既に浮き袋という魚体の浮力を調整するための大きな空気袋があったのだが、沢山空気は入るし、既に周囲に血管も通っているし、これを肺にする方が、負荷が少なくて済むと進化の知能が判断し、浮き袋の「転用」が決まったのである。進化プロセスにおける「見立て」の最高傑作の一つと言っても良いだろう。二〇世紀人は「見立て」をデュシャンの命名にそって「レディメイド」と呼び、後出のアキッレ・カスティリオーニらの駆使したデザインの手法としても知られているが、実は、その起源は人類以前に遡るような深遠な根をもっていたのである。
トランスクリエーションとレディメイドを比べると、前者は言葉や形は変えても意味や機能を変換しないが、後者は言葉や形は変えずに、その意味や機能を読み替えるというように、修辞的にみるとちょうど反対だが、その創造形式にはいずれも「転用」の身振りが含まれていて、「肺」の誕生の場合は、確かにレディメイドでありながら、「呼吸」という一貫した目的を、異なる環境において異なる器官を使って実現したということにおいては、まさに原・トランスクリエーションと言ってもいいエピソードである。
つまり、トランスクリエーションと言う言葉の根っこには、現代の資本主義社会どころか、遠く太古の野生に由来する創造力が隠れており、それは、造物主のように、ゼロから自分でなにかを生み出すと言うよりは、目の前にある既成物(物、素材、自然、他)を手に取って、その本質を慎重入念に研究し、その可能性を己の目的にそって最大限に引き出そうとするタイプの創造力であった。
自著『メイキング』のなかで、やはりこの種の創造力に注目する人類学者のティム・インゴルドは、この「作る」というよりも「育てる」ないし「成長する」と言った方が相応しいような創造力の特徴を、humble(控えめな、慎み深い)という形容詞で表現している*1。「控えめな創造力」というのは、つまり、人間が頭の中で考えた物をそのまま素材で再現する、つまり、人間(作者)のヴィジョンを素材や世界に押し付ける人間中心主義的な創造力ではなく、素材や環境との精妙な対話の中から結果として何かが生まれて来るような創造のあり方を指しているのだが、それが何と、前世紀末頃から、この「控えめな創造力」を備えた、しかもそれまでの世界にはあまり見かけなかった新しい職能の人々が、まだまだマイナーな形とは言え、一見関係なく見える多様な分野において揃って登場し始めたのである。
新しい職能の登場
資本主義がエスカレーションして、もうこれ以上行くと環境にも社会にも、また人々の精神にとっても極めて危険なレベルを越えてしまうと言う認識を世界的に初めて訴えたのは、ローマクラブ第一回の報告書「成長の限界」(1972)であったが、ちょうど高度成長期を迎える中で、その認識はごく少数の人達を除くと、大勢からは、しばらく完全に無視されることになった*2。だが大衆レベルでもこの認識が徐々に広がり始めたのは、前世紀末、八〇年代の末くらいからだろうか。科学と理性、そして産業に夢を託した西欧文明の破綻が明らかになり、自然環境、社会環境、そして人間の精神環境に極めて深刻な危機的状況が現れ始めたからだ。そして、ちょうど同じ頃から、それまであまり見かけることのなかった新しい職能の人々がちらほらと登場し始めた。建築家や庭師など、伝統的な職能の場合には、肩書きはそのままに、それまでの時代にはなかった新たな態度や使命をもつようになって来た。中にはまだ名前の付けようのない職能の人々もいた。
自然、社会、人間の精神に対する彼らの態度や世界観は、かつてのローマクラブの宣言と通じる認識を共有しており、活動のメソッド、つまり思考と創造の方法論に至るまで、全く異種のかけ離れた分野に分かれて活動する彼らの間に、はっきりとした共通点が多々認められた。それぞれの分野をばらばらに見ていてはこの全般的な傾向を認めることは出来なかっただろう。多くの分野の活動を同じ地平において眺めてみることで初めて、それぞれの分野に現れた「新しい職能」のすべてが、実は、同じ一つの歴史的現象を構成していることが見えて来たのである。
私がこの現象に気づくに至った切っ掛けは、ある意味で偶然だった。2007年にイタリア近代デザインの父の一人、アキッレ・カスティリオーニについての著作『アキッレ・カスティリオーニ – 自由の探求としてのデザイン』(アクシス刊)を上梓した後で、「もし、今カスティリオーニのような人間がいたら、何をしているだろうか?」と問いつつ周囲を見回してみると、意外にもデザインより、教育、経済、政治、環境、建築、芸術、金融、食、農業、福祉、医療、町づくり、その他、かなり多岐に渡る分野にカスティリオーニの「後継者」といえる人達がいることが見えて来た。
私が言う、「カスティリオーニのような人間」とは、どんな特徴を持っている人間なのか。書籍を上梓した直後に、書籍のプレゼンや講演で各地を回るにあたり、改めて自著を要約しながら、最も重要なポイントが三点あることに気がついた。
まず一つ目は、彼が、同時代(戦後〜二十世紀後半)の社会にとって本当に必要なことを追求したということ。つまり創造における社会性の重視である。戦後間もなく、イタリアでまだデザインと言う外国語が人口に膾炙しておらず、ブルーノ・ムナーリ(1907−1998)やアキッレ・カスティリオーニ(1918−2002)、エンツォ・マーリ(1932−2020)等と言うデザイナーたちが、それを「プロジェッタツィオーネ」(progettazione: イタリア語で、プロジェクトを考え、実践する、と言う意味)と呼んでいた時代のデザインは、現代社会におけるデザインとは全く異質な物で、(売れない物は作らなかったが)私企業の利潤追求よりも、人々の生活環境の改善を目指す社会奉仕的な活動であった。
もう一つは、プロジェクトの価値が、最終的なフォルム以上に、そのプロセスに一貫性をもって浸透したある正しさ(倫理)の度合いによって判断されていたということである。意外かもしれないが、倫理が美学より優先されていたのだ。イタリアンデザインも六十年代後半からはこの傾向を逆転させてしまうが、確かにカスティリオーニの作品は、一見奇抜に見えようとも、すべてが必ず機能的な理由を持って生まれて来たものであって、消費文化的な「色気」を生み出すデザインとは一切無縁であった。彼らにとっての美とは、あくまで正しいプロセスによる結果を意味していたのだ。
そして三つ目は、デザイナーとして、基本的に工業製品の創造に関わりながら、彼の創造プロセスが非常に繊細で、自然のそれを思わせるということであった。カスティリオーニ自身は、自然とかエコロジーと言う意識は特に持っていなかったが、彼の創造力の展開のし方には、どこか野菜を育てる農夫に似た態度、いや、もっと言うと、生命や生態自体の内部の精妙な創造プロセスを思わせるところが多々あったが、それこそ、「作る」というよりも「育てる」ないし「成長する」と言う概念に近い、インゴルドの言う「控えめな創造力」であった。後続の回で詳述するが、ムナーリやカスティリオーニ兄弟ら、戦後のイタリアンデザインの父と言える人達の創造力の最大の特徴は、まさにこの「控えめな創造力」にあったのだ。
ここまで考えた後、「もし、今カスティリオーニのような人間がいたら、何をしているだろうか?どこにそう言う人がいるだろうか?」と自問しながら、つまり、この三つのポイントを基準にしながら世界を見回した時に、実に多様な分野に渡って、互いに非常に良く似た「新しい職能」の人達の姿が見えて来たのである。彼らの登場は偶然ではない。まるで、危機に瀕した歴史自身の秘められた憂慮の声に応えるかのように彼らは登場して来たのである。それが一つの歴史的現象であることを明確にするために、私は彼らに一つの同じ名前「優しき生の耕人たち」(Gentle Cultivators of Life)をつけて呼ぶことにし、彼らについての研究を始めることにした。もう十年以上前だ。欧州と日本で「優しき生の耕人たち」と言える人々を探し当て、毎回インタビューをしながら十回記事を書いた連載*3がその始まりだったが、その後、この基礎研究は幅を広げ、それを基に私が「移動教室」と呼んでいる教育活動*4等も実践されるようになった。かつての連載は、インタビュー記事に毛の生えた程度のものだったが、今回の連載では、そこにはなかった主題も加えつつ、それぞれの主題をさらに掘り下げながら、「優しき生の耕人たち」という歴史的な現象のもつ深い意味を探ろうと思う。
- 脚注
- 1. ティム・インゴルド著『メイキング』左右社、2017年、55頁。
- 2. その前後に、レイチェル・カーソンの『沈黙の春』は、1962年に出ているし、シューマッハーの『スモール・イズ・ビューティフル』も1973年に出ていたが、当時の彼らの主張は大勢からはほぼ完全に無視されて、砂漠に向けて話しているようなものだった。
- 3. 連載「優しき生の耕人たち」(アクシス、2009年2月〜2010年8月)
- 4. 2015年12月より、クリエイティブネットワークセンター大阪メビックの主催を受けて、若手のクリエイターを対象にした短期研修活動をイタリアで企画、実践している。
次ページ:優しき生の耕人たち
PROFILE
Yosuke Taki
多木 陽介
アーティスト、批評家